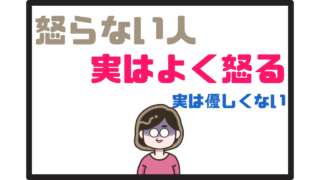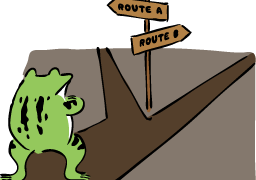【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ぜひおすすめしたい」と感じたのでご紹介です。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作ってもらえます
「なんでこんなにわかるの?」と思えるほど的確で、わかりやすく言語化してくださり、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください
耐え忍ぶ。
忍者は時に、鬼のような辛さを乗り越える力を垣間見せます。
そんな力、ある方がおかしい。いえ、ない方が厳しい視線を注がれる我らがジャパン。
忍耐力がない人は我慢弱く、継続できない特徴があり、他者との共存環境では少し不利なことが多いかもしれません。
「それならば忍耐力を高めたい!」と思いますが、忍耐力を養うことはいわば修行、直ぐにどうこうできる話ではなかったりします。
そこで、忍耐力がない人ならではの特性を生かし、逃げちゃおう。
そんな話をお伝えします。
鬼ごっこで逃げるのが上手な人は、忍耐力がなかろうが困りません。
忍耐力がない人ならではの考え方や、自らの在り方の活用となる理解のために、忍耐力がない人の特徴と特性を生かした応用が役立つことを願います。
Contents
忍耐力がない人の特徴

忍耐力がない人の特徴13選
1、違和感に絶えられない
興味・関心に沿い、自らの在り方に反した違和感に絶えられないために、継続困難となる特徴です。
2、恐怖に対する免疫がない
嫌、認めたくない、知りたくない、味わいたくないと、あらゆる抵抗を抱く恐怖が起きた時に、対抗する力がありません。
恐怖への免疫は経験によって育むため、恐怖と対峙した際に、自らの認識を自覚して対処しようとした経験の少なさを物語ります。
恐怖に対する経験が少ないのではなく、恐怖と対面した際に、「自分でどう対処する?」という認識に持っていった経験が少なく、継続的に恐怖を味わったことがあまりない人です。
3、逃げ癖がある
恐怖を味わった際に逃げる選択をする傾向があります。
継続的に物事を経験する機会が減り、認識や対処は“逃げる、頼る”になりがちです。
4、自分の限界を決めている
脳の認知情報をとにかく信じます。
目に見えて把握できる“確実な立証”を大切にする、理論立てる人間性。
自らの観念や価値観をモットーに、限界も制限も脳内にあるもので定めます。
恐怖への免疫がないことから、未知の世界に対する恐怖には屈服を即決する特徴となります。
5、孤独はNG
寂しがり屋と孤独の狭間におり、人と過ごす時間とプライベートの自分を共に欲します。
人が嫌いでも孤独になることに耐えられず、恐怖から逃げられない状態になってしまうので、孤独は断固NGです。
6、自己内観能力が乏しい
自分という存在理解は脳内記憶を主体にし、今の自分ではなく、これまでの自分として理解する傾向があり、自己認識に偏りがある特徴です。
自分を内外から認識するバランスが崩れ、自己責任の念が乏しく、特に自己内観として内側から己を認識する機会を設けることが少なく、恐怖への免疫がないというものです。
7、他者認識力に長けている
内観が乏しくとも、自らを客観的に見る認識や、他者の立場や目線として見る認識に長けています。
自分を外側から見ることに特化した特徴で、他者の気持ちへの配慮、他者の思考や考え、行動に対する予測や予想が上手で、中には他者が何を思って何をするかを容易に察知する人もいます。
8、先読み力がある
他者認識にて予測する力を持ち、事前に先に起きることを読む能力に長けています。
鬼ごっこで逃げるのが上手な人の典型でして、一手先から何手も先まで読む人もおり、自らの経験や他者の経験測からシナリオを作るのが上手です。
経験が増すごとにシナリオをストーリーとして創作する技も加わり、相手の先読みを相手以上に理解している、なんてことも起きます。
9、世渡り上手
その場の自分にとって一番利益がある状態の選択が上手な特徴です。
逃げることで自らに利益(満足や納得)を得られる人でもあります。
10、甘え上手
人に頼り、任せることが上手な特徴です。
相手に諦めさせる術を持つというものでもあります。
11、言い訳や演技が流暢
自分を責められ追い詰められることから脱した経験が多く、如何に自らに傷を付けず、不毛な時間を削除し、嫌なことがふりかかる可能性を限りなく低くするかの答えを見出す速度が速いです。
この経験を自分のために役立てないと、自己否定や現実逃避が癖になる人もいますが、忍耐がないことでの不利な状況の経験値の高さから、言い訳や演技が流暢で多彩、時間稼ぎや、問題の焦点を外すテクニック、誤魔化し、諦めさせることが上手です。
12、理論的に行動や思考を準備する
頭の中で何かが起きた時の脱出口を常に用意しています。
最悪の事態になることがほとんどなく、行動や思考を理論的に考えられる人です。
理論立てて計算式がないものを理解できず、パニックや疑心暗鬼、人間不信になる人もいます。
13、自己愛が強く、他者からの干渉が苦手
自己愛は自己中心を表し、自らがこの世の中心で人生を創造し、主体性を持って主観である理解があります。
自分が主人公である認識が汚されていません。
自分勝手やわがままとは全くの別概念、人間として持つ自らが中心で人生を創っている基本原理に忠実なさまです。
他者からの干渉や強引な影響など、自らを変えようとする行為や人間が苦手です。
以上が、特徴でした。
忍耐力がない人の特徴 一覧
- 違和感に絶えられない
- 恐怖に対する免疫がない
- 逃げ癖がある
- 自分の限界を決めている
- 孤独はNG
- 自己内観能力が乏しい
- 他者認識力に長けている
- 先読み力がある
- 世渡り上手
- 甘え上手
- 言い訳や演技が流暢
- 理論的に行動や思考を準備する
- 自己愛が強く、他者からの干渉が苦手
※向上心がない人の詳細は、【悪いことではなく幸せ】向上心がない人は仕事を辞めてフィジーに行けばいい をどうぞ。
忍耐力がない人の改善
忍耐力がないとは?
そもそも忍耐力とは何でしょうか。
辞書にはこのように書いてあります。
辛いことや苦しみなどを耐え忍ぶ力、辛抱する力
耐え忍ぶことに我慢や忍耐という言葉が当てはまり、辛いことを乗り越える一つの力だとわかります。
雑多な世の中です。不安や恐怖がはびこり、苦痛に危険、嫌なことなどいくらでもあります。
忍耐力があると辛い状況や状態を乗り越える手助けになるので、あったらいいものです。
忍耐経験によって新しい世界や認識が見え、自らの価値観や観念を変える機会にも育みにもなり、自己成長としての恩恵がたくさんある大切なものです。
忍耐力は誰しもに必要ではない
着目したいのは、忍耐力はあくまで辛いことを乗り越えるための一つの力にすぎないことです。
辛いことがなければ忍耐の“に”の字も出てこなくなり、国や環境が変われば価値観も違うので必要だと思う人すらいないかもしれません。
忍耐力は必要なものと言う以上に、欲するものかと思います。
不安や恐怖が多い環境であればあるほどに忍耐力は欲されるもので、辛さや苦しさを乗り越えて自力での育みを求める価値観があればあるほどに、大切で欠かせない力となります。
人間性と価値観の合致にて忍耐力を欲する人もいれば、欲しない人もいます。
なぜならば、忍耐力以外にも辛さを乗り越える力はあるからです。
適応力と、逃げる力です。
※他にもたくさんありますが、「忍耐力がない人といえば」というものがこれら
適応力を持っているか、逃げる力を持っているか(または欲するか)によって、忍耐力がないことはポイポイッと投げ捨てて燃やしてもなーんにも起きません。
選択肢は一つだけではないので、自分の生き方や求めるものに応じて選択すれば、忍耐力がないことの不利はなくなります。
あくまで必要な人のみが欲することで育む力の一つが忍耐力です。
忍耐力がない人の改善となる考え方
忍耐力がない人は恐怖への免疫がない特徴があります。
「恐怖はマジで嫌だ」という。
忍耐力がなければないほどにとにかく嫌がります。
恐怖はどこかしこにはびこる菌のようなもので、いつどこで怒られたり、否定されたり、未知や苦痛や危険があるか、寝ぼけて気づいたら夜中にお墓のど真ん中、きゃーなんてことも起きます。
忍耐力があれば、辛いけど耐えて忍ぶ辛抱で何とか対処できるかもしれません。
しかし、恐怖とは自分にとって本当に嫌なことなので、強引に恐怖と対峙して少しでも継続して味わってしまったらもう泡吹いて失神しかねません。
これまで逃げ続けてきたからこそ忍耐力がないという、確実な経過と生まれてからの経歴があるので、忍耐力の養いも大切ですが時間(継続)がかかります。
継続が困難な特徴から、養おうとすればするほどに苦しみが増えて苦行になり、確実性がとにかく乏しい改善であることを本人が最も自覚してしまうと思います。
忍耐力がない人は理論的で確実な立証を好む傾向もあるので、継続して養い鍛えるといった、長期的な見込みに対する行動継続も合わない可能性が高く、精神論や頑張ればなんとかなる的なノリは合いません。
忍耐力がない人の特徴に合わせた考え方となるのが、逃げちゃう。
忍耐力がない人の改善は、現状の能力や才能や経験を伸ばすことで辛さを乗り越える力を養う、逃げが活用的です。
※逃げるのが癖になった末路は、【逃げ癖の末路はタブー】本当は逃げていない理解が直すポイント をどうぞ。
忍耐力がない人と逃げる力の関係性
忍耐力がない人は肉体や精神を酷使する以上に、頭を使うことで対処してきた経歴があります。
思考優位で頭の使い方に慣れている。
他者認識に優れ、物事や自分や他者を客観的に見ることがとても上手。逃げる力をもたらす基盤になります。
わかりやすくするために、一度鬼ごっこをイメージしてみてください。
鬼ごっこで逃げるのが得意な人は、走るのが早いことも大事ですが、それ以上にその場の環境の認識度と、他者の考えていることを予測して捉える、他者認識と先読み力があります。
ずる賢い人です。
鬼ごっこだけでなくとも、普段授業を受けていないのにテストの点数がいい人もこれに該当し、いい意味でずるくて賢い、妬まれて嫌われることもあると思います。
「あれ~、○○君だけ見つかんないな~、どこだぁ?」と鬼が困っている時、「ずっと後ろにいたよ、てへぺろ」と声を掛けたら、驚かせすぎて鬼の腰を砕いちゃうような人です。
忍耐力がない場合には、これを目指します。
ずる賢いことは良い意味。忍耐力がない人の特徴と相性がピッタリです。
忍耐力がない人は逃げるのが上手な特徴を兼ね揃えている
日本の環境では、我慢や忍耐は重要視される一つの力ですので、幼少期から養う人が多いです。
しかし、逃げられる環境があれば忍耐力は養われず、逃げる力が養われます。
「耐え忍ぶことが善」かどうかは人それぞれのルールであり自己満足ですので、自分の歴史と経験に合わせると、私達はどんな環境でも何かしらの能力を付ける生活を過ごしています。
何かを選択しなければ、それ以外を選択して自然と経験しています。
「忍耐力も大切、忍耐力以上に大切なものがある人もいる」
「忍耐力がない人だからこそ逃げる力を使うといいよね」という考え方です。
逃げる力の活用方法
能力開花には、なんと言っても“開き直り”が有効です。
「逃げるの最高」という。
逃げるとはピューっとその場から遠ざかるとんずらだけではなく、鬼ごっこの逃げと同じイメージですので、スタイルがたくさんあります。
ただ嫌なことから逃げるとんずらは、
「大丈夫かな?追ってこないかな?」
「あの人に次会ったらヤバいな」
「あの会社逃げるように辞めたから近くにいくのやめよう」
などとより恐怖を増やす自作自演になるので、恐怖を嫌がる在り方に自ら矛盾を作り苦しめてしまいます。
耐えられないからこそ逃げるのであれば、恐怖を増やす逃げ方は自分のためにならないので、特性を生かします。
そこで逃げるスタイルの自覚をします。
自分に合わせた逃げるスタイルを明確にする
自分に合わせたスタイルの抽出には、逃げる力を自分のために活用する前提認識が大切で、如何に自己内観力を上げるかがポイントです。
内観とは、内側を掘り下げるように自分を知ることで、行動や思考や感情の基(動機や過程)を見つめることです。
実際にやってみると体感するのは、内観には必ず継続する力が要ることです。
ここで選択が起きます。
自らの内側の理解を育むか、逃げる力を特化させるか。
どちらも人それぞれに大切な道ですが、内観力は忍耐力の育みにもなり、逃げる力のスタイル確立にもなります。
内観を継続できれば忍耐力を付けていく過程に入りますが、継続ができなくとも少しでも内観のさわりを経験することで、逃げる力のスタイル選択に役立ちます。
望遠鏡で鬼を把握する逃げ方か、鬼の先読みをするか、環境認識による隠れ方の見出しや、周囲との同化(気配や存在感をなくす)か、別人になりすまして鬼と自然に関わるか、話術でタッチされない交渉術で錯乱させるか、相手の気持ちを汲み取って協力サイドに回るか、他者にお願いして逃げる役を代わりコーヒー牛乳を飲んで一休みか…。
内観ができてもできなくても、どんな逃げ方を習得できるか、育めるか、鍛えられるかを見極めてスタイルを自覚することで、逃げる力の育みが始まります。
※逃げるメリットとデメリットは、【甘えでいい】嫌なことから逃げるメリットとデメリットに甘えの真意 をどうぞ。
逃げる力の確立ポイント
逃げるとは世渡り上手の真髄。その場の環境認知からの自らの在り方を自在に変える演技へんげです。
そのためにも自己内観力はない方が良かったりします。
内観はスタイルの確立時に必要ですが、その後はない方が逃げる力の育みとなります。
逃げる力のポイントとなるのは他者認識、客観視、先読み、理論、言い訳、演技です。
テストの山当てもこれらの活用に該当します。
逃げる力に特に関与するのが“他者認識力”です。
如何に他者の立場・目線になって物事を理解するか、他者の認識に近付けて行動と思考を把握するかです。
他者認識の育みには先読みの自己検証と、他者の行動結果の把握が大切です。
他者の認識目線に近付ける意識を持つことで、忍耐力がない人ならではの逃げることでの改善方法となります。
※逃げる力の詳細は、逃げるのが上手い人は逃げ方を知る│ピューっととんずらはご法度をご覧ください。

忍耐力がない人の特徴と生き方 まとめ
忍耐力も逃げる力も人それぞれの過去の歴史があり、生き方の構築となる価値観と観念から作られた大切な能力であり、育みの結果です。
共に大切であることには、現状を変えるスタイルとして二つの道が理由としてあります。
一つは自分にないものを手に入れる道。
一つは自分にあるものをさらに伸ばす道。
私達の人生は時間という制限のある中で進んでいますので、何かに費やせば何かは得られず、何かを得られなければ何かを得ます。
忍耐力を養い鍛えることも大事ですが、忍耐力がない人が忍耐力を付けるとは、爪のない白鳥に、「もぐらのように穴を掘れ」と言っているようなものかもしれません。
「穴掘るなら、飛ぶよ」
バサッ、バサッ。
ないものを習得することも大切ですが、恐怖や苦痛や危険がある場合、少し一呼吸してからどうするか考えたいものです。
ポイントとなるのが“自己内観力”です。
忍耐力の養いにもなり、逃げるスタイルの確立として、逃げる力の特化を進める基盤作りにもなります。
逃げる力の育みに飽きた時には、内観を鍛えて忍耐力を高めることにフォーカスしてもいいかもしれません。飽きたら逃げる力、そしてまた忍耐力、たまに適応力なんて具合もありですね。
どんな形でも人それぞれの生き方ですので、何か気楽で自己を高める道の歩みとなれば、良き塩梅かと思います。
現状持っているものを伸ばし、自分自身に合わせた考え方として、忍耐力がない人ならではの生き方の構築の一つの理解となれば幸いです。
それでは、忍耐力がない人の特徴と改善するための逃げる力のお話を終了します。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ピン!」と来た方はぜひお試しください。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作成してもらえます
的確にわかりやすく言語化してくださるため、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください