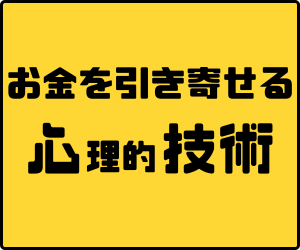「私が残りの仕事はやっておきますので」
「元気なさそうだからこれ買っといたよ、蛇の瓶漬け」
「それじゃあ順番に鍋をよそっていくからね、あ、グラス空いてるよ」
気を使うことは他者との関わりでは大切なツールです。
しかし、嫌われる可能性にもなります。
使い方如何で良いようにも悪いようにもなる気使い。
良かれと思ったことが嫌われる理由になってしまうと、どうすればいいのかわからなくなってしまいます。
ここでは、気を使うことで嫌われる方へ向けて、気を使う改善方法をお伝えします。
- 気を使うとはどういうこと?
- 気を使って嫌われるのはなぜ?
- 気の使い方とは?
気には使い方があり、気が利くとの大きな違いがあります。
嫌われないための改善としてお役立ちできれば幸いです。
Contents
気を使う人は嫌われる

気を使うと良い悪いが極端になる
「気を使う」の「気」とは、目の前や周囲の状態や状況を意味します。
気を使うとは、周囲の状況を把握し、見合ったことをする。
心配りや配慮、気を配るとも言えるものです。
「気」をどのようになんのために使うかによって、人に好かれも嫌われもします。
気を使う際に必ず起きるのは、自ら発信して他者に行為していることです。
自らが始まり、気を使って相手に何かします。
相手に利益を与えるのか、自らに利益を与えるのか、両方に利益を与えるのか、どういった影響を与えるかは気を使う人に全てがかかっています。
ここで言う利益とは、満足や納得の取得、不満足や不納得のなさです。
- 相手に利益を与える
…気を使うと好かれるか利用される - 相手と自分に利益を与える
…コミュニケーションとなり好かれる - 自分に利益を与える
…相手を利用する形になり、嫌われる
お困りの場合には気の使い方が間違っているかもしれません。
「私は気を使うぞ」と行動するため、嫌われる場合には押し付けや他者利用にて一方的な気の使い方になる可能性があります。
知らずの内に自分のためにしかなっていない、相手の利益になっていないことが起きている状態です。
気を使う人が嫌われる原因
気を使うことは片や善、片や悪。悪意のない悪、騙す気のない勘違いや思い込みといったものもあります。
気を使う際に優しさは必要ありません。
大切なのは、「何がその場に、その状態に、その人に、その状況に見合うか?」の理解です。
状況に見合った対処や人間関係の工夫であるため、行為の目的は明確に自分のためです。
- 嫌々気を使えません
- 相手のためだけに気を使えません
- 状況把握がなければ気を使えません
- 他者の状態や状況を認識できていなければ気を使えません
気を使う際、相互の認識ができていないと、使い方がおかしくなってしまいます。
使い方がおかしくなると、他者に利益がないだけではなく迷惑をかけ、知らぬ間に「自分のため」だけにフォーカスして相手を利用してしまうことが起きて嫌われます。
自分のために気を使うと嫌われる
「気を使う」の「使う」は使用する本人に主導権があります。
「気が利く」の「利く」は効果があるか否かを相手が決め、主導権の概念すらありません。
行為の主導権があると少しトリッキーなことが起きます。
「他者のため」だと無意識に認識すると、気づかぬ内に自分のために気を使います。
自分のためにみんなの分の鍋を取り分ける、適格に相槌を入れる、話の腰を折らない、みんなが嫌な顔をしないように休日イベントに参加する、つまらない話に愛想笑い…と行為が加速します。
相手のためだと思いながら、真相は自分のため。
悪意なく自らが喜び、満足し、納得し、不安と恐怖を感じないための行為となり、他者を利用してしまうと嫌われます。
※優しいからこその件は、【カオスの与え】優しすぎる人が嫌われる理由4つ&大切なこと をどうぞ。
優しさの押し付けになると嫌われる
気を使うには常識やルールの使用が多くなります。
状況や状態に見合わせるために、既に大枠として定まった規範に則ります。
- ご飯を食べる時には箸を取ってあげる
- グラスが空いていれば、注文を聞いてあげる
- 体調が悪そうであれば、定型の声をかける
優しさがあれば相手の状態や状況や心理を加味して気が利く人になりますが、自分のためであれば常識的行動をとったことでうまく収まります。
ここで一つ起きることがあります。
常識やルールに則って気を使うことで、自らに喜びや効果をもたらします。
自分が喜ぶのは大切ですが、人に気を使うことで自らを満足や納得させると、結果的に他者利用が露呈して嫌われます。
本人に悪意はなくても、常識やルールに準じた「これをすれば心配りだよ、優しさだよ」という行為は、自分が喜ぶための優しさの押し付けとなります。
気の使い方は気づかぬ内に使い方が変わりやすく、無自覚に他者利用、ルールに準じた正当化と自負の主導権、押し付けになります。
気を使われる側は大きな違和感と嫌悪を抱き、嫌いになります。
※嫌われる理由がわからない時は、嫌われる理由がわからない時に知ってほしい│何故か嫌われるスピリチュアルと心理 をご覧ください。
気を使うと相手を疲れさせる
気を使って疲れる場合、相手も同様に疲れています。
気を使うことは、「労力を尽くし、嫌なことも我慢して、あなたのためにしている」と思えるさまがあります。
相手の立場や目線の認識がない場合には、自分の思考内ルールへの従順と、規律に則った正しい照合にフォーカスし、相手が実際にどう思っているかを知らずに、相手のためだと思い込みやすくなります。
自負や正当化意識があると、相手へのフォーカスがなくなっていき、悪意なく意図せずに「自分のためだけ」の気を使う行為に変わります。
この状態になると、気を使うことで相手にも気を使わせます。
気を使う自分に自負や自信を持つと、空間の主導権を握ろうとする
自負や自信を抱くと主導権を握り、嫌なことが起きない空間を無意識に作ります。
相手をアウェイにする空間創作は不安や恐怖を味わわない行為となり、上下関係を作ります。
上下関係で気を使うと、相手は嫌でも気を使う対応を求められます。または主導権を奪い取る戦いになります。
多少の関わりでも上下だ主導権だになると、相手は嫌がり気を使うことで対応し、知らぬ間に相手に無理矢理気を使わせてしまい、関わる相手は疲れてしまいます。
わかりやすい例は、自宅に訪れた人に対してお茶を出そうとして、「あ、お気使いなく」と気を使う時です。
「あ、そうですか、じゃあ出しません」とはなかなかいきません。
気を使うとは気を使わせることでもあり、使い方が大切です。
場所や環境によって使いどころがあり、いつでもどこでも気を使うことは使い方の逸脱になりかねません。
※気を使ってめんどくさがられる詳細は、【トラップ有】気を使いすぎる人がめんどくさい理由6つ&見直し点 をどうぞ。
気を使う人の改善方法
気を使う目的を明確にする
「何のために私は気を使うのだろう?」の答えを明確にします。
気を使うか否かは、一つの大きな選択を誰しもにさせます。
喜びを選ぶか、恐怖(苦痛)のなさを選ぶか。
気を使えば否定や馬鹿にされることが減り、道徳の教科書に反しない姿を作り、他からの影響による不利益をなくせます。
自分らしくなくとも、常識やルールに準じた姿を善とした価値観や観念を持っていれば疲れることもなく、違和感なく空気を読んで見合った行為に及べます。
自らの意思や目的をはっきりさせると、「自分のため」の目的を忘れずに、「社会性のため、みんなのため、他者のため」と目的を追加でき、「自分のためだけ、相手のためだけ」という逸脱になりません。
気を使う際の選択は気づきにくいものです。
意識的に気を使う際にしている選択の自覚が大切です。
※人と話すのが疲れる時の解決策は、【繊細な人の対人戦略】人と話すと苦痛で疲れるようになった時のポイント をご覧ください。
気の使い方を知る
気を使って嫌われ、疲れてしまう場合、「知らぬ間に」「気づかぬ内に」という無自覚で気の使い方が逸脱していると考えられます。
良かれと思って気を使う行為が空回りし、相手の配慮が逆に相手に迷惑をかけてしまうという状態です。
改善は気の使い方を知ることです。
気を使うには気づくのが初め
気を使える人は空気を読むプロですので、状況把握能力に長けています。
状況把握は認識力とも言い、状態や状況に気づくことで認識します。
気がついた時、あの人の状態、この時の状況、あのさまの意味、何を求めている?とさまざまに認識する段階に入り、気を使うための材料集めとなります。
これがないと気を使う意味や目的が定まらないので、使い方は自然と逸脱していきます。
気を使う際には気づくことが前提条件です。
気づいた後に選択
気づいたら気を使うか使わないか、気を配るか利かせるかという選択をします。
気づくと選択の余裕があり、自分次第で使うか否かを選べます。
思い出してください。気を使うとは自ら発信して、自らが発端でする状況に見合った行為です。
「気を使え」と言われた段階で後手、気を使う方法は逸脱します。
※この場合には何をどうすればよかったかを学ぶ機会になる
如何に気を使うために気づくか否かが最も重要であり、気づくと自分の意思で行動できるので疲れにくくなり、一方的な行為にならず嫌われなくなります。
もし行為が逸脱しても自らストップをかけられ、自分や周囲の他を認識しやすくなります。
使い方によって良い悪いが極端に分かれるのが気を使う行為ですので、気を使うために気づく前提があると知ることがポイントになります。
※気を使うための気づく詳細は、【決定的に違う】気がつく人と気がつかない人の特徴と能力│認識力が起こすこと をご覧ください。
気を使う時は自分に気を使う
気を使う際、まずは自分に気を使いましょう。
他の状況や状態ではなく、そこに居合わせる自分に見合わせた行為をします。
例えば、大多数の居る環境では気を利かせる行為には限界があり、一人一人違う認識を理解して効果をもたらすなんてことは、スーパーおもてなし浴衣美人でなければ不可能です。
しかし、気を使うことはできます。対集団、ビジネスシーンなどの型や枠組みがある前提では大活躍。
自分らしさが必要な環境か否かを初めに判断し、ビジネスシーンなど必要ない場所であれば、社会性に沿わせて苦痛や恐怖のない利益のための行為だと自覚して気を使います。
友人や家族など身近な存在の環境では、気を使わずに好き勝手やったり、嫌であればその場に見合わせた行為をしたりと調整します。
自分に気を使うとは、気を使うチューニング(調整)です。
チューニングすることで自覚が伴い、自覚して気を使うと誰しもに心地良い行為となります。
自分のために気を使うことで主体性を持つ
気を使うとは自らの行為を認識し、常識に飲まれずにその場その場に見合わせた自分らしさを作ることです。
「気を使うとはどういうことか?」を把握すると、気を使う際の自分を自覚しやすくなり、主体性があると飲み込まれなくなります。
「気を使わなければならない」と思う状態をなくすことが改善に繋がり、「自らが主体的に気を使っているんだ」という意識が物を言います。
自分が辛く苦しければ、気を使うことは何かがおかしくなっている合図ですのでストップしましょう。
「自分に気が使えているかな?」という自覚を意識的にし、他に飲み込まれないことが大切です。
※気が利きすぎる注意点は、【実は同じ】気が利きすぎる人&気が利かない人の原因と改善 をどうぞ。
気を使うと嫌われる改善 まとめ
気が使えることは大きな能力。空気を読めるというのは気づくことであり、認識力の高さを物語ります。
これをするためには学びや育みや経験が必要です。
気づかなければ気を使うことは困難。状況をパターン化して常識やルールを紐づけるように記憶する必要があるので、なんとも大変です。
無理強いは社会に準じたり従う以上に、飲み込まれて自分がなくなる可能性があります。
気づくのか否かは大前提の必須理解ですので、気づかなければ無理にすることではありません。
気づく育みは日々の生活で行えます。如何に自らの五感と感情を認識し、思考を自覚し、心の気持ちを感受するか。
認識は本人にしかできないため、如何に自らが認識できる人になるかは自分をどれほど認めているか次第です。
気づくことで気を使う選択へ向かい、優しさや配慮が出てきた時は気を利かせることもできます。
気を使うことは一歩違えば嫌われ、一歩変えれば気が利いて好かれます。
使い方が重要になる状況把握。使い方を知る肝となるのは自らに気を使うことです。
気の使い方を知る一助となれば幸いです。
ありがとうございました。
『心理とスピリチュアルの学び場』
誰しもに人生を変える機会と選択があると信じています。 著名な心理セラピストとして知られる、西澤裕倖(にしざわひろゆき)先生プロデュース。
著名な心理セラピストとして知られる、西澤裕倖(にしざわひろゆき)先生プロデュース。PR:株式会社Central&Mission
※これは長期的に本気で変わりたい方専用です。