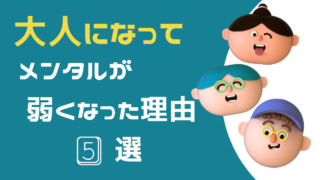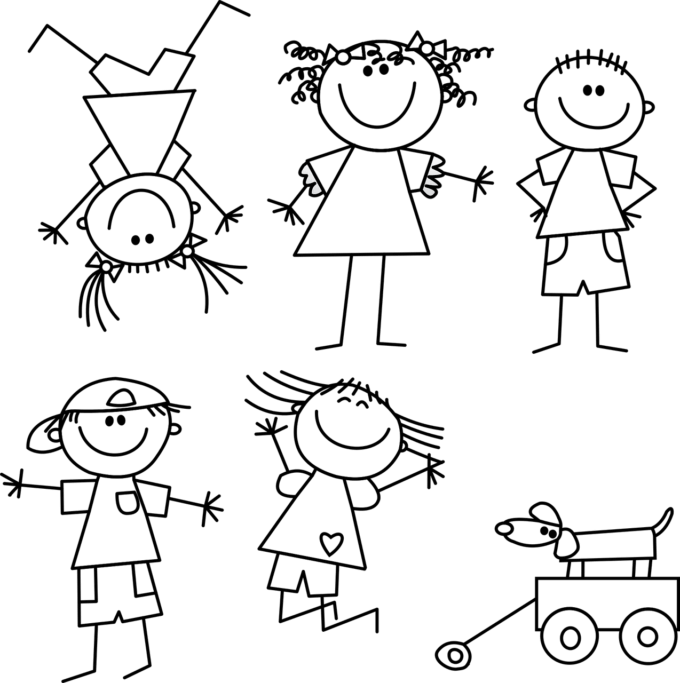『DNAシフトセラピスト養成講座』
・セラピストになりたい方・自己理解を本格的に始めたい方
・専門的に人を癒し、サポートしたい方
 著名な心理セラピストとして知られる、西澤裕倖(にしざわひろゆき)先生プロデュース。
著名な心理セラピストとして知られる、西澤裕倖(にしざわひろゆき)先生プロデュース。PR:株式会社Central&Mission
※本気で人生を変える方専用。
いろいろ音を立てる人は音を楽しんでいる。
そんな平和的な人であれば、「あれ、もしかして日常で音楽を奏でているのかしら?」と。
さぁ、冗談はさておき、生活音がうるさい人は何かと迷惑です。
どうしてそんなに音を立てるのか、目立ちたいのか、驚かせたいのか、迷惑をかけたいのか。
パワー不足。
そんな話がここにあります。
パワーがあり過ぎて制御できていないようにも思えますが、実はパワーダウンが原因だったりします。
私はうるさい人や、音を立てる人を異様に察知してしまいます。私が音を立てないからです。
そんな目線には生活音がうるさい人の心理が写り、対処法が見えています。
音のない人間が音を立てまくる人間を洞察するとわかる、少し奇妙なお話をご覧ください。
Contents
生活音がうるさい人の特徴

生活音がうるさい人とは?
「何者?ふとんをバンバン叩き続けるいつかのおばちゃん?」
生活音がうるさい人とはノイズメーカー。日常にはびこるあらゆる物を使用して音を立てます。
ドアはバンッ!
物を置く時はドンッ!
椅子に座る時はガッシャン!
コンビニのレジにはドッサ!
歩く時はバッチャンバッチャン!
ラーメンはズルズルだけでなくバモバモ!
日常での生活音を強調し、「これだけ音が鳴るんですよ」と行動で教えてくれる人です。
故意に音を立てている自覚がなく、潜在的に無意識に音を作り、音を立てないようにできず、迷惑をかけたい人ではありません。
「みんなが耳栓してくれ」
「気にしないで」
「それぐらい気にすることじゃないでしょ」
と思いたいのが本人の気持ちだったりします。
生活音がうるさい人の特徴12選
1、他への敬いがない
人、物、場所、環境など、自分以外の他への配慮や敬いがない特徴です。
他への認識がなく、物を大事にする、人の気持ちを考える、他者の目線や立場で認識するといった概念が希薄です。
2、おおざっぱでお粗末で無神経
何事にも音を立てるので、動きが大きく二方向、前後、左右、上下です。
荒っぽく、繊細さが動きにありません。
3、ブレーキがない
行ったらドンッ、戻ってドンッ。
「いや、もうこの人何なのー」と、ブレーキの重要性を教える存在です。
4、エネルギー過多で循環がない
エネルギーがありすぎでありながら循環されておらず、強引にエネルギー増し増しにて肩からピュー。あちこち漏れ漏れです。
5、無気力で力がない
エネルギーがあるので燃料満タンかと思いきや、力の入れ具合の調整ができず無気力。
足に力が入らず、床をズリズリ引きずるようにパワーダウンの兆候がでます。
6、承認欲求強め
自己主張として音をあえて作る人もいます。
自己価値や肯定を他から求める在り方があり、「私はここにいるよー」と叫びます。
7、重力に弱い
重力に逆らう力がなく、椅子にドンッ、机にドンッ、ドンドンドンッ。
椅子が壊れるの早めです。
8、体が重い
軽さ、軽やかさ、爽快さ、軽快さ、躍動がなく、重みやダルさが多め。
体重とは別の重さがあり、心から来ていたりします。
9、図々しい
ガツガツ来ます。
目の前の利益がエサのように見えているので、一心不乱に真っ直ぐです。
10、弱肉強食
強い者にはまかれ、弱いものは食う。
もらえる時には全てを手に入れようとします。
11、集団帰属意識が低い
家族や社会という集団への意識が低く、仲間や他との調和に対する認識がなく、他と関わっても調和や共有ではなく、自己利益の追求になりがちです。
12、軸がない
孤独を恐れ、恐怖に弱く、強迫観念を持つ人もいます。
自分の中に軸がなく、ブレやすく、安定がないために情緒不安定になりがちです。
集中力が低く、注意散漫となる基でもあります。
以上が特徴でした。
生活音がうるさい人の特徴 一覧
- 他への敬いがない
- おおざっぱでお粗末で無神経
- ブレーキがない
- エネルギー過多で循環がない
- 無気力で力がない
- 承認欲求強め
- 重力に弱い
- 体が重い
- 図々しい
- 弱肉強食
- 集団帰属意識が低い
- 軸がない
※生活音がうるさい人の詳細がわかるので、【決定的に違う】気がつく人と気がつかない人の特徴と能力│認識力が起こすこと もどうぞ。
生活音がうるさい人の心理
生活音がうるさい人はパワー不足
音を立てるのがノーマルか、音を立てないのがノーマルか。
地球には重力があるため、音を立てるのがノーマルです。
肉体に力が入っていなければ自然と音が作られ、力を入れることで重力に逆らって音を抑制できます。
心身に力があればうるさくない、力がなければうるさくなります。
この力のIN/OUTは、体ではなく“心身”です。
肉体的な物質概念だけでなく、脳の思考や感情、心の気持ちや精神も含めた心技体。
自己コントロール、感情表現の抑制調整、エネルギーの循環度、肉体稼働に関与する筋肉バランスと活力を含めます。
詳しくお伝えすると、血液循環や量や質、リンパ液、エネルギーの浄化滞留など多岐に渡るので割愛しますが、要約すると自己認識による自己の内外理解によって見出される生命基盤です。
生活音がうるさい人は自分に対する理解が希薄、活力や動力となるパワーが見出せない(エネルギーが心身循環していない)。
うるさくなるキーワードは、「パワーに対する調整と抑制」「エネルギー循環」です。
生活音がうるさい人はエネルギーが循環されていない
重力に逆らわないと、手や足など肉体の自重にて加速するように音を作ります。
しかし、それだけでは生活音がうるさくはなりません。
上下の重力関係だけでなく、ドアの開け閉めや、食事の咀嚼音、テレビの音量を上げるなどの生活音もうるさい、あと布団が泣くほど叩くよ、と。
これらの力の調整がなくなる様にも、パワー不足が起因します。
自己抑制のなさ、調整不可、エネルギー循環のなさにてパワー不足となり、音の強弱に歯止めがつかなくなります。
パワー不足は基盤崩れから起きるエネルギー循環のなさ
パワーをうまく出せないと無気力になり、周囲を考慮する余裕がなくなります。
自分のことしか見えない状態ですが、自分も見えていないために他への敬いのなさや、無神経な様となります。
生活音がうるさい人の心理に、自分の基盤構築の欠如があります。
この世に存在する自分としての基盤が崩れると、安定や安心がなくなります。心身のエネルギー循環の最も大切な初めがないと、エネルギーがあっても使い方がわからなくなります。
エネルギー循環がなくなり、地に足が付いていない状態になります。
足にエネルギーがないので足はだるく、体が重くなります。自律神経も乱れ、情緒も安定しなくなります。
自己理解の希薄さが関わり、食生活、多忙による疲労、ストレス過多などがあります。
生活音がうるさくなる原因
「周囲を考慮する余裕がない」
「自分のことしか考えていないようで自分のことが見えていない」
これら二つの様は、他の目線で物事を認識しないことを意味します。
他者にどう思われているか考えない、思わない、知らない、わからない、わかろうとしない、わかろうとできない。
わかろうとしたくてもわからない人もいますし、わかろうとしたくてもできない人もおり、わかる気がない人もいます。
人それぞれの様がありますが、共通している心理は自己理解の希薄です。
自己理解がなければ他者を理解することは困難です。
生活音がうるさくなる原因一覧
自己理解が希薄な心理の原因がいくつかあります。
- 自己責任を持つ経験がない(周囲がなんでもしてくれたなど)
- 幼少期に躾されていない
- 過去に甘やかされた、または仮面一家にて家族と絆がない
- 集団帰属意識の欠如
- 集団の中での自立がない
- 情緒的な安心感のなさ
- 絶対的に頼れる人を求めて止まない欲求(自立意識がない)
- 弱肉強食意識があり、自己優先が強い癖(または他を敵にする)
- 実質的で実利主義、目の前の確実な利益を欲する余裕のなさ
- エネルギー循環がなく、無気力
- 恐れや強迫観念があり、否定されることを恐れる(または否定されると相手を完全なる敵とみなす自己防衛の過剰)
基盤が崩れると生活音がうるさくなってしまう
幼少期の環境や躾、自己理解のなさ、自責・自立意識の欠如、安定と安心感のない内情での焦りなどによって、自分という存在の足場がもろくなります。
基盤が崩れると物事の認識や理解の余裕がなくなり、自己理解する意識に向かうことが困難です。
承認欲求を強めて自分の存在認知を自らではなく他によって高めようとしたり、自己主張して存在を周囲に知らしめるために、あえて音を作る人もいます。
その様が当たり前になることで自覚しなくなり、幼少期から癖のように音を立てる在り方が定着する人もいます。
自分の基盤が崩れることで生活音はうるさくなり、心の安心や安定のなさを表現する心理となります。
生活音がうるさい人の対処法
対処ポイント
エネルギー循環させてパワーを心身で体感させることが対処ポイントです。
活力や動力を感じるようにし、血流を促すように滞りを流してあげます。
安心させましょう。
「ちょっとあんたドタバタと階段登んじゃないよ」ときつく言っちゃうと、一発K.O寸前までいきます。
崖っぷしに追いやるようなものですので、安心感とは真逆になり、うるさい人は傷つくか逆上するかの両端になりがちです。
エネルギー不足の人は傷つき、過多の人は逆上です。
安心によってうるさい本人に余裕を持ってもらうことが対処です。
※ご参考にうるさくなくなる方法、気配を消す方法は熊が教えてくれた│忍法【自分を感じず他者を見る】をご覧ください。
生活音がうるさい人の対処法①:生活に心の余裕を与える
身近にいる人に対する対処法。ストレスや多忙、自律神経の乱れや食事に対しての緩和が大切です。
刺激ではなく癒し、心身に休息や余裕を与えられるように関わることで、生活音は少しずつ治まっていきます。
関わり方、接し方、話し方が重要になり、否定や非難などの恐怖や孤独を感じさせるのはNG。
安心や安全を与える関わり方にします。
食事の見直しは有効的
心の余裕を肉体から与えることも大切です。
私が実際に対処してきた経験では、食事の見直しはかなり有効的です。
刺激物を抑え、自然物を増やします。
「オーガニックとか無添加ものだけ」という極端さは必要ありません。少し野菜や穀物や果物を増やし、少しお菓子や化学物質を減らすという感じで、適応できる範囲でいきましょう。
生活音がうるさい人の対処法②:集団帰属意識を増やす関わり方をする
関わる際に調和を与える対処です。
生活音がうるさい人は家族や社会など集団帰属への意識が低く、その中での自立がありません。
個を主張するのですが自立ではないので図々しくなったり、自己優先して他を敵にしますので、敵ではないことを表します。
まずは両手をあげて近づき、武器を目の前で見えるように床に置きます。
イメージとしてはこうですが、敵ではない様を表し、同じ社会(または家族)の仲間だと表して関わります。
絆に対して強い想いが心の中にあり、仲間や信頼できる関係が深くなればなるほどに音を立てることがなくなり、他を考慮する余裕を持ってもらえます。
生活音がうるさい人の対処法③:安全を認識させる
うるさい人は余裕がもたらされる環境に身を置くと、別人のように静まります。
極端な例では、仕事も家庭もお金もストレスも何も考える必要のない安泰の中点。別荘で朝から湖畔に釣りに行けば、ボーッとコーヒー。
「あら、どなた?」と思うほど静寂を作ります。
緊張させるのは厳禁、うるさくなります。
恐怖となる否定や非難をせず、あしらいや蔑み、評価の低い価値のない人のように接すると、うるささを抑制する理由を本人から見出せなくなり、うるさくするのが当たり前だと思い込み、自己認識をめんどくさがり、対処がいばらの道に。
自己防衛で自らを殻に入れ込むのをなくさせるのが対処法となり、安全な場所にいると認識させることが大切です。
生活音がうるさい人は自ら改善できないことを理解してあげる
潜在的な認識であり、認めたくない心理や原因であるため、自覚なく生活音がうるさくなります。
自ら変えたくても変えるのが非常に困難な実情があります。
うるさくしたくてしている訳ではないため、周囲から本人の改善を促すための関わり方をしてあげるとお互いのためになります。
アプローチの着目は“本人に余裕を持ってもらう”ことでして、安心と安全認識をこちらから与えることが対処です。
エネルギーが循環されればありのままの姿として、素直で純粋で素敵な人間性が露になります。
絆や仲間意識を持つことができれば心から喜び、関わる人を大事にするのが、生活音がうるさい人です。
情緒的な安心感を持ち、他者とは比べられないほど仲間意識を強めてお互いのためになる時間が始まります。
お互いの育みを考えながら対処するのが生活音がうるさい人との関わりです。
※感情的でうるさい人への対策は、【すぐ感情的になる人に疲れる方へ】苦手意識があるからこその策略 をご覧ください。
生活音がうるさい人 まとめ
生活音が多い、騒がしい、うるさい人。
公共の場で関わりのない人であれば、対処はスルーで終わりですが、関わりのある人であれば対処は自らを変えることを意味します。
他者を変えるためにはまずは自分からです。
本人が騒音の基であると気づいていない場合もあり、気づいていても気づかないように潜在的に恒常化している場合もあり、あえて自己の存在認知と承認を得るために、うるさくしても迷惑だとは一切思っていない場合もあります。
人それぞれにうるさくする理由と原因と心理があります。
物事をシンプルにするためには相手を知ることが最も効果的です。
私は生活音を一切立てないように生きていた時間が長いので、まるで忍者のように気配も音も消すことができます。
かくれんぼ最強パターンと、そんなことはどうでもいいのですが、この状態にも同様にエネルギー循環のなさ(エネルギーを消してしまう自滅行為)があり、なさすぎることは我慢や抑制し過ぎで良いこととは全く別概念です。
音がないのもあるのも、どちらも本人にとっては何の問題もありませんが、周囲は気になるものです。
生活音がうるさい人の理解や認知を深めると、動きや音の予測、音響の広がりと、うるささの影響範囲の把握など、対処の道が物理的にも見えてきます。
人の在り方、基盤の大切さを知っていただき、より相手を理解した上での対処がお役立ちできれば幸いです。
安心と安定のない心理から、うるさい人自身の道を開きつつ、人間理解にて他者認識力を高める機会にされてください。
それでは、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
『心理とスピリチュアルの学び場』
誰しもに人生を変える機会と選択があると信じています。 著名な心理セラピストとして知られる、西澤裕倖(にしざわひろゆき)先生プロデュース。
著名な心理セラピストとして知られる、西澤裕倖(にしざわひろゆき)先生プロデュース。PR:株式会社Central&Mission
※これは長期的に本気で変わりたい方専用です。