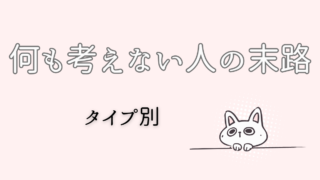【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ぜひおすすめしたい」と感じたのでご紹介です。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作ってもらえます
「なんでこんなにわかるの?」と思えるほど的確で、わかりやすく言語化してくださり、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください
何を言っても変わらない、わからない、無駄。
「言う意味なんてない」とすら思ってしまう。
そんな言っても無駄な人や状況や状態がある一方、反対側があります。
言われる側。
言われても変わらない、わからない、無駄。
「聞く意味なんてない」とすら思ってしまう。
そんな言われても無駄なことや状況や状態があります。
言っても無駄な人、言われても無駄なこと、人間関係の合致は難しいものです。
ここでは、言っても無駄、言われても無駄という状態にある心理をお伝えします。
私自身、今は言う側ですが、子供の時は言われる側。何を言われても聞かないひねくれ者でした。
聞かないことにはちゃんと理由があり、言う側と言われる側の反発には明確な心理が潜みます。
心理の理解により、お互いのためになる素敵な道が見られます。
「言っても無駄」に潜む感情や思考、気持ちや行為の理解が、人と人の営みの向上となることを願い、心理の哲学による紐解きと対処法をお楽しみください。
Contents
言っても無駄だと思う心理

言っても無駄な人とは
何かを伝え、教え、助言し、助け、変化を促し。さまざまな目的を持って何かを他者に対して言う。
- よかれと思って
- 相手のためになると思って
- この人を助けたいから
- これをすれば絶対良くなる
- 変わって欲しい
- このままでは私が我慢できない
- 変わってもらわないと嫌だから
- ‥‥
親、パートナー、子供、恋人、友人、知人、同僚など、何かを言いたくなる状況や状態があります。
仕事など周りが迷惑する状況があればしっかり教えたい。
親であれば言いたい気持ちを分かって欲しい。
夫婦だからお互いのためにも変わって欲しい。
子供には成長して物事を理解して欲しい。
だけど変わらない、わからない、なんでやねんと。
言っても無駄な人は、言う側の目線から見るとこう↓写っているかもしれません。
理解力がない、頑固者、こっちの気持ちを知ろうとしてくれない、変化する気がない、成長意志がない、聞く気がない、自分に興味がない、他者への敬いがない。
言っても無駄な人とは、自分の力が作用しない人。
言っても無駄な人のタイプ
言っても無駄な人とは、他からの影響を受けない人とも言え、タイプが三つ見られます。
- 自己認知の高さによる自律、自立、自責がある
- 自律、自責への意識があり過ぎて他が見えない
- 不安や恐怖に駆られて他を受け入れられない
言っても無駄だと思う側の心理
力が作用しない言う側は、影響力が及ばないことに対して憤りや心地悪さを感じます。
自分の行為に意味がない状態を見たくない、認めたくありません。
誰しも嫌だと思います。良かれと思って、会社のためになると思って、目の前の人のためになると思って言い、理解してもらおうと頑張っているのに、行為に意味が見出せません。
しかし、言うことで相手が影響すればどうなるでしょうか?
理解しようと頑張ってくれる、勉強している、メモして毎日確認している、成長しようとしている、努力して変わろうとしている。
レスポンスがあり、影響力の認知ができ、言ったことに対する意味が掘り起こされるようで嬉しいと思います。
相手の行動や変化への気持ちを知れば、「言っても無駄」とは思いません。
言っても無駄だと思う心理には、自分の内側で渦巻くものがあり、自分の行為に対する意味を他から求めているかもしれません。他責とも言います。
他責とは、自分の行動の結果を他に任せる(または求める)こと。
言っても無駄な心理は、他責により自らの行為を自ら認めないことでの己の葛藤。
そんな考えが一つ。
言う目的の焦点にある心理
「お金くれればエクストラサービス、先輩が教えない仕事のスゴ技教えてあげる」となれば、自らの利益のためなので状況も心理も一変します。
仕事で教えなければならない、家族として躾したい、などと自らの利益追求が先行し、その後に他者のためと付随する場合、「言っても無駄」と思うのは、「言っても自分の利益にならない」という意味になりかねません。
「相手のため」が二の次なので、言ったところで聞かれないのは当然かと思います。
私のようなひねくれものであれば、おそらく何があっても聞かないです。なぜならば、見方を変えると利用されているからです。
言うのは「自分のためor相手のため?」
相手のために時間も労力も思考も使って言い、教え、変化を促す。それで影響が見出せなければ、「言っても無駄だ」と思うのは当然です。
「あんたのために自分を労費させてんだから、言って変わらないならもう言うことないよ、継続したいなら金でも払いな」という感じですね。
この場合、「言ってもわからない、だから?」と気にする理由がありません。
気楽にさようならで終わり、二度と言うことはありません。
自分のために言うのか、他者のために言うのか。目的の焦点が己か他か、両方か、どちらに配分が多いかにて心理が表れます。
- 他のために言う場合、他が変わらない時は言うのは終わり、または自らの在り方や関わり方を変えて継続(自責)
- 自分のために言う場合、他が変わらないと憤りやストレスを作り頭をかきむしる(他責)
言っても無駄だと思うのは自分のために相手を変えたい
まるで不良を相手にする教師のようなイメージかと思います。
あれはテレビの中の話、「教師って大変ね」と思いきや、実は日常的に起きていたりします。
何を言っても聞かない時、他を変えようとするか、己を変えて関わり方を変えながら言い続けるか。
この違いには自責か他責があり、自らを変えて他者に影響を与えられるか、他を変えようとする一辺倒で自らに着眼が向かないかの違いがあります。
言っても無駄だと諦める場合、相手を変えることにフォーカスして、自分が変わるつもりがない可能性があります。
相手を変えるためには必ず自分が変わるのは必須です。この理解がないと、押し付けや干渉や他者認識の欠如に繋がります。
言われても無駄だと思う心理
言われても無駄だと思う側の心理
次は言われる側の心理です。
言ってくれる人の影響をどれほど受けるかによって、変化や向上、退化や低下が起きます。
人が人に何かを教えるのは難しいことだと思います。本人に必要で大切で重要なものかは本人にしかわからないからです。
常識や規律を正として教育・躾する場合、人が人に何かを教える意味が希薄になります。
人間味がないので誰が教えても同じ状態、ロボットが教えた方が干渉や押し付けや支配の可能性がなくなっていいかもしれません。
人が人に影響を与える場合には、どれほど他者の立場や視線に立つ他者認識と人間味があるかが重要ポイントです。
これらが欠如していると、「言われても無駄」と言われる側は思います。
「それでは、言う側に全ての責任があるのか?」と思えそうですが、全くそんなことはありません。
言う側が主導権を握るため、不安を感じやすい
全ての主導権は言う側が握っています。いつでもどこでも、好き勝手に切り上げ、やめて、二度と言わないことだってできるのが言う側です。
このことを大なり小なり言われる側は認識しているため、不安や恐怖を抱きます。
主導権を握られている状態に私達人間は不安や危険を感じ、防衛意識が自然と働きます。
身構えやすい立場であるため、言われる状態に抵抗や嫌悪を感じ、防衛意識が強ければ強いほどに受け入れが困難になり、言われても無駄だと思いやすくなります。
言われても無駄だと思う心理一覧
- 人間味がないと聞く耳を持たない
- 利用されることへの嫌悪に反発する
- 自分の立場や目線で言われないと、全くの他人事に聞こえて内容が入って来ない
- 主導権を握られる、不安と恐怖心で抵抗がある
- 防衛意識が強く、受け入れられない
- 防衛意識にて支配や攻撃性に拒否がある
全てに共通するのは、言ってくる人を受け入れられない抵抗です。
拒否しているわけではなく、不安や恐怖を増長し、マウントをとられて支配されるような、コントロールされて利用されるような様子が少しでもあると身構えます。
すると硬直(緊張)します。
わからないから、理解がないから、変化がないから、成長がないから周囲の人々が教えてきます。
しかし、硬直していれば心地悪さもあり、相手が自分のために利用してくる場合には、一切受け入れたくない拒否も起きます。
言っても無駄だと思われると同時に、言われても無駄だと思っています。
両者の矛先の完全なる不合致があり、「お互いにどこ見てんの?」となっています。
言われても無駄だと思ってしまう理由
言われても無駄だと思ってしまう理由には、言ってくる人を受け入れられない抵抗があり、相手に主導権を握られる状況に対しての不安と恐怖が潜みます。
極端な例としては、私物化してマウントをとり、支配してコントロールして相手を変えさせようとする場合。
親と子、生徒と教師、部下と上司間で起こるシチュエーションです。
ここで不安と恐怖に対処する方法は人それぞれです。
- 自らを隠して見栄を強めて偽ります
- 怒りによって自己防衛し、本心を守ります
- 無視して、知りたくない事実を抑制して自らの内側を鎮めます
- 蔑みや文句を言い、自らの弱味や恐れを誤魔化します
- ‥‥
対処して言ってくる人に主導権を取らせないようにするのが自己防衛であり、自らを苦しめずに守る在り方です。
頑固になり、聞く耳を持たず、「言ってくれる」ではなく「言ってきやがる」的なことにもなりかねません。
他者認識力の乏しさ、言ってくれる人の立場や目線で物事を認識することができず、見ている焦点は自分の保身や安泰になります。
不安や恐怖への対処法が、立ち向かったり受け入れたり、恐怖を理解したり自らを高めたりではなくなり、受け入れない、見ない、逃げる、誤魔化すになります。
「言っても無駄」と諦められ、それを受け入れないためにも、「言われても無駄」と自ら跳ねのけたように思おうとすることも起きます。
言っても無駄な時の対処法
言っても無駄な人の体験話
私は言っても無駄な人でしたので、この後の対処法がわかりやすくなればと思うので小話をご覧ください。
私が中学生の時、先生がどれだけ時間をかけて、特別にマンツーマンで教えても、数学ができない男の子が同じクラスにいました。
その子はとんでもなく頭の悪い子で、特に数学はお手上げ状態。
私は勉強ができない子で、国語の教科書なんて開いた記憶もありませんが、数学は好きで一人で教科書を勝手に進めて、授業はそっちのけで自分で授業をしていました。
先生に何を言われても無駄な子でした。
二人の言っても無駄な子は、先生の指示によって窓側端っこに移動させられ、数学の時間は常に私達二人は隣合わせで放っておかれました。
私は暇なのでその子に教えようと思ったのですが、とんでもなく馬鹿な子で、笑いがおさまらないほど笑いました。
メチャクチャキレてましたが、私達は仲良くなり、数学の授業だけ私が教師になって教える日々に。
発想や着眼が私にはない間違え方だらけなので面白くてしょうがなく、その子は怒っていましたが、なんだかんだみるみる理解していきました。
最終的にはみんなと同じように理解するようになり、成績は1から3へ。その段階で私達は席を元に戻されて終了。
先生良い所取りー、って話です。
言っても無駄、言われても無駄の対処キーワード
「言っても無駄」だと思う場合、「言われても無駄」だと思われているかもしれません。
「自分のために言う」と、「自分のために受け入れない」の関係性で反発し合います。
「無駄だ」と思う諦めや落胆、意味がないと判断された状態には、言った影響力のなさがあり、受け入れられていない様があります。
言う側と言われる側は相互に向き合っていれば最高ですが、どちらか一方が相手を見ていれば、無駄ということはなくなります。
対処するためのキーワードは、「影響」と「受け入れ」です。
言う側は影響。
言われる側は受け入れ。
言っても無駄な時の対処法
対処法は、「自分を明確にする」「相手を尊重する」です。
言う側は自分という存在をはっきり把握すると、より自己認識力を高めて自分を知ることができます。
人間味が増し、主導権を握ろうとしたり、干渉や押し付けなど、相手の不安や恐怖が刺激されることがなくなり、受け入れてもらいやすくなります。
親や教師や上司など、社会的な武装やアドバンテージを貰っている場合、無自覚に主導権を握ろうとしている可能性があります。
「教えてあげてる」
「変わって欲しい」
「成長して欲しい」
これらの認識は相手を自分のテリトリーに入れ込もうとし、他者を把握しないことが起きます。
目の前の人の人格や性格、価値観や信念や観念を把握せずに影響を与えることは困難です。
自分がある人ほど相手を把握しようとします。受け入れない選択が容易になってしまうので、如何に相手を見て・感じて・考えて・想って伝えるかが重要になります。
対処法は如何に相手に合わせて自分を変えられるか。
言っても無駄な時の対処法は、自分を変えることです。
人を変えるとは自分を変えること
私達は他者を変えることができません。変わっても変わったと認識できません。
他から影響をもらって変わったように思えても、実際には影響を自らが自らのために使用して自らが変えています。
「他者を変える、変わって欲しいなど」と思う場合、影響させるのではなく、影響の材料をあげることを意味します。
「変える」ではなく、「変わってもらう」
相手を変えるのではなく自分の意識を変えることが、人を変える意味です。
人を変えることは尊重。
相手への敬いです。
言う対象を敬うことができれば、そのままを尊重して受け入れられます。
干渉や押し付けは起きず、自らを変えて相手との関わりを見出し、影響の材料を与えて変わってもらう意識が起きます。
一つの方法では理解されなくとも、別の見方や方法などを見出し、影響を与えるために継続して言うことができます。
諦めないや頑張るではなく、自己成長であり他者認識力を高める機会であり、意識だけでなく自分の認識幅や能力や才能も変化していく状態です。
※人が変わる、変わらない詳細は、人は変わらないことに意味がある│変わる人と変わらない人の明確な違い をご覧ください。
https://nandemoii.com/people-are-constant-or-not/
言っても無駄の心理 まとめ
言っても無駄な心理には人と人の関係性にある哲学が潜みます。
人間関係の相互理解、言う時の内側の無自覚な意識、教える際のアドバンテージ認識、教えることの意味に着眼に目的。
他者を変えるのは自分を変える人間の在り方です。
人間同士が関わる際にはお互いに良いも悪いも含めて影響し合います。
常に拒否と受け入れと無関心のフラットがあり、相互の反発や受け入れが起きたり起きなかったり。
言う内容、思考、知識としての影響もありますが、感情、気持ち、意識としての影響が大きくあり、言われる側は相手の口から発された音や情報を受け取るだけではなく、気持ちなどの中身を受け入れます。
「言っても無駄」と諦めるのはもったいないかもしれません。
言うからには自らを明確にして自らの在り方を自覚します。その様が責任を持つというものです。
責任を持つと、相手は言われるという不安や恐怖が先行しやすい状態を対処しようとしてくれます。これも責任を持つ様です。
自らの力で干渉するのではなく、影響によって相手自身に変わってもらう協力やサポートをし、言うことの意味が見出されます。
その際にはお互いに自責を持った関わりにて、良き影響を与え合い、自らが変わることで相手も変わり、それは相手も同じように認識します。
言っても無駄だと思う際にはご自身を見つめ、相手を捉え、相互の関わりを主体にフォーカスされてみてください。
対処として、役立つ人間理解があれば幸いです。
それでは、言っても無駄な心理のお話を終了します。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ピン!」と来た方はぜひお試しください。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作成してもらえます
的確にわかりやすく言語化してくださるため、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください