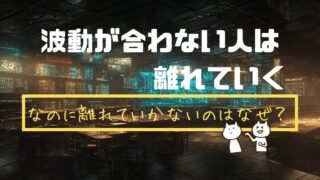【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ぜひおすすめしたい」と感じたのでご紹介です。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作ってもらえます
「なんでこんなにわかるの?」と思えるほど的確で、わかりやすく言語化してくださり、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください
笑いのツボ、一度入ると出て来るのが難しい人もいれば、ササッと出て来る人もいます。
ツボの浅い深いの違いとはなんなのか。
ツボに入る笑いには、根源的な笑いのメカニズムがあります。
ここでは、笑いのツボが浅い人と深い人の心理から、メカニズムの考察を見ていかれてください。
- なぜ笑いのツボが浅いのか、深いのか知りたい
- ツボを浅くする方法を知りたい
笑う仕組みは未だ解明されていない不思議な謎解き。
一つの考え方としてお楽しみいただければ幸いです。
Contents
笑いのツボが浅い人の特徴と心理

笑いのツボが浅い人の特徴
目立つ特徴をご覧ください。
- 明るい性格
- 自由を好む
(実際には調和を好む) - 女性性が高い
- 話すより聞くのが好き
- 縛りや抑圧されるのが嫌い
- 周囲に同調しやすい、共感性がある
- 自己愛が強く、自分を大切な存在だと思う
- 人を無意識に評価・判断する(人の目を気にする)
- 自らを客観的に捉え、物事を受け入れる
- 認識力が高い(よく気がつく)
- 頭の回転が早い
明るさや心を主体にして、周囲を捉えて自らの在り方を定めるスタンス。
心の余裕が伺える特徴であり、太陽のような人です。
「自由が好き」ですが、実際には他との調和を好む傾向があり、協調性がありながら縛られるのが好きではない特徴が目立ちます。
主張や押し付け以上に、傾聴や受け入れスタンスがあり、女性性(凹)が高い人ほど笑いのツボが浅くなると考えられます。
笑いのツボが浅い人の心理
ツボが浅い人とは些細なことでもすぐ笑う人です。
ツボの口が広い。
笑う意志があり、面白おかしさを見つけて笑う才能が伺えます。
笑う気がある人はツボが浅い
笑う意志があると、笑いたいと願い、笑わせてと欲し、笑える点を見つけ、笑える要因を探ります。
自分を喜ばせる意欲に基づき、出来事を基に笑いを得ようとします。
笑うことでの効果や恩恵を求め、喜び楽しい感覚になることを欲する結果、笑うための活動が盛んになります。
笑う動機は楽しみたい欲求であり、自分を大切にする自己愛に基づき、ツボに入ろうとする気がある人ほど笑いやすくなります。
自己愛によってツボに入る気がある=笑う意志がある=ツボが浅い
※ツボが浅い人の育ちは、【“ある力”を生む環境】よく笑う人の育ち方7選 をどうぞ。
笑いを見つける能力が高い
ツボに入る気があっても、「何が面白いの?」を理解できなければなかなか笑えません。
ツボが浅い人は認識力があり、物事によく気がつき、周囲をよく把握します。
頭の回転が早く、頭がいい人であるからこそ面白さを知り、おかしさを理解しやすく、笑う頻度が高まります。
ぼーっとして何も考えていなそうでも、認識力がある人は核心を突く発言をしたり、物事の本質を見る力があります。
受け入れるスタンスがあり、新しいものを取り入れる柔軟性と縛りのなさによって、笑いやすくなります。
純粋に現実そのままを捉え、既存の自己ルールと照合することでギャップが作られ、そのギャップに気がつき、笑う気があることで、笑う材料になります。
認識力が高ければ高いほど笑いを探って見出せるため、ツボに入りやすく、浅くなります。
ツボの口の広さ(大きさ)=認識力の高さ(よく気が付く)=ツボが浅い
※心理詳細は、【よく笑う人は頭がいい苦労人】特徴と心理に笑いを作る人間味 をご覧ください。
笑いのツボが深い人の特徴と心理

笑いのツボが深い人の特徴
反対に、ツボが深い人の特徴はこのようになります。
- 自己抑圧が強い
- 我慢や誤魔化しが癖になっている
- 笑うための活動が衰退(笑わせてもらうスタンス)
- 個人主義にて他に同調しない
- 認識が自分の捉えたいものに偏る
- 周囲に気がつかない
- 傾聴がなく主張が強い
- 意識的に人を評価・判断している
- 自己愛による抑圧の解放意欲が弱い
- 心を開かず、脳が主体
- 自らを客観視できていない
笑いのツボが深い人の心理
あまり笑わない人をツボが深いと言います。
ツボの高さ(深さ)が大きなポイントとなり、あまり笑わないのですが、笑いのメカニズムを教えてくれる存在です。
金魚鉢で言うと、金魚が沈静している状態。
ツボが深い人を一言で表すと、笑う才能をあまり使わない人と言えるかもしれません。
笑うための活動がなく、笑う要因を探る動機や意志がないと活発度が沈静化して、ツボに入るのが難しくなります。
笑う才能が低いのではなく、自己愛によって自らを笑わす動機や意志の少なさ、または心を開きたくない心理が関係していると考えられます。
ツボが深い人は笑う才能と自己愛を活用しなくなっており、笑うための活動が衰退している状態。
この原因となるのが、抑圧です。
※ツボが深い人の生育環境は、【笑わない人の過去と家庭】みんなが笑っているのに笑えない理由がある をご覧ください。
ツボの深さは抑圧度の高さ
笑いのツボが深い人は、自己内部にあるツボそのものの高さが深い人です。
深さには大きな意味があります。
ツボの高さ(深さ)=抑圧度の高さ
※ツボのサイズが抑圧バロメーター
抑圧とは自らを抑え付けることであり、解放しないさま。
抑圧バロメーターを高めるのは、抑圧が全くないか、抑圧されていると自覚しながら我慢や誤魔化しをする心理です。
抑圧が一切ない場合は、お坊さんのように大笑いしなくなり、絶対的な心の余裕からニコニコ。
抑圧が強い場合は、ツボに入る意志(笑うための活動)がなくなり、笑う才能を使わなくなります。
抑圧は思い込みや固定観念などを増やし、物事を捉える際にしっかり細部まで見たり、感じたり、考えることがなくなり、意識的に捉えたい一点を認識するので認識力を下げる最たる理由となります。
認識力が低くなるためにツボの口が狭くなり、笑うための活動は沈静化します。
ツボに入る意志がなくなり、口がキュンと閉じることで、何が面白いのかわからなくなるツボの見失いが起きます。
例外:ツボが深い人は個性的なツボを持つ
抑圧によってツボが深くても、認識力が高い人は口が広いのでツボに入れます。
自意識を強く持って個を主張か尊重する人の在り方でして、自己世界をどこまでも尊重しているので、他者に笑わせてもらうのではなく自ら笑いを作るスタンスがあり、個性的なツボを持ちます。
笑う頻度は少なくなりますが、想像を広げて、過去の記憶と照合したり、ツッコんだりして笑います。
自分の中で抑圧がありながらも、認識力を駆使する人は、あらゆる出来事に個人の面白みを見出します。
例えば、木の葉っぱを見ている時、葉っぱの並びや模様から、実体像を具現化して巨人に見えたり、鼻をほじっている顔のでかい鹿に見えたり、見方を変えてあらゆる物を認識します。
ここに想像性も含めてストーリーを作ることもでき、ふんどしを巻いた天使と、タバコを咥えたようにかっぱ巻きを食べる赤ちゃんが相撲をとっている、なんてことが起きています。
抑圧があるからこそ笑える仕組みが潜み、ツボが深い人は一度笑うとなかなか笑いを止められなくなります。
※愛想笑いができない件は、愛想笑いができないことに意味がある│人間性が恩恵になる笑いの使い方 をどうぞ。
ツボの浅深にある最も大きな違い
ツボが浅い人と深い人の決定的な違いは、抑圧有無(または抑圧の解放意欲有無)だと考えます。
- ツボが浅い人は抑圧が弱く、解放意欲が強い
- ツボが深い人は抑圧が強く、解放意欲が弱い
浅いも深いもどちらも大切になり、笑いやすいのはツボが浅い人ですが、価値ある笑いを実際に作れるのはツボが深い人だと考えられます。
一番楽しいのはツボ口が広くて、ツボの高さが深い状態。
抑圧が強くて解放意欲も強いと、よく笑いよく泣く人です。
ストレス影響:急にツボが浅くなる
「なんだか最近すぐ笑うようになったな」という人がいます。
抑圧の限界による心理的変動が考えられます。
疲れやストレスが蓄積し、これ以上の抑圧は精神に影響をきたすとみなされた時、抑圧解放運動が自己内部で起きます。
ストライキです。
抑圧の過激化は自分の見失いに繋がり、喜びや楽しみや癒しなど自己愛に基づく欲求従順や意欲がなくなると、精神の治癒がなくなるために闇の世界へ入る可能性もあります。
自己愛は防衛本能と結託し、自らを護って大切にするためにも、抑圧を解放しようとする意志を導き、ストライキを自分のために発動します。
結果、抑圧の解放を目指す活動が起き、笑いやすくなります。
心理的に捉えると、人にとって笑うことの大切さがわかります。
精神にも影響している欠かせない活動が笑いです。
※作り笑いの詳細は、いつも笑っている人の過去に笑顔を作る心理|人間には正当な企みがある をご覧ください。
【笑いのメカニズム】ツボを浅くする方法

笑いのツボとは「活動ゾーン」
中に入ると笑ってしまうツボ、300ルピー。
これまでの内容をおさらいしながら、ツボの詳細をご覧ください。
- ツボに入る意志
=笑いを作る気(金魚の活発度) - ツボ口広さ
=認識力(笑うための活動基盤) - ツボ高さ
=抑圧度バロメーター
笑いのツボに入るための意志(自らを喜ばせたい気持ち、自己愛)、入りやすくする認識力、そして抑圧をなくすことでよく笑うようになります。
一言で表すとこうなります。
笑いのツボとは、抑圧の解放による痛快面白ゾーン。
抑圧を解放するゾーンに笑うチャンスがあり、後は自分次第で笑うかどうかが決まります。
イメージは、ステージからお菓子を客席にばら撒くお祭り、たくさんお菓子を得るために走り回り、それを楽しむ人はツボが浅い。
特大のお菓子だけを狙っている人は、あまり笑わないけれども一度ツボに入ると大笑い。
お菓子になんか興味がない人はジーっと座る、ツボが深い人です。
※笑いの使い方については、【笑いを使用中】面白くないのに笑う人の心理に自己愛と自己防衛 をご覧ください。
ツボを浅くするポイント①:抑圧の自覚
抑圧の解放がキーワードとなる、笑いのツボ入り、浅入り。
どれだけ抑圧しているかは、どれだけ苦労しているかと言い換えられるかもしれません。
我慢や辛抱があり、強制や強要による縛り、憤りやストレスを発散できない苦しみがあります。
これらが蓄積すればするほど、ツボはボボンとでかくなっていきます。
抑圧を解放するためには抑圧そのものを自覚するのがファーストステップとなります。
自覚すればあとは解放、「この抑圧してきたものを、もう思いっ切り吹き出してやる、ううう!」
この原理を使用すると、「笑っちゃダメだよ」などの抑圧をあえて作る、または笑ってはいけないシチュエーションにするなどが、ツボに入る気を強める方法にもなります。
抑圧は笑わないためのストップになりながら、笑うためのポイントにもなります。
ツボを浅くするポイント②:心を開く
抑圧の解放は、言葉を変えるとこのようにもなります。
建前による偽りやルール従順は自らを抑え、本音が解放となる。
建前と本音、偽りと事実のギャップ。
下ネタやブラックジョークがわかりやすい例です。
建前による縛りや制約があることで、下ネタはいい具合に抑圧され、本音や事実を吐露した時に解放によってツボに入ります。
例えば、私が中学生の頃に観た、芸人よゐこの濱口さんが無人島生活をしていたテレビ番組。
捕まえた大きな魚の調理。油で満たされた熱い鍋にピョーンとぶん投げた瞬間、
「人間とはこうあるべきだ」などの解放意欲がありながらそれができないことでより抑圧を作っていた私は、濵口さんがドーンと入れて、ボーっと火が燃え上がるシーンによって、全てが解放された感覚で大笑いしました。
抑圧の解放は心を開く瞬間となり、ツボを浅くするためには心を開くことがポイントになります。
ツボを浅くする方法:心とエゴの理解
面白おかしくて笑う場合には、明確な縮図があります。
心がエゴを笑う縮図です。
心とは愛であり、意志を見出す原料。
エゴとはお伝えしている抑圧。
※他によって自らを見出す意識。比較や上下区分けにて優劣を見出して、自分を認めるなどがエゴ
自ら笑える要因を探し、笑いを見出すさまは、はっきりと自分が自分の中の記憶や認識を基に笑っている在り方です。
ツボに入る笑いは自らが自ら(記憶や認識)を笑っており、心がエゴを笑います。
- ツボが浅い人は、心を開いて自分の中にあるエゴをよく見て笑う
- ツボが深い人は、心を開かず自分の中にあるエゴを見たくないので笑わない
このことから、ツボを浅くするためには自らが自らを客観的に理解し、笑いたい自分と、抑圧されている(我慢、頑張んなきゃいけないと思う縛りなど解放されていない)自分を知ろうとすることが方法になります。
笑わない状態から笑いやすい状態に持っていくのは、今すぐできることではありません。
少しずつ客観視して、心を主体にする自分と、抑圧されている自分を把握し、心の方を優先されてみてください。
※無理矢理の笑ってしまう時は、【恐怖心の接待中】無理して笑うのに疲れた時に最も大切なこと をご覧ください。
まとめ:笑いのツボが浅い人と深い人
ツボに入る笑いは根源であり、笑い作りの基盤になると思います。
抑圧の解放を基盤にすると、緊張と緩和、本音と建前、予測させて裏切る、想像させて反転させるなどの応用に繋がります。
これらによって笑いを提供すると、他者を笑わせるために自分の世界に飲み込むことも、笑うための材料を提示して自ら笑うこともできます。
抑圧の解放をさらに紐解くと、何が笑いになるかの研究に入ります。
面白いのは笑わないことが出来る点でもあります。
私は解放できる状態では大声で笑いますが、解放しない環境では青鬼のような目をしていますので、まず笑うことはありません。
さらに瞑想すると抑圧のない真っ新な自分を認めるため、ツボがベロンと上下に圧縮されて、高さがゼロになります。
こうなると笑顔にしかならず、笑いとはこの笑顔を如何に強く、勢いよく押し出すか、そしてそのためにどうエゴを使うか、という捉え方もできます。
笑う必要性は人それぞれですので、抑圧をなくす行動へ向かう大切さもあり、あえて抑圧を設けて笑いを作る大切さもあります。
人間だからこその笑いには創作性があり、過去の記憶との照合や認識力による情報ハンドリングがあり、心とエゴの理解があります。
どの理解を深めても楽しいのが私達人間の愉快痛快さであり、愚かさと逞しさ。
ツボに入るメカニズムにて、如何に笑い、笑わないかを探り、見出し、作り、遊ぶ一助となれば幸いです。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ピン!」と来た方はぜひお試しください。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作成してもらえます
的確にわかりやすく言語化してくださるため、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください