一見いい人だがザワザワと違和感があり、会った後にドッと疲れる。
実際には上っ面だけいい人。
表面の取り繕いに成功した人であり、物理的余裕がありながら精神的に追い詰められている人。
心迷いし普通の人。
ここでは、一見いい人、合わないという訳でもない、にもかかわらず一緒にいると疲れる人を詳細に分解し、暴きます。
わかりにくいですが実は奪う人であり見えざる搾取があるため、正体把握と対処のためにお伝えしていきます。
- 一緒にいて疲れるが理由がわからないので知りたい
- 対象把握と対処策を考えたい
知らぬ間の搾取はたちが悪いので、言語化がお役立ちになればと思います。
Contents
一緒にいて疲れる人
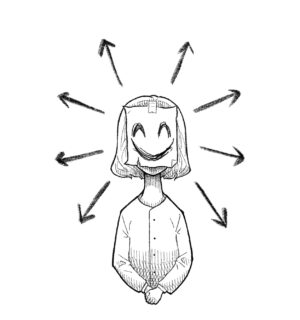
一緒にいて疲れる人:「上っ面だけいい人」
見かけはいい人、配慮も気使いも空気読みもバッチリ、周囲に合わせもするので自分勝手な印象はありません。

私の経験上、これに該当する人はそれなりに成績優秀、顔体の造形や運動神経など何かしら社会的評価を得ており、生育環境も含めて物質的に困ったことがなく、表面的コミュニケーションに長けている人物。
「なんだか会うと疲れるな、けどなんでだろ?」と疑問になります。
人によっては、「もしかして私の方に原因があるのかな?」という人もいると思います。
疲れるが、理由がわかりにくい対象。
一緒にいて疲れる場合、性格の相違、意識の違い、スピリチュアルな魂レベルの違いなど、“波長が合わない”ことがわかりやすい疲れる要因だと思います。
または自分勝手な自己愛性人格障害、実は攻撃的で作為アリのカバードアグレッション、エナジーバンパイアなど、シンプルな性格悪もあります。
一体何者なのか?
日本の近代的普通の人。
もとい、上っ面だけいい人です。
人物紹介はこちら。

・社会的中点であり、空気読み、暗黙の了解、同調圧力適応
・知的でありながら経験則がなく、机上の情報インプットに長けている
・常識的、大衆的でありながら、「自分は他とは違う」という特別感を持ち、かつ隠す
・自己表現が少なく、体裁と見栄えを気にして周囲(大衆や強い者)に合わせて振舞う
・表に出さないが内心は批判精神の塊、否定や見下し、悪口や文句を好む
・大衆美徳・ルール・常識従順があり、言われたことを努める力がある
・我慢癖、頑張り屋、自己愛が強く、他者承認欲求が強い(がひた隠す見栄と強がりがある)
・被害者意識が強く、不安と恐れを感じやすく、仮面を好んで重んじ、嘘と誤魔化しを多用(誤魔化していることも誤魔化す)
・礼儀正しく、言葉使いも正しく、服装も正しく、仕事も正しく、生活環境も正しい
いわゆる、社会的“正解”に当てはまる生活様式と人格様相を持つ人。
[日本の普通の人であり、一見正しい人]と言えるかもしれません。
こちらに合わせてくれる、笑顔で配慮もしてくれるので、一見いい人にもなります。
「暑いですね、よかったらお水飲みますか?」
「あ、すいません、じゃあお願いします」
「え?…あ、は~い、今持ってきますね~ニコニコ」

なんか引っ掛かりがありましたね。
ここでお伝えする対象は、一緒にいて疲れる“何か”をしてくる人であり、全くもっていい人ではない内情があります。
※こういう人に疲れやすい理由は、【心を護る人と消す人】人といると疲れやすい人が気を付けたいこと『無意識テイカー』をご覧ください。
一緒にいて疲れる理由12選
1,普段は穏やかだが、突然豹変する
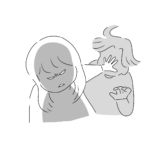
醜態を露わにしたくないので穏やかを装う、そんな自分を演じることに喜びがあります。
しかし、急に怒り出すか泣き出す、または虚無化します。
空気感を外側全面に押し出すため、空間をエゴで支配し、周囲は疲れます。
2,負けず嫌い、何があっても認めない
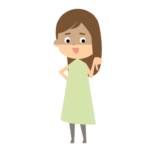
自己形成に見栄を使っており、「負け、ダメ、劣っている」など自己評価を下げるものは何があっても認めません。
口調は柔らかくても、「はは、それは絶対違う、あの人が勝ってるなんてあり得ない」と断固頑固。
3,表立って言わないが否定・批判精神

「内心、否定しかしないんじゃないか?」と思えるくらい否定・批判癖があります。
しかし露わにはせず、頭の中でゴニョゴニョします。
一人の時には姿形そのままを悠長に露わにしています。
4,表立たせないが見下し精神

自己防衛や不利益回避への強い優先があり、見下し癖を隠す努力をします。
誰かがくしゃみをした表情だけで嘲る人もおり、一生懸命やっている人の空回りをクスクスと下に見ます。
他者に嫌な思いをさせないための隠蔽努力ではなく、表立って自己評価が下がることの回避が狙いです。
5,自分の頭がいいと思っている自惚れ

「私は頭がいい」と思っており、自惚れています。
が、自惚れていると思われないように取り繕い、自慢しないように日田隠す己は爪を隠す能ある鷹だと思っていたりします。
実際には思いたい、そう信じたい思念であるため、「あぁわかる」「それくらい知っている」「それはこういうことでしょ」「言い方はこっちの方が正しいよ」
自然と偉そうな態度、あごが上向き、鼻で笑う。
無意識の言動に表れるため周囲は違和感です。
6,正しい、間違っているの善悪二元論

これも表には出しませんが雰囲気に出ます。
善悪二元論に縛られた人と一緒にいると創作性が皆無、共作や共同が存在せず、調和がありません。
常に決定付ける見方をしながら自己表現はしないので、何か言いたそうな雰囲気のみ出ます。
「どうしたの?」
「んん、何もないよ、ニコ」
賛同していないのに賛同し、共感していないのに共感する素振り。
一緒にいる時空がつまらない、否定や批判心が常に視察している空気感+演劇は息苦しい緊張感です。
7,「わかる」と言いながら何もわかっていない
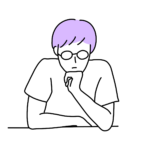
思い込みが激しく、わからないと認めない特徴。
「それわかる」と言ってもわかっていないので違和感。
「なるほどそういうことか」と言ってもわかっていないので実際に行動に移せない。
自分の意思があると思っているが実際にはないため、意思が必要なもの、例えば人間関係は成り立ちにくくなります。
理解に本質や意思が伴っておらず、関係性を成り立たせるためには“お互い”に教科書を読むような関わりになり、合わせるために我慢や気使いが増えて疲れます。
8,自立しているように振舞うが、自立心がない

自立がなく、依存と執着心が強い人。
一方で強がり、自立しているように振舞い、依存や執着していないように振舞います。
このギャップの在り様を見ているだけで、「なんかこの人自分に嘘をついているような、常に誤魔化して生きているような」と違和感になり、見ているだけで疲れます。
9,表面は優しく、実質は干渉と観察
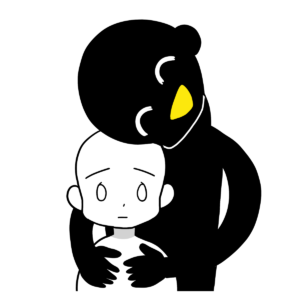
気使い、配慮、心配の優しさは、中身を覗くと自分のための他人利用。
「それ大丈夫?暑くない?喉乾いた?」
「心配だよ、頑張ってね、スゴイよもっとやって」と干渉することで感情を寄せている外面を形成します。
実際は心を一切開いておらず、社交的に明るくしながら相手の反応を逐一観察していたりします。
10,感情コントロールができない

自制力がない人ほど一緒にいると疲れます。
身近な人に対するほど怒りや悲しみを無制御に露わにし、泣いたり笑ったり虚しくなったりと感情に忙しないです。
自分の統率性が低く、それを隠蔽するためにも常識やルール従順、正当化を多用します。
“正しくない人”を探す方が楽であるために、自分のことは棚に上げて他を批判しつつ、そのさまを隠します。
11,人のせいにする、切り捨てる

自己コントロールがないだけでなく、責任を持っていない特徴。
コントロールできないのではなく、する必要がないと思えるように別のことを頑張って正当化しており、最たるものが言われたことに従う、常識やルールに則る。
「言われたことちゃんとやってるのに上手くいかないじゃないか!」と平気で他人を責め、自分より下だと思える人にだけモラハラやDVになる人もいます。
隠そうとも感情コントロールできないので、怒りは許せない怨念に。
または、あからさまに嫌な態度、一方的に関りを切るなど、切り捨てる言動を明確に表すことで自分の優位性を保とうとすることもあります。
12,被害者意識が強い
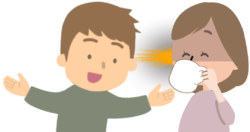
正当化が根付いており、「自分に非がある、悪い」と思っていません。
「私は責められない立場であり、被害者という正しい側である、なでなでされる側だぞ」と平然と思う、それが本人にとってのナチュラリティ。
日本では通用するであろう、「被害者は守られる」という価値観を信仰しており、井の中の蛙は外界に出ることがありません。
信仰を貫くためにあえて自分を被害者の立場に置きたがる人もおり、意図的なネガティビティをばらまくタイプもいます。
以上が、一緒にいて疲れる理由でした。
※上っ面だけいい人の詳細は、【生態性と見分け方】上っ面だけいい人の本性は豹変ではない…をご参照ください。
一緒にいて疲れる人にされていること
一緒にいて疲れる人にされていること➀:意欲的な干渉

表面上は優しいのですが、実質は干渉であり無尊重の表し。
干渉することで自由を奪う人である場合、とても疲れます。
自由を奪う干渉の典型例がこちらです。
- 期待
- 心配する(させる)
- 気にする(させる)
- 依存、執着する(させる)
- 嫉妬する(させる)
- 勝手な解釈
“する”だけでなく、“させる”行動も目立ち、強要ではなく間接的に誘引・誘惑します。
※例えば、心配させる言動をあえて相手にするなど
自分のために好んでこれらの干渉行為をします。
例えば、人を心配するのは相手のためではなく、自分の不安感を和らげるため。
「大丈夫?可哀想、大変だよね」と言いながら全く見当違いの解釈をします。
親であるならば毒親タイプであり、自分を毒親だと微塵も思っていないというまさに典型。
心配のつもりで嫉妬を使う人もおり、「怒りではなく悲しい気持ちだから嫉妬じゃない」と勝手な自己都合世界を生きます。
人によっては、親でもないのにまるで親かのような接し方を他人にします。
「これは執着ではない、あの人のため」
「え、そんなことして欲しくないですけど」
「いいんだよ恥ずかしがらなくて、正直にして欲しいと言っていいんだよ」
理解しているふうで何もわかっていない、わかる気もない、そもそも他人に興味はない。
相手の思うままに関わらせると、「自分」という存在は全く別物として解釈され、心配や期待でその自分像に矯正させるためのプレッシャーを与えてきます。
こちらは自分であることの資源を消費させられ、自分が自分でなくなる感覚を味わいます。
疲れます。
知的で表面的であるため、干渉する狙いがありながら、「干渉している」と認識しないように誤魔化し、あわよくば被害者になろうとします。
実行動が見えにくい“隠蔽体質”であるのが見極めを難しくします。
※気の使いすぎで疲れる理由は、相手も疲れる優しさの呪縛【気を使いすぎて疲れる人に大切な理解】をご覧ください。
一緒にいて疲れる人にされていること②:境界線の侵犯

上述➀の意欲的な干渉が実行動です。
『自分の中で処理できない“不安と恐れ”を代わりに処理させるため』が狙いだと考えられます。
不安を感じた時の心地悪さを扱えず、処理できず、自己対処する気がない結果、他人に近付いて仲良くなり、表立ってあからさまな心配や期待や気使い、またはそれらをさせる言動をします。
言動を際立たせることで、相手の反応から安心できる材料を出させようとします。
例えば、「モリ子ちゃん、最近元気ないけど大丈夫?私とっても心配で夜も眠れない」
「モリ子ちゃん聞き上手だから、元気になれるように頑張ってまた私の話聞いて欲しいなニコニコ」
「え…うん、心配してくれてありがとう(何言ってんの?こっちの状況考えなさいよ、なんて言えない、トホホ)」
まるで尊重がない、けれども本人は真面目に自分のことしか考えていないと気づいていない、気づく気もない。
表面上の言動や態度は配慮するが、本質的に自分にしか興味がないために平然と相手の心理や感情的境界線にウネネと我をねじ込みます。
まるで「元気になるって言え!」と言わせるように、相手から安心材料を出させて己の不安を和らげるための他人利用。
調和や思いやりであれば円滑な人間関係になりますが、心を開かず他者に着目がないために、自分が利益を得る代わりに相手は疲れる交換制度。
それに気づかなくなりながら、本人は因果を積み続けていることに気づく由もありません。

問題はこれを良かれと思っている人もいること。
境界線の侵犯という捉え方ではなく、自分の不安や恐れを代わりに処理してもらう(またはさせてあげる)ことこそが親密であるという根本的な見下しと支配メンタルの持ち主かもしれません。
※優しすぎる(いい人すぎる)場合、自分を利用させてあげる自己犠牲が思いやりだと思う人もいますが、ここでお伝えしているのは自称優しい人であり、全くもっていい人ではないので全く別人です。
※実は怖い人については、「いい人だけど…会うと疲れる」【実は怖い人の対処法】をご覧ください。
一緒にいて疲れる人にされていること③:自己矛盾処理の代替

『自己矛盾』
例えば、
わかっていないのに、わかっているフリをする。
自分の意思がないのに、意思があると強く思い込む。
自己評価が低いのに、自己評価が高いと強く思い込む。
自立していないのに、自立しているように振舞う。
誤魔化しているのに、誤魔化していないように装う。
他人に興味ないのに、干渉したくなる。
強くないのに、強がっていきる。
大衆的でありながら、自分は特別だと思う。
不安でいっぱいなのに、不安がない自己世界を生きていると思い込む。
他人利用しているつもりはないが、実際はしていると気づいている。
脆さと強がりが一緒くたになるように、怒っているのに怒っていない、自分がないのにあると思い込むように。
理想と現実が矛盾を抱えながら一つの意識に収めるさまは、強情と執着以外の何ものでもありません。
過去の出来事を認めず、「こうだ」と思い込みたい空想を強引に型にはめ、妄想を現実に仕向ける支配的認識構図。
自己矛盾によって嫌な気持ちが生まれ、対処できないために他責で外に出す結果が、干渉、心配、期待、気にするなどの意欲的言動(+それらの隠蔽)になります。

精神的に、自分で処理するものであり、自分以外に処理できないものを代わりにさせようとする在り様。
安心を貰うことが目的であるため、事実もネガティブも一切要らない。思い通りのものをくれなければ失望落胆、裏で否定に批判。
安心感をくれそうな人、誘導できそうな人、不安を処理してくれる人を欲し、人を選んで自己矛盾処理の代替に人間関係を使います。
一方、自己矛盾を誤魔化してさらに現実から逃げようとする場合、自分を大きく見せる強がり、マウント、支配的態度、見栄を意欲的に発する干渉になります。

心配して優しそうでありながら、マウントを取る支配的態度と両極端ですが、同一人物です。
メンタルと精神状態によってどちらの面が出てくるか変わります。
ちなみに、この心理では潜在的に「自分より下」だと思える人と関わろうとする傾向があり、身近な人ほど私物化や支配的な言動が顕著になります。
※要注意人物の詳細は、【危険人物には直感を活かす】離れた方がいい人と関わってはいけない人の特徴 をご覧ください。
疲れないために:防衛必須
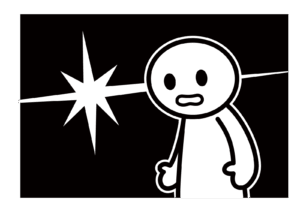
実際にしていることを要約するとこうなります。
自己矛盾 + 境界線侵犯 + 利益・不利益の操作的意図 = 周囲は疲れる
これらを取り繕いと正解を狙う演技にて織り込めるので、感受性の高い人でなければ気づくことすらないわかりにくいものかもしれません。
この内容で際立たせたいのは、『本来自分で処理するものを、意図的に代わりにさせようとすること』
なんで不安を自分で対処しないのか?
精神未熟で自立がない、自分との向き合いがない、向き合う気がないためです。
だからこそ自己矛盾を作り、不安や恐怖を味わうのはおろか、見つめることもできず、結果的に隠蔽と誤魔化しと正当化と否定と被害者お面を多用する。
注目したいのは不安の処理ができなくても、それをあえて外側に出すか、克服できるできないにかかわらず内に収めて向き合い見つめるか(=考えようとするか)は選択できることです。
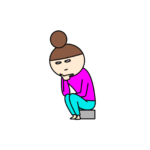
子供であれば、「もう無理だ、怖い!」と意図せず相手に干渉することはあります。
しかし、ここでお伝えしている対象は“意図的”に外側に出します。
わざと境界線を犯し、わざと自己矛盾を自分でなんとかしない。
他人という存在は利用するためという観念体系があり、教科書は覚えられるが自分の頭で考えることを放棄している、またはそれを認めないのでやり方を学ぶ気がない可能性があります。
育ちが関わると考えます。
意図的であり、反省も成長も改善もする気のない人は、親や社会性など他に従うだけの生き方をしてきた人、そして苦労知らず(だが本人は苦労自負するタイプ)に多いかもしれません。
悲劇のヒロインとして主演でありたいと自己世界から出る気のない人は変わりません。
「疲れるから何なのか?」という話でもあるので、対処は人それぞれに必要有無が分かれると思いますが、自他両方のためにできることもあります。
関わりを減らす。
関わることは自分のためにも、相手のためにもなりません。
不安緩和できる術を知っているため、関わることは相手のエゴを増長させ、より自己評価を高めたかのような世界にのめり込む可能性があり、演舞の装飾は増えていきます。
そして何より、平気で境界線の侵犯をさせてはいけません。
自分に対する尊重が壊れてしまいます。
対策は防衛が望ましく、関わりを減らすことがおすすめです。
相手に気づかせてあげようと優しさを持つことも得策ではなく、この対象に該当する人は心を開いているようで全く開いておらず、開く気もありません。
開かない以上は損得勘定と社会的利得有無が関わる動機になり、片方が我慢し続けることが義務化されます。
疲れないためには防衛必須です。

・関わりを減らす
・境界線と距離感を明確に保つ
・相手の要望や被害者面に共感しない
・心配、期待、気使い、嫉妬の干渉は、冷静に当たり障りなく流す
・やり取りは対面ではなくメールや文面にシフトしていく
・相手の都合で会わない、プライベートで会わない、会うならこちらの都合で会う
・関わる環境を職場だけ、お昼だけと限定していく
ご参考になるものがあればと思います。
※自分側を見つめたい方は、【自己磨き専用】人に会うと疲れるスピリチュアルな理由『心の因果』をご覧ください。
最後に:一緒にいて疲れる人
世の中にはわかりやすい性格悪や合わないさまがあります。
一方、この内容のように無知と無明による自己固執、我(エゴ)に特化させたパターンもあります。
エゴは防衛発達意識であるため、常識や社会ルールへの従順を得意としており、社会適応力の高さから合っているように装うなど、事実を歪めながら歪めていない誤魔化しを得意とします。
一緒にいて疲れる人は意外にも身近におり、今日も気付かれないように実行動に及びます。
本人は自らを誤魔化しているので自覚がない素振りをします。
が、実際は自覚があります。
表面化と隠蔽能力を育むことで“普通”を活かし、気付かれずに利益搾取できます。
そして大きな利点となるのが、搾取しながらも悪意なく、概念と照合して捉え方を異色のものにできます。
「良かれと思って心配しているだけ、オホホホホ」
意欲的な干渉に、自己矛盾を代替させる人は、精神的に捉えると煩悩の塊です。
エゴの塊でありながら、装いという脳機能の多様にてまるで別物に仕立て上げ、現実に目を向けません。
しかし、どうしても拭えない、本人も誤魔化せないものがあります。
心の迷い。
煩悩多き心の迷い人は自分との向き合いなくしてどこに向かうのか?
他人利用以外に私は知りません。
それをも誤魔化せるのは社会性、概念による表面化、事実の隠蔽、暗黙の世、正しいという虚無。
じ・ゃ・ぱ・ん。
人間を見る一助となれば幸いです。
ありがとうございました。

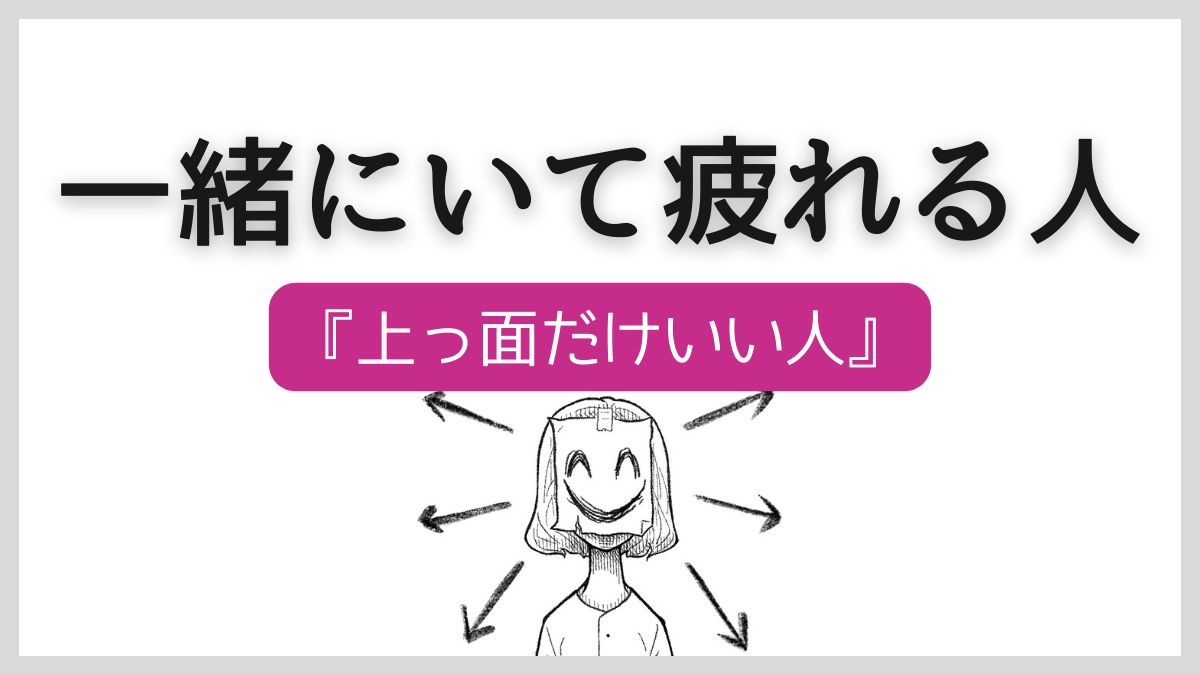




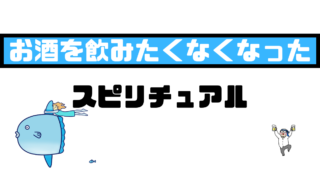
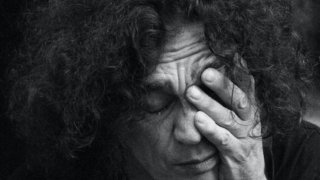






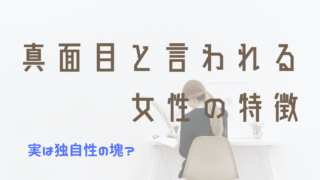




これに該当する人、違和感ありありながらボヤけてて他人に説明できない気色悪さ。ニコニコ笑顔で「あなたは素晴らしい!ステキ!大好き!」「あなたのようになれたらな〜」と、反吐が出そうな言葉をいっぱい投げられました。
ウンウン!と頷きながら完全に人の話は聞いてない。明らかに。
「大丈夫!?心配だ…」と言いながら、微塵も優しさや思いやりがない。明らかに。
そしてびっくりなのが、周りの人達がそれに気づかない。
このペテン師を悪く言うと簡単に悪者になってしまう私。
気づきすぎるとただただ苦しいだけですねー。いくら説明しても誰も理解しない。
孤独でしたが、また一つ浄化されました。
ありがとう🎶