【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ぜひおすすめしたい」と感じたのでご紹介です。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作ってもらえます
「なんでこんなにわかるの?」と思えるほど的確で、わかりやすく言語化してくださり、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください
言ったことが相手に届いていない。
うんうん言っているけどわかっていない
依頼が遂行されたことがない。
話を変えられる。
意思疎通ができない。
話が噛み合わない。
「同じ日本語なのになぜ?!」と思うことがあります。
話が通じない人にはイライラや疲れが伴い、ストレスになり心身への影響があります。
そこで、話が通じない人の実情を知ると、疲れやイライラを解消できます。
ここでは、疲れてイライラしてお困りの方を対象に、話が通じない人の特徴と対処法を見ていかれてください。
- 話が通じない人とは何者?
- 疲れてしまう時にはどうすればいい?
これらを紐解き、話が通じない実情を知っていただく内容となっております。
疲れないための対処として、実情理解がお役立ちできれば幸いです。
Contents
話が通じない人の特徴

話が通じない人とは?
話が通じないのは話を理解しない。伝える気持ちも、意思も、意志も、目的も理解しない。
話す人を認識していないことを意味します。
繋がりのなさを表し、意思疎通の合致がなく、調和や共有といった相互理解や交流が起きておらず、会話をした意味が話し手から消えます。
会話しようと試みたのに、一瞬で一方通行の会話でも対話でもない単独舞台が始まります。
話が通じない人とは、相互交流する気がない人。
相互の意識がないと、相手を思ったり、考えたり、気持ちを汲み取ったり、理解したりといった認識がありません。
他者認識力がない状態。他者の立場や目線で物事を考えたり感じたり予想したりができません。
話が通じない人は他者を認識する余裕がない
話が通じない人は悪い人ではありません。
わざとやっているわけでも、危害を加える気もなく、ただ話が通じない。
「相互交流する気がない」のが、話が通じない人を象徴します。
相手を認識できないのではなく認識する気がない。しかしわざとではない。
相手を認識する余裕がないと考えられます。
話が通じない人の人間性、自分を何よりも愛したい自己愛の強さが関わります。
自己愛は大切な人間の姿ですが、強いと他者への配慮や思いやりよりも、遥かに己を優先します。
思いやりだと思っているものが、思い込みや決め付けにコロッと変換されます。
しかし、それに気づきにくいのが自己愛の強さ。自分が嫌がることはしない自然なさまには自覚がなく、話しが通じないと思われていることに気づかないほど、認識が自分に集中します。
話が通じない人とは自己愛が強い人間性でありながら、現状自分への愛の欠如があるために他者を認識する余裕がない人と考えられます。
話が通じない人の特徴9選
対処しやすくするためにも、どんな人なのかをより深く理解していきましょう。
1,自己愛が強過ぎる
自分のことを大切にし過ぎて、「自分自分」になります。
2,自己主張が強い
自己愛が満たされていないことを表します。
自己愛が強いにも関わらず愛がない(または注ぎ込む愛が少ない)ために、自己愛の矛先は他者から愛を貰うことになり、主張します。
3,自分の世界からのみ物を言う
自己主張は己の世界観の剥き出しになり、自分の世界のことは他の人もわかっているかのように話し、突拍子もないことを誰しもが理解している前提で話し進めます。
突然話が変わっても気にせず、常に自分の世界に入った状態で他界に物を言います。
4,わからないと言わない
自己の正当化意識が強い特徴です。
「自分が間違っている」とは思わないようにし、断固貫きます。
正当化が癖のように根付き、わかっていないのに理解したつもりになりきり、疑わないようにします。
5,否定されることを何よりも恐れる
自分で自分を否定していると思わないための自己防衛優位です。
不安や恐怖を嫌がる特徴があり、特に他者から否定されるとブチキレる人もいます。
恐怖を内包する人間性、否定された、自分一人では何もできない、周囲に言われるままに生きてきた、それを強いられたなど、心の傷を持っている人もあります。
6,思い込みが激しい
思い込みが激しいために変化しない特徴です。
変化を好まず、自らの正当化や否定への恐怖がない様を優先します。
7,頑固
話が通じない人に共通するのは、不安や恐怖(否定・苦痛・危険)を受けないことに対する頑固さです。
徹底的な自己防衛を変えない固執があり、人や仕事など一定の関わりが構築された場合には変えることを好みません。
8,環境適応能力が低い
環境が変わっても馴染ませたり、合わせることを好みません。
海外で日本のルールを押し付けるイメージで、自らをその場に合わせて変化や柔軟にさせません。
9,人を利用する
「嫌なことを味わいたくない」という願望が強く、自らを変えるのではなく他を利用したり執着することで利益を得て、願望を叶えようとします。
自分が嫌な思いをするのであれば他者を利用して回避しようとする人もいます。
「助けたらいつの間にか一人で逃げてるー」なんてこともあり、無用に手出しすると見捨てられる可能性があります。
以上が、話が通じない人の特徴でした。
※話が続かないイライラは、会話が続かない人へのイライラに答えがギュー│対処法は既に自分の中 をご覧ください。
話が通じない人 疲れる
話が通じない人は疲れる
相互交流する気がない人は悪気はないのですが、相手が話しかけてきた行為を自分の世界の出来事に変換する傾向があります。
相手の立場や目線に立つ状態がなく、癖になっているため無意識にしており、話しかけられれば自分の独断場にします。
話しかけた人の話す目的すらも奪い取るように独断場にしてしまい、会話の決着がどこかに行ってしまい見えなくなります。
動機、気持ち、目的を持って話すと決めた行為、全てをちゃぶ台に乗せてドーンッ!とひっくり返される状態です。
呆気にとられ、イライラし、相手を見ると、「あれ、この人わざとやってない?」と悪気なし、「どうしたものか?」と考えさせられます。
話が通じない人の世界に入れ込まれて好き放題され、一方的に悩まされ、困らされ、考えさせられ、まるで宿題のように義務を課せられます。
これは疲れてしまいます。
疲れる時の対処法
離れるのが一番明確な対処ですが、お仕事などそういうわけにもいかないかもしれません。
関わったとしても疲れないようにしたいものですので、「話が通じないけど、まぁ気にならない」という状態にします。
対処ポイントは、話が通じない人の世界に入らない、入れられないことです。
話す空間がアウェイになっていると気づく
話す時に必ず起きるのが、話が通じない人の空間になることです。
- 陽気な性格であれば、悪気なく周囲を気にせず一方的に話す
- 陰気な性格であれば、悪気なく周囲を気にし、一方的に話させたりと人を利用する
話が通じない人に疲れる場合、翻弄されて話す目的を見失っている可能性があります。
相手のホーム、アウェイにいながらの対処は困難です。
もし相手を否定すると逆上してキレたり、泣いたり、本気で反応することもあるため、悪意のない人に対する自らの行為を反省し、懺悔になりかねません。
対処は如何にアウェイにならない(自分の目的を見失わない)か。相手の世界に飲み込まれなければイライラも疲れもなくなります。
話が通じない人の実情を理解すると役立ちます。
詳細に入りましょう。
疲れる対処:話が通じない人の実情を知る
話が通じない人は恐怖と愛の交錯が起きています。
恐怖への意識が強いために自己愛が激化して余裕がなくなり、他者に認識が向かわない状態です。
理解ポイントは恐怖に飲み込まれた人ということです。
恐怖とは、認められない、知りたくない、味わいたくないなど、拒否行為をもたらす基。拒否、苦痛、危険に対する認識です。
誰しも嫌なものですが話が通じない人は特段嫌がり、恐怖に飲み込まれている状態を認めないために変化を求めず、思い込みを激化し、正当化を図り、自己主張し、愛を欲する様が自然と表れます。
他者から優しくされたり助けられると、執着して近寄って利用する傾向があります。
本人の中で変わらないように努め、正当化して思い込むので、理解していないのに理解している気になります。
事実を真っ直ぐに見れなくなり、会話を飲み込んで自分の世界に入れて、嫌なことを味わわずに済む状態にしようとします。
能力がありながらも発揮できなくなり、仕事もミスが多くなってしまう在り方を自らしている状態です。
話が通じない人の内側で起きていることを理解すると、相手の世界に入らないようにする意識を持てるため、対処が容易になります。
疲れないためのおすすめ対処
疲れないために相手の世界に入れ込まれない。そのために実情をご覧いただきました。
実情を知ると相手を俯瞰して認識できます。疲れないために俯瞰性を持ち、相手を知れます。
疲れないための対処法は、自分を向上させるための機会にすることです。
如何に自分を成長させるために話が通じない人と関わるか、という考え方です。
話が通じない人は、質問力、先読み力、俯瞰性、他者認識力、要点をまとめる速度、思考内整理の上達、柔軟性向上、切り替えの転換・工夫など、人間関係で重要な能力向上の鍵を握ります。
疲れを学びや向上の成長機会にできるため、関わる意味と動機ができ、目的が話が通じない人自体になることで、飲み込まれて目的を見失うアウェイにはなりにくくなります。
関わる目的を話が通じない人にすると自他共のためになる
自らのために話が通じない人と関わる目的を持つと、相手を否定しなくなります。
話が通じない人には、否定せずに肯定することが大切です。
拒否しない状態に肯定を付け足すと、自らのためになりながら相手のためにもなり、相互交流が加速します。
「相手のためにしている」と思う必要はありません。相手を関わりの目的にすることで、一方的に相互交流を切って独断舞台を始められたとしても、こちらから相互交流を持ち寄れます。
これをするためにも実情理解が重要になります。
話が通じないとしても悪い人ではないので、肯定される喜びの状態には心を開きます。
気づけば相手も自分も意味のある関わりの場となり、どちらもアウェイではない空間共有になると、目的を見失わず自他のための場となり、疲れもイライラもしなくなります。
※頭が悪い人に話が通じない話は、頭が悪い人と話が通じない時に知れること│実は人生の先生なの?!をご覧ください。
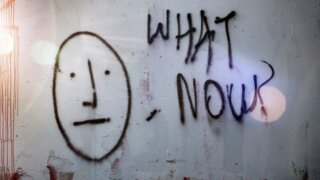
話が通じない人は疲れる まとめ
如何に相手の世界に入れ込まれないようにするか、如何に自らのホームを保持するかが対処には重要です。
自らが話す行為の目的を、「自分のため」という成長の利益に繫げます。
話が通じないと話す意味が見出されないので、継続は自分のためにはならず、相手に対する奉仕活動になりかねません。
相互交流する気がない人に無理強いしても、自らが疲れてしまうので関わらないのが得策です。
しかし、関わりがせっかくある場合には、話が通じない前提理解をし、目的を会話ではなく自分の学びや向上の成長のためにしてみてください。
相手を利用するのではなく、如何に相手を活かした状態を作りながらお互いの利益を生み出すかを考え、否定せず肯定しながら自分のために関わると、話す意味がもたらされます。
恐怖を糧に己を構築する人の貫き度は鉄板のように硬いため、鉄板をひん曲げるのではなく、熱して焼きそば作っちゃう。
そんな考え方が良い塩梅かと思います。
目の前の人との繋がりにある経験や育みが役立つ内容となれば幸いです。
それでは、話が通じない人に疲れる時の対処のお話を終了します。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ピン!」と来た方はぜひお試しください。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作成してもらえます
的確にわかりやすく言語化してくださるため、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください





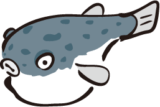
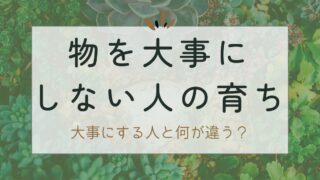

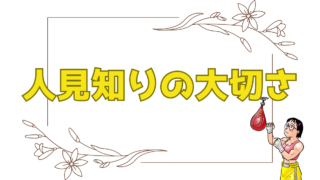



追記
変わらないから変えないから!とまるで自分に言い聞かせるように言っていたのは、私が注意したことで普段の相手の行動を否定してしまったからなのですね…
とても理解しました
理解するための洞察をされていますね、素晴らしい。
難しいですが、相手のことがわかると、距離感を持った関わり方ができるので何よりかなと。
すごいです…!めちゃくちゃ当たってます…!
まさに話が通じない、人が話し始めれば全て自分の話、お前の話は俺のもの、俺の話も俺のものじゃないですけど、そんな人がいて…
この間、あまりにもその様や、他の決めつけが酷いので軽く注意したら、私は変わらないから、変われないし、変わる気もないから、関わったらそっちが嫌な気持ちになるだけだと思うよ、とか言われました…ええ…とても嫌な気持ちになりました…その発言で…
でもそこには確固たる自分を変えてはいけないんだという、強迫観念のようなものが見えました…
北斗さんの記事を読んで、全くその通りだったので凄く納得しました
ありがとうございました