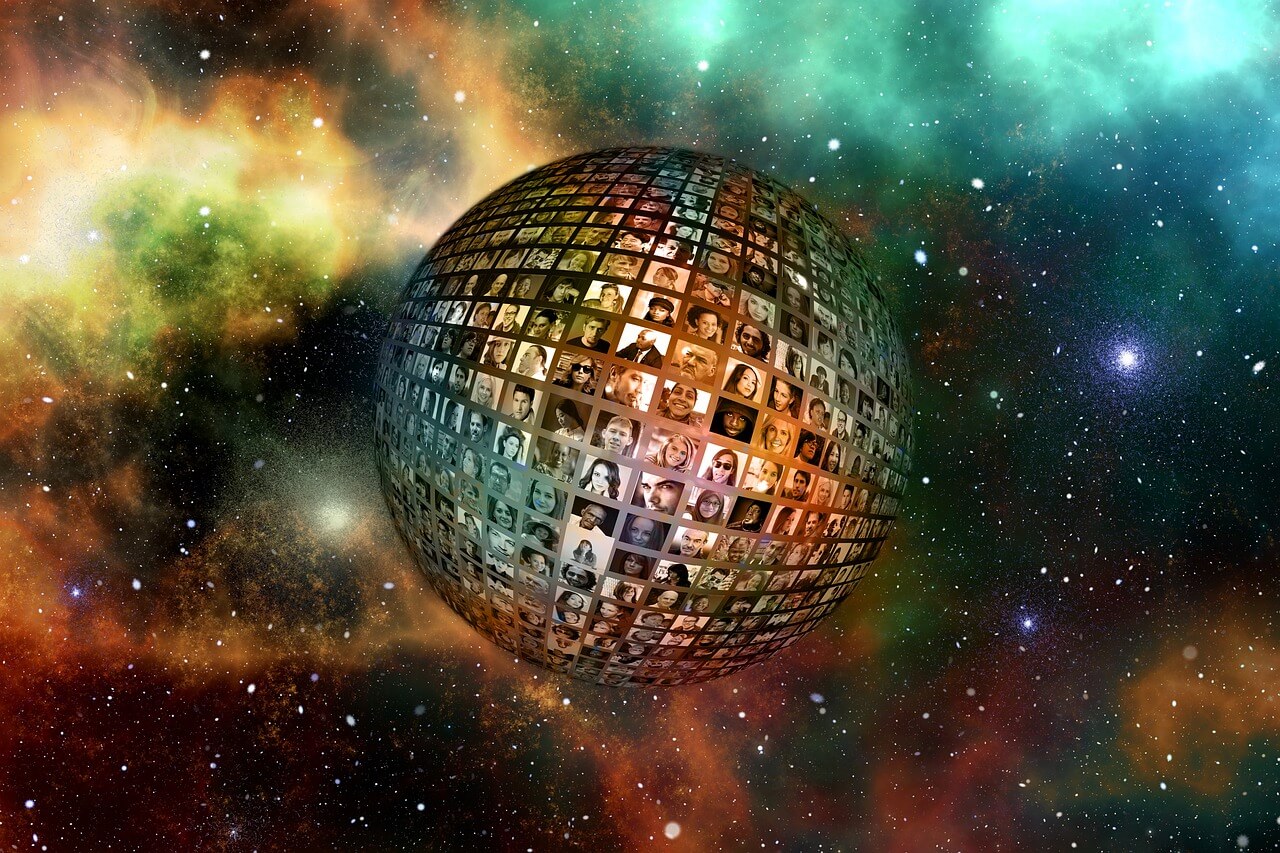『DNAシフトセラピスト養成講座』
・セラピストになりたい方・自己理解を本格的に始めたい方
・専門的に人を癒し、サポートしたい方
 著名な心理セラピストとして知られる、西澤裕倖(にしざわひろゆき)先生プロデュース。
著名な心理セラピストとして知られる、西澤裕倖(にしざわひろゆき)先生プロデュース。PR:株式会社Central&Mission
※本気で人生を変える方専用。
飽きずに何年も同じ喫食。
朝は同じ、夜は少しバラエティーな工夫を加える人もいると思います。
私は毎日同じものを食べる傾向があり、海外を旅している時と日本にいる時に違いがあると気づきました。
違いには、毎日同じものを食べて飽きる・飽きない理由があります。
ここでは、毎日同じものを食べる人の内情と真意に迫ります。
- 同じものを食べて飽きない人の性格を知りたい
- 毎日同じものを食べるメリットを知りたい
飽きない理解を深める内容となっております。
ご自身の認識を高めるために、一つの考え方となれば幸いです。
Contents
毎日同じものを食べて飽きない人の性格

そもそも、同じものを食べて飽きるのはなぜ?
しかし、「飽き」をどれくらいのスパンで見ているかが人によって違います。
人によっては今この瞬間のみを認識しており、同じものを食べても新鮮な気持ち、「またこれ」と捉えません。
「当たり前」と思いにくい認識をしていると、飽きにくくなります。
「当たり前」を認識する人ほど飽きやすい性格に。
「当たり前」を認識しない人ほど飽きにくい性格に。
何でも食べられる環境では、「当たり前」が作られやすい
日本は食の国。
飲食店の多さ、食文化の多様化、食への興味・関心、欲の強さ、価値観の特異性。
Youtubeやテレビはご飯食べる動画ばかり、幸福を感じる瞬間ナンバーワンは「美味しいものを食べている時」
多種多様な食材に料理が年中食べられる環境、なんといっても不味いものがほとんどありません。
お米ですら美味しく、漬物ですらメインそのもの、コーヒーと同じ値段で一汁三菜食べられちゃう。
ここまでいくと食事は利益そのものです。
いつでもどこでもなんでも食べられる環境であればあるほど、「当たり前」という認識になりやすく、慣れが恒常化して飽きやすくなります。
おそらく日本は、毎日同じものを食べることに違和感を感じやすい場所だと思います。
[同じもの=刺激が少ない=利益として認め難い=飽きる=同じはつまらない]
快楽だけでなく、健康管理も含めて、心身の喜びを見出すために毎日さまざまなものを食べる動機が作られます。
慣れないように刺激を求め続けられる、そんな環境が整っているのが日本かもしれません。
毎日同じものを食べて飽きない人の性格:自律

食環境に従う以上に、自らの意思や価値観を主体にした自律があると考えられます。
たくさんの食材があっても食べるか否かは人それぞれ。
スーパーの照明や陳列心理に飲み込まれず、主体的にズンズンと店内を進みます。
気づけばかごの中はいつもと同じ、納豆に卵に鯖。
これは私の場合ですが、心理や健康状態、または欲に合わせて食べ物を決めると、自分自身の状態や環境が変わらない限りは同じものを食べます。
突然南米に出張となれば、現地での心理や健康や欲に合わせて調整され、同じものを食べる、そんな具合です。
毎日同じものを食べて飽きない人の性格:「自分にとっての利益」が明確
「世の中はこう、だけど私はこう」
同じものを食べる以上、それが自分のためになっている理解があるからそんな自分に従います。
例えば、お金を節約できるから毎日同じ献立の人もいます。
肉体と食材の相性を考えていろいろ食べた結果、ある食べ物に落ち着いたから食べ続ける人もいます。
自己ルールに基づくさまには自分の意思があり、何が自分にとっての利益かしっかり把握します。
同じものを食べて飽きない人のキーワードは、「自分が主体」
人によって欲に忠実なさまであり、思考に基づく自己利益追求でもあり、他のルールや社会環境、お国柄などに飲み込まれず、自らを主体にするのが飽きない人です。
※同じものを食べていても味覚が変わる理由は、食べ物の変化と味覚の変化で幸せが始まる|意識と波動で変わる体さん をどうぞ。
欲に従う結果、同じものを食べ続ける人もいる
色々食べたいと食欲や物欲が盛んな人もいますが、食事に興味がない人もいます。
私達人間は生きることを目的に本能が活動してくれますが、今の時代では生きるために食べる人はあまりいないと思います。
生きる余裕があると欲を優先して、満足や納得しようとします。
自分を喜ばせたいから欲を持ち、喜べる食べ物で喜び続ける、というシンプルな状態。
自己愛があり、感覚・感情優位で、今を生きる認識があればあるほど、この兆候が強くなると考えられます。
欲を優位にして自らを喜ばせるために肉体が働く状態ですので自制がかかりずらく、健康面の配慮が弱まる可能性があります。
自己防衛による欲に従う結果、同じものを食べ続ける
怠惰欲やホメオスタシス(生態恒常性)、不安や恐怖心を味わいたくない防衛意識に従うと、いろいろなものを食べることでの不利益をなくせる、そんな利益を得られます。
- めんどくさいことをしない
- 失敗しない
- 献立を考えなくて済む
- 手軽で簡単
- 労力不要
- 無駄な消費削減
辛さや嫌悪や拒否したくなることなど、不安や恐怖心を抑えられるので、あまり余計なことはせずに同じものを食べます。
さまざまなものを食べる以上に、同じものを食べることに心理的な利益があるので、飽きる理由がなくなります。
共通点:同じものを食べても飽きない人の性格
自分にとっての利益を自分自身で認め続けられることです。
自己ルールや意思が主体、認識主体(自分を信じる)、欲求主体、防衛主体の違いが人によってあります。
自己ルールに従う際には意思を持って自らを律し、思考や知性を使用して同じものを食べることに利益を認めます。
認識に従う際には自分を信じている前提があり、経験や体験した理解を基に、毎日同じものを食べることに利益を認めます。
欲や自己防衛に基づくことが自分の利益である人もおり、快楽を得たい気持ち、苦しみたくない気持ちに忠実です。
利益を認められない場合には喜びがなく、つまらなくなり、興味がなくなって飽きるので、毎日同じもので飽きないことは、毎回自分の利益になっていると認めるさまがあります。
習慣化して自覚しなくなる人もいると思いますが、無自覚でも、「あぁするよりはこっちがいい」「これがベストだ」と潜在領域では常に認めている状態です。
飽きない人の性格は自分を主体にする在り方があり、主体性の内訳が人によって異なります。
- 自己ルールに従う自律
- 自分の認識を信じる自律
- 欲に従う利益追求
※食べることに興味がない人の内情は、食に興味がない人の特徴と心理|偏食も少食も自然な自己理解と喜び をご覧ください。
毎日同じものを食べるメリットと注意点

毎日同じものを食べて飽きないメリット
「何が自分にとっての利益なのか?」を明確にできるため、合理的で効率的に食事の利益を得られます。
私が海外にいた時はこんな具合でした。
カンボジアではフランスパンによくわからない具を挟んだ屋台飯を、飽きもせず食べ続け、節約にも時間の有効利用にもなりました。
メキシコではタコスばかり。山奥に行けば一種類の郷土料理を食べ続け、土地の人々の食生活や味の傾向、現地のお母さんしか作らないおふくろの味を知れました。
アフリカでは薄いビニール袋に入れた豆汁とご飯のグチャグチャのを食べ続け、地元の食事事情を経験。今にも破れそうな袋と向き合う食べ方を知り、現地の考え方も知ります。袋を使う意味やその後の処理などを知ると、インドが清潔に感じるアフリカ感堪能でした。
民族地にいけば芋を練った粘土みたいなのを一ヵ月間食べ続け、現地の人がどうして飽きないのか、一生これのみを食べていく心境を理解できました。またそれだけを食べる意味は食べ続けるとわかり、精神的に大切な理解になりました。
主体性があると、その場その時の環境、状態や状況を踏まえて物事を捉え、自分にとっての利益を見出せます。
私の場合の利益は、「知ること」に重きを置いていますが、人それぞれに主体性を基にした利益を作る基盤になります。
自分として生きるための必須アイテムですので、主体性を高めるメリットはかなり重要だと思います。
しかし、注意点もあります。
注意点:「正しい間違いはご法度」
「私はこれでいいと思っている」が恒常化すると、当たり前になります。
「当たり前」は意思を知らぬ間に喰いちぎり、飲み込み、それに気づけなくなります。
自分の利益フォーカスが強くなり、周囲が見えずに自分勝手になったり、自己管理が欲の解消に傾いて健康を害したり、同じものを食べることから変化できなくなります。
自律や主体性は大切ですが、物事を正否判断すると当たり前が頭の中にはびこり、見えていたものが見えなくなっていると気づきにくく、気づいた時には身体がおかしいという危険性があります。
私はこれを経験して痛い目を見ました。
いつものように納豆、卵、鯖の塩焼きばかり食べていました。
何の問題もなかったのですが、普段の生活とは違って、家のリノベーションを始めた時に問題が起きました。
栄養素が足らず、普段とは違う状況や状態であるにもかかわらず、食事に変化を加える概念がなくなり、体が壊れて倒れました。
普段あまり動かなければ肉を食べなくても大丈夫ですが、肉体労働時には動物性たんぱく質や脂が必要となり、自分のいる状況や環境次第で何を食べるかを変える大切さを忘れてしまっていました。
もし思い当たる場合は、お気を付けください。
※食欲の心理は、「食べても満たされないのはなぜ?」│食欲が止まらない心理とスピリチュアル をどうぞ。
同じものを食べる際のおすすめしたい考え方
飽きる場合には何かしら喜びの喪失として、自分の利益を認められなくなっている状態が考えられます。
これは飽きるのが良い悪いではなく、飽きることでサインを得られる意味です。
[飽きる=自分で利益を認められていない状態]
「何が自分にとっての利益か見出しにくい状態が今ある」とわかれば、するのは飽きないことです。
[飽きない=自分で利益を認められる状態]
飽きたら飽きなくするのがまさに主体的に行動する人。主体的に物事を捉えて、自分にとってどうすればいいかを考える機会になるのが飽きです。
飽きなくなった時は飽きる大切さがあると理解しておくと、欲にフォーカスし過ぎて好きなものを好きなだけ食べることを自制でき、当たり前をなくして知らぬ間の不変の在り方を解消できます。
両方をサインとして活用できるので、「当たり前」をなくして自分の感覚と思考で物事を捉える目線を持つと、飽きも飽きないも共に自分の喜びを作り、バランスを図る材料にもなります。
飽きたら何かしらアクションを起こすタイミング。飽きなければ注意点を忘れずにバランスを図る状態です。
※食べ物以外の飽きる飽きないの違いは、【人生に飽きたからこそわかる合図】飽きない人との違いと対処法
肉体が求めている食べ物の大切さ
「自分にとっての利益」
この言葉は本当に人それぞれに何が利益か変わります。
ほとんどの場合は刺激や快楽や満足や納得だと思います。これは脳が求めているものを食べる状態が主です。
- 脳が求めている食べ物
- 肉体が求めている食べ物
脳が求めるものを食べると刺激を含めた快楽を得られるので、束の間のエンターテインメントになりますが、もし継続すると当たり前の恒常化や健康を害する危険性があります(バランスを図るためには大切)。
同じものを食べる際、肉体が求めているものを食べるのがおすすめです。
肉体が求めているものを食べると主体的に利益を作れる上に、健康状態が良好になります。
腸を敬う生活作りになり、胃腸などの肉体利益を主体にする在り方です。
例えば、納豆、白米、みそ、卵、ヨーグルトなどを飽きずに食べる人は多いと思います。
私もそうでして、洞察すると無意識に肉体が求めているとわかります。
私の場合、納豆をおいしいとは一切思いませんが毎日食べており、私の約10%は納豆でできています。納豆の味を好んでいないので脳は喜びませんが、腸が喜んでいるので食べても飽きません。
醤油をかけると脳が少し踊り、「これは刺激だぁ、やったね」と利益を認め、おいしいと思ってくれます。上述の飽きる飽きないの活用です。
脳以上に肉体の利益を認識している人は、同じものを食べても飽きず、体が快活になりながら思考もクリアになる利益を体感されていると思います。
「肉体の意見を聞いているから飽きないんだ」と理解されると、よりご自身の健康や思考に利益をもたらせますので、お役立ちできればと願います。
※食べることの少し変わった捉え方は、スピリチュアルな食事はエネルギー|食べる必要がなくなっていく?! をご覧ください。
最後に:毎日同じものを食べる人の性格
飽きる飽きないの違いが人それぞれあり、両方ある大切さを知っていただく内容でした。
私達ほとんどは生きるために食べていませんので、現在の主体は欲であり、求めているのは刺激、快楽、利益認識だと思います。
こればかりに偏ると主体性がなくなり、欲に飲み込まれて自制がなくなり、健康を害する危険性もあります。
飽きた時にはぜひ飽きないものを探してみてください。
飽きない時には飽きることの大切さを忘れないようにされてみてください。
環境が変われば、季節が変われば、天気が違えば、状態や状況が違えば、食べるものも変わっていきます。
肉体の安定も刺激もどちらも大切なものですので、主体的に利益を作り、認め、さらにバランスを図るために、飽きる飽きないのサインを活用していきましょう。
日本にいられる大きな恩恵が食事かと思いますので、現状の心身内部の静かなお寺に、束の間のライブハウスを入れ込め、楽しい遊びを作られると面白いかもしれません。
これをラーメンと言うようです。
「ライブコンサートが始まるって」
これを外食と言うようです。
より健康的で快活な食生活が促進される一助となれば幸いです。
ありがとうございました。
『心理とスピリチュアルの学び場』
誰しもに人生を変える機会と選択があると信じています。 著名な心理セラピストとして知られる、西澤裕倖(にしざわひろゆき)先生プロデュース。
著名な心理セラピストとして知られる、西澤裕倖(にしざわひろゆき)先生プロデュース。PR:株式会社Central&Mission
※これは長期的に本気で変わりたい方専用です。