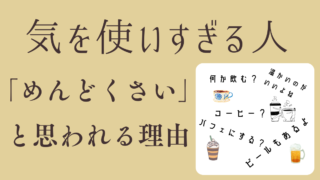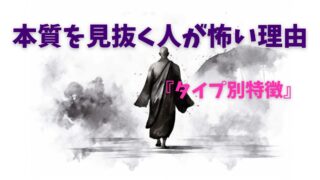【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ぜひおすすめしたい」と感じたのでご紹介です。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作ってもらえます
「なんでこんなにわかるの?」と思えるほど的確で、わかりやすく言語化してくださり、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください
「私、結婚して、子供も生まれて、幸せ過ぎてしょうがないんです」
「ふ~ん、で?」
朗報の返答はこんなもんが妥当でしょう。
人の幸せを喜べない…喜ぶ必要はあるのでしょうか?
私達人間は自分の喜びに興味がある生物。納得や満足の利益をもたらしてくれる存在には興味ありますが、それ以外に全くないのは自然なさまかもしれません。
「人の幸せを喜べないことは特段おかしくない」
しかし、「人の幸せを認識できないと自分のためにはならない」という真相が潜みます。
そこで、「人の幸せを喜べないからなんなのか?」の理解をここで深めていかれてください。
- 人の幸せを喜べないのはなぜ?
- 喜べないから幸せにならないの?
- 喜びたい場合の方法は?
これらを紐解き、「他人の幸せを喜ぶ必要はないけれど、喜ぶのは自分のために大切なんだ」と知っていただく内容となっております。
心理による自己理解によって、喜びを自分のために作る一助となれば幸いです。
Contents
人の幸せを喜べない人は幸せにならないのか?

人の幸せを喜ぶとは?
他人の幸せ、純忠満帆で生活に余裕もあり、仕事も才能を活かして成功。
「だからどうした」
捻くれた私はこう思っていた時があります。グミをクチャクチャしながら。
ですが、アフリカの貧困地域の人々が切磋琢磨して、みんなで協力し合って、他国のサポートを受けながら井戸を作り、地雷を撤去した話を聞くと、「ワーイワーイ」とグミを口から出しながら喜びます。
「人の幸せは自分からの距離感や、死に物狂いの頑張りがあるか否かにて喜ぶかどうかが決まるのかな?」と当時は思っていました。
自分との距離感。日本からアフリカという距離ではなく、自分の思考や心の在り方との距離感です。
自分と似ている(理解・共感・同情できる)人の幸せほど喜べる。似ていない人の幸せほど興味がない。
親友の幸せは喜び、上っ面の友達ほど他人より距離が遠いので興味がない。
都度状態や状況は移り変わるため、誰の幸せを喜び、誰の幸せを喜ばないかは現状や幸せの類次第でコロコロ変わります。
捻くれた私を例にするのはあれですが、私は幼い頃からインドに行って貧しい人達を救済する夢を持っていました。
いざインドに行った時、夢は散りっちりに砕かれ、「助けるかっ、ボケぇい」とマザーテレサハウスで叫んだもんです。
自分との距離が近いと思っていた空想が現実となった時、目の前の人達と距離がかけ離れていたことへの気づき、落胆、失望、喪失などなど、いろいろありました。
勝手なボランティア精神はあくまで自分が納得するためだった、という気づきと共に人の幸せを喜ぶことを投げました。
ですが数年後、再度インドへ訪れた際には、全く別の形でボランティアをさせてもらい、現地の人々が喜ぶことのとんでもない嬉しさを体感しました。
この時間差にあったのは私の変化であり、紛れもない余裕がありました。
人の幸せを喜ぶのは自分との距離感が近い人。心や精神に余裕があれば自然に喜ぶと考えられます。
理解や共感や同情できる距離感の近い相手であれば、自然と喜べるのが他人の幸せ(上述の私の例では、死に物狂いで努力する人=頑張りを評価する価値観の私は頑張る人の幸せを喜べる)という考え方です。
※不幸を喜ぶ心理は、人の不幸を喜ぶ心理にてわかる精神性「本当は誰しも喜んでる?」をどうぞ。
人の幸せを喜べないとは?
人の幸せを喜ぶには心の余裕が大切だと思います。余裕がなくとも、距離感が近ければ近いほどに喜べます。
距離が遠ければ遠いほどに喜べません。喜ぶ理由がないからです。
例えば、「私は結婚したいんだ、どうしても結婚したい」と思う人がいて、隣には、「私も結婚したい。来年には結婚予定なんだ」と言う人がいます。
前者は願望があり、同時に欠乏感を抱くかもしれません。
「今結婚していない私」を願望する度にまじまじと認識し、非リアリティの現実から欠乏感を抱くと、結婚したい願いは現状の本人から最も離れます。
後者は未だリアルではなく予定として結婚予想していますが、相手もいて、お互いの約束も交わしていることから、「結婚している私」をリアルに認識します。
ここで両者の同僚の椚田さんがこの度結婚です。
前者は自分との距離感が遠い人の朗報となり、興味なし、喜べない。
後者は結婚した人を目の前にして、「自分もこうなるんだ」と空想から現実味を味わえるので、椚田さんが幸せであればあるほど、自分を張本人かの如く投影して喜びます。
前者のように余裕がなければ、自分のことしか考えていないかもしれず、人の幸せを喜ぶことは困難で、距離感が近くても他人の喜びに着眼しているわけではなかったりします。
人の幸せを喜べないとは、その人との距離感が遠いか、自分が幸せでなければ当然かもしれません。
人の幸せを喜べない人は幸せにならないのか
自分が幸せでなければ他人の幸せを喜ぶ理由が見出しにくくなります。心に余裕があれば自然と人の幸せを喜びます。
喜べないのは自分のためにならないから。喜ぶ理由や意味がわからない(またはない)状態です。
喜ぶためには理由が必要で、他人の幸せをちゃんと見ているのかどうかの認識が大切です。
相手をしっかり知ると、相手との距離感を自ら近づけるために喜べます。
距離感を近づけたいと思える相手でなければ喜ぶ理由がないので、あとは心に余裕があるかどうかで喜べるかどうかが変わります。
忘れてはならないのは、喜ぶかどうかは本人が決めている、自分のために喜んでいることです。
喜びたい人は進んで相手を知り、何が幸せか知り、距離感を自ら近づけようとします。
心に余裕がある人は自分だけを認識する状態ではなくなり、他者も自分と同じように認識します。無意識に距離感を近づける在り方があり、自然と人の幸せを喜びます。
「人の幸せを喜べない人は幸せにならない」ということはなく、「人の幸せを喜ばない人は幸せになる機会を使用しない」と考えられます。
※人の幸せが嫌いな真相理解は、【むかつく、嫉妬、嫌い】幸せそうな人への反応が表す大切なこと をどうぞ。
人の幸せを喜べない人の心理
人の幸せを喜べない人の心理
喜ぶ理由を見出しにくい状態には、幾つかの心理があります。
- 自己評価が低い(自己肯定しない)
- 他者からの肯定を求める(承認欲求が強い)
- 他人に興味がない(自己愛が強い)
- 成長意志が乏しい
- 他律ぎみ
- 認識力に偏りがある
幸せの定義は人それぞれで、嬉しくて歓びがあれば幸せに感じる人もいます。辛くてもやりがいや生きがいを感じる人は幸せだったりします。
千差万別に幸せがあり、共通しているのは、「自ら見出し・作り・育む」です。
人の幸せを喜べない人の幸せ作りに関係する心理に、成長意志の乏しさ、認識の偏りがあります。
1、成長意志の乏しさは幸せを喜べなくなる
他人とはいわば未知の存在で、同じものを見ても他人が見ている色を理解できないほど認識は全くわかりません。人の幸せがどう喜ばしいのかは、「自分が喜びたい」と思うか、「この人の喜んでいる状態を知りたい」と思う必要があります。
他人の幸せを喜ぶ際には、「自分のために喜ぶ」「この人を自分と同じように認識する(距離感を近づける)」という、自らを自らで喜ばそうとする欲や、喜びを自ら見出す作り出しが大切です。
欲と作り出し(創作)が加わることは、自らの意志を表し、自らを変化させて成長させる意志となります。
他人の認識に向かって距離感を使づけようとすることで、幸せをその人目線で感じ取り、理解や共感や同情できる可能性(喜ぶ理由や動機)が出て来ます。
「私が幸せになりたいの!」と我欲が出て来ると、相手の幸せを感じ取るのではなく、「幸せ感だけが欲しい、私のために」と、他者を利用して自らが幸せを感じようとする別物になりかねず、そこには創作がないので成長意志がないとわかります。
成長意志があればあるほどに人の幸せを喜ぶ理由を自ら見出せます。成長意志が乏しいと、喜ぶ理由がないままになり、喜べなくなります。
※人の幸せを許せない心理は、【本当は憎んでいない】他人の幸せや得を許せない心理と改善ポイント をどうぞ。
2、認識の偏りは幸せを喜べなくなる
もう一つの心理は認識の偏りです。
誰か友人や家族などが幸せを祭っている時、幸せの当事者でなければ何がどのように、どれほど、どんな感じで幸せなのかわかりません。
距離感が近ければ、認識や価値観、思想や人間性が近いので、他人に自分を投影することで自分が幸せであるかのように祭り喜ぶことができます。
友人でも家族でも現状の自分との距離が遠ければ、投影する動機も意味もありません。違和感になって喜ぶのが苦しくなります。
他人の幸せを喜ぶことは、如何に他人目線で物事を見て、考えて、感じ、立場になって思い、抱き、想うかを知ることを要します。
人の幸せを喜ぼうとする以上に、どれだけ相手に自分を投影できるかが喜ぶポイントになります。
いわゆる、投影する自分を明確に持った上で、どれほど他者の中に入り込んで未知の認識を理解するか。
自己認識力(他者認識力)の育み=自分を知り、他人を知ろうとすること。
自己認識の育みがないと、自分を知ったと思い込んだり、物事を決め付けることも起き、自己評価が低く、承認欲求にて肯定を求めたり、比較して優越感を求める他律の在り方が表れます。
すると、幸せの定義を偏って認識する可能性もあり、他の価値観にある幸せに対しても、「どうせ努力なしの他力でしょ」「私だったらこうすればもっと幸せだな」「俺だったらそれ微妙、こっちの方が良いな」と幸せへの同感や共感がなくなり、喜びを感じにくくなります。
※幸せになれない人の特徴的行為は、【四次元ごもり】幸せになれない人の共通点3選&スピリチュアルな捉え方 をご覧ください。
人の幸せを喜べない時の改善方法
人の幸せを喜べない時に確認したいこと
「人が幸せだから喜ぶ」のではなく、喜ぼうとするかどうかによって、人の幸せを喜ぶということがわかります。
他人の幸せが嬉しくなければ嬉しくない。良いも悪いもありませんのでシンプルです。
ポイントとなるのが、「幸せを喜べないと何か不利益ですか?」という自問です。
周囲の反応を気にしたり、喜べないことに自己嫌悪になる場合には、他律の心理が表れます。
この場合、人の幸せを喜ぶこと以上に、自律を育むことが大切になります。
喜べないことに何も苦しみや違和感がなければ、既に自律があり、自らを自らに従わせ、ルールを自ら作っているため、喜べないことが自分らしさとなり、不利益になりません。
人の幸せを喜べない時に確認したいのは、自分が喜びたいと思うか否かの意見です。
「喜びたい」と思う場合には、改善方法がありますのでご覧ください。
人の幸せが喜べない時は、成長意識を持つ
自らが自らを客観視するために、自らが自らを喜ばそうとする思いや気持ちを持ちます。
自分という存在にズブッと埋もれるのではなく、少し離れるように介入しすぎない意識が大切です。
便利な環境から少し不便な環境にするイメージです。
安泰や他律や倦怠は人の変化を拒みます。
成長とは内なる認識を変えることでの育み。常に変化しようとする意識を絶やさないためにも、普段の生活に新しいことを組み込み、挑戦や乗り越えること、自分をさらけ出してみる己との戦いも時に大切です。
自律と自分の客観視によって、人の幸せを喜ぶようになります。
成長への意識が生まれ、自らを高める行為や経験が、人の幸せを喜ぶか否かの選択を明確にさせます。
※成長にて喜びを広げる詳細は、人として成長するために必要なことは知ること|事実は常に裸を見せる をご覧ください。
人の幸せが喜べない時は、人を喜ばせる
人を喜ばせるチャレンジをすると、幸せを喜べるようになります。
他者の目線や立場にて物事を認識する力を育むと、人を喜ばせることの難しさ、他人の千差万別度合、他へのフォーカスの軽薄度がはっきりわかります。
すると自己認識が高まります。
「相手は何が嬉しいのか、何を喜ぶのか、何に心地良くなり、納得し、満足するか」
お世辞を抜きに反応してもらうことで、学びとなり成長となり、認識力の育みによって人の幸せを喜ぶ理由や意味がわかるようになります。
人の幸せが喜べない人は幸せになる まとめ
ここでの核となるのは、「人の幸せをあえて喜ぶ必要なんてない」という考え方です。
喜べなければそれが自分にとっての自然ですので、喜べない自分の内情や認識を知ることが自分のためになります。
喜べない現状によって、より自己理解を深め、より喜びに対する認識が深まると、喜びを自ら作る意識が高まります。
人の幸せに喜べないことを活用して育むと、それこそ幸せになります。
喜べないからには何かしら理由があり、喜ぶからには何かしら理由があります。
理由は、「自分のため」に繋がっているのが私達人間です。
- 友人の笑顔は自分のため
- 恋人が喜ぶと自分の喜び
- 奥さんが嬉しいと自分の楽しみ
- 人を救済すると自分の納得
- 救済された人が喜ぶと自分のいきがい
- ‥‥
喜びたい人は喜びます、それが自分のためになります。
喜べない人は喜びません、それが自然です。
喜べないことを活用して、認識を広げると喜ぶ理由がわかり、選択できます。
喜べないことを活用して、喜びたいと思う人を増やせるようになるのが、ここでの内容です。
喜びたい(理解できる、共感したい、同情したい)と思える人を増やすと起きるのは、自分が喜ぶ機会が増えることです。
幸せになる機会を自ら育み作ると、さらなる幸せを見出すことと思います。
選択や自由度は紛れもなく幸せになる行為。満たされて余裕ができればできるほど、嫌でも人の幸せを喜ぶようになっていたりします。
そんな時を楽しみながら成長されると、良きかなと思います。
人の幸せに対する喜びは幸せを左右しません。幸せを作り出す自分が常に喜ぶかどうかの選択肢を持つことを、今一度確認する内容であることを願い、終了します。
最後までありがとうございました。
【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ピン!」と来た方はぜひお試しください。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作成してもらえます
的確にわかりやすく言語化してくださるため、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください