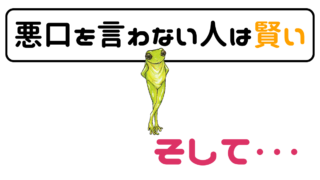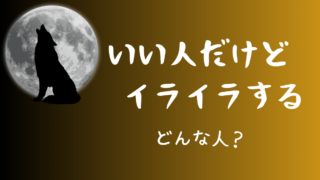【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ぜひおすすめしたい」と感じたのでご紹介です。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作ってもらえます
「なんでこんなにわかるの?」と思えるほど的確で、わかりやすく言語化してくださり、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください
職場という集団帰属地での嫌いな人、関わりたくないものです。
人それぞれに関わりの対処や対応を工夫し、嫌いな人と話さないように無視することもあると思います。
私自身、会社員だった時にはなるべく無視していました。
しかし、話さないように無視すると自分のためにはならないことに気づきました。
ここでは、ご自身のためになる嫌いな人の対応として、話さないことの意味と対応策をお伝えします。
話さないで無視すると起きることも含め、人間の内部理解をご覧ください。
嫌いな人との関わりを見つめ直し、自らを大切にするための対応策がお役立ちできれば幸いです。
Contents
職場の嫌いな人 話さない対応

職場の嫌いな人とは
嫌いな人がプライベートの自由空間ではなく、職場という仕事空間にいると、同じ嫌いでも意味が変わります。
仕事にて同じ時間・空間をシェアしながら同じ業務をこなし、社長のために働いてお金という対価をもらいます。
職場にはあらゆる縛りがあり、嫌いな人と同じ時間・空間・目的を共有する必要性が出てきます。
職場に嫌いな人がいることは、自分の時間と空間と目的に抵抗を作る。職場での自分らしさの障害となる存在です。
「自分らしくありたい」「心地良くありたい」「納得できる時間を過ごしたい」と思えば思うほどに、邪魔な存在となる人です。
不利益を与える人は嫌いな人になる
このような人々が居ると嫌いにならざるを得ません。
- 仕事を真面目にしない
- 仕事していないのに評価される
- 自分の地位を脅かす
- 自分の願望に抵抗となる
- 人間性が合わない
- 存在がモチベーションを下げる
- 自分勝手で迷惑をかける
- ‥‥
これらの人々に共通することはありません。
人を嫌う側の心理には共通点があります。
職場で嫌いな人とは、職場での自分にとって不利益となる存在です。
嫌いな人に話さないとどうなる?
攻撃的な人はいじめ、防御的な人は話さない対応が基本スタンスとしてあります。
人間の本能的な性質であり自然な動き。身をまかせた状態での対応の形です。
私が会社員の時に嫌いな人がおり、話さないという防御対応をしていましたが、必ず起きるのが嫌な覚悟でした。
話さないように距離を離そうとすればするほど、自ら嫌いな人のことを頭の中にボンボン作ります。
大好きな人かの如く嫌いな人で頭が埋め尽くされ、いつの日か必ず関わらなければならない時がやってきます。
「話しかけないと、あー、嫌だー、何でだよ、他の人にお願いしようかな、子供かよ、なんだ私って、こんな弱かったっけ?」と自問自答がグルグルグル。
とても嫌な覚悟をして、「よしっ!あ、あのー、この書類なんですが。。。」
疲れ、ストレスを作り、あえて疲れたいのかと思うほどに全て自分で作る一連が起きます。
話さないことで一時的に対処はできるのですが、嫌なことを蓄積するように疲れとストレスを一斉に作る時がやってきます。
職場で人を嫌うと周囲に迷惑がかかる
嫌うことで嫌われる人も距離を取ります。
何も言わずとも雰囲気や感覚的に嫌われていることはわかり、嫌われれば同じように嫌い、距離を取り合います。
問題はそれが職場であるため、周囲に迷惑が掛かってしまいます。
集団意識の欠損、崩壊、コミュニケーションのなさによる連携力の低さ、モチベーション低下、横のつながりと流れに障害を作り、業務効率低下、業績ダウン、顧客満足低下。
※みんなが一人を嫌う場合には業務効率が上がる人間心理の怖さも有
話さないようにする様は目立つ
上司は部下を評価するのも仕事ですので、仕事量や質だけでなく、会社側の目線や立場での業務成果、姿勢、認識を見ます。
個人経営者でなければ一人で業務をこなす人は少ないので、大半は他との連携や繋がり、管理力やリーダーシップ、調和や協力が重要になり、評価査定にはどうしても気になる点が浮き彫りになります。
「あの人にだけ全く関わらないな」
全員を嫌い、誰にも話さないのであれば全く別の見られ方になりますが、単数を嫌って話さないようにすると異様に目立ちます。
評価を下げられる可能性があります。
話さない対応は一時の蜜で終わる
嫌いな人に話さないメリットは確実にあります。一時的に関わらない時間を作れることです。
しかし、それ以外はデメリットとなり、一時凌ぎにて問題から逃避するのが話さない、無視する対処です。
※職場で嫌われる人の特徴と末路については、職場の嫌われ者の特徴と末路│孤立の先にある末路に危険性と改善をご覧ください。
職場の嫌いな人に話さない:メリット&デメリット
話さないことでのメリットとデメリットを整理します。
- 一時的なストレス解放
- 共通認識の仲間との結託
- 個(独立)への認識向上
- 嫌な覚悟の時がやって来る(自らを自らで苦しめる)
- 嫌いな人を意識することでの脳内汚染(整理支障)
- 思考過多、認識情報多による疲労作り
- イライラ、気を使い、周囲への配慮増加にてストレス
- 集団意識の欠損(社会的自立の後退)
- 周囲伝播による不調和・違和感拡散
- 組織としての調和崩壊
- 業務効率低下、実績ダウンの可能性を高める
- 評価査定ダウンの可能性を高める
- 集団としてのモチベーション低下
職場では話さない無口な人もおり、仕事は仕事と割り切って業務に向かう人もいるので、話さないことは個々の業務効率や能力向上にもなります。
嫌いな人を認識から一切撤廃して、まるで存在しないかのように無関心。それを自然とできるのであれば効果的な策で、業務への支障もなくなります(業務効率アップの可能性すら有)。
良きも悪しきも共にあるので、人それぞれに大切な対応となる方法です。
着目したいのは、嫌いな人がいることでどれほど職場での自分らしさに抵抗が作られるかです。
対応でポイントとなるのは、嫌いな人の存在から自分らしい対応を見出す。嫌いな人と自分を理解することが大切です。
※職場で話さない人自身の向上対応は、職場で必要以上に話さないと起きる不思議│静かなのに目立つってどういうことー をどうぞ。
職場の嫌いな人 話さない以外の対応策
職場での嫌いな人の対応策ポイント
話さないのは人によってとても大切な手です。
ただ、身をまかせた本能的な対処であるため、改善や向上の余地があります。
話さないことは自己防衛の在り方を優先する人間性でもあるので、自分に見合った対応策を考えるのが最も効果的。自分に見合うかどうかが重要です。
相手は嫌いな人ですので、無理矢理話したり我慢したり自らを変えるのではなく、相手と自分の不調和を知ることが必要です。
嫌いは嫌いとして認め、何が嫌いで、何が不利益になって、どうして嫌いになるかの自分の認識を知ると、心地良く職場のためにも自分のためにもなる対応ができるようになります。
嫌いになる理由と不利益な点を確認
不利益、自分にとっての不納得や不満足、見たくない認めたくない知りたくない味わいたくない拒否の元。
自分らしさを表現する状態への抵抗、自尊を汚す言動・行為をする人は自然と嫌いになります。
「職場では仕事をするんです」という人は、真面目に仕事しない人を嫌います。
「職場では人間関係が重要でしょ」という人は、コミュニケーションをとらず、話さない人を嫌います。
人それぞれに不利益があり、自分を護る意識によって人を嫌いになります。
人を嫌いになるのは自己愛と自己防衛意識
嫌いな人に対する認識は、大きく二つあります。
- 自己愛と支配欲からの攻撃性を含めた嫌い
- 自己愛と自己防衛からの防御性を含めた嫌い
「この人嫌い、辞めさせたい」か、
「この人怖いから嫌だ、関わらないでほしい」
どうして嫌いで、何が不利益になっているかの、自分と相手の関わりを見極めることが対応時に大切な行為となります。
自分に見合った対応策を探る
嫌いな人に対して自然と表れる行動があります。
- いじめる攻撃性(排他、抑圧)
- 話さない防御性(拒否)
- 逃げる逃避性(転職、回避)
- 無関心の放任性(個)
- 統制の社会性(合理化)
- 歪曲の虚偽性(仮面)
- 慈悲の寛容性(勇気、自己認識)
大きくはこれらにて自然な様が表れ、人それぞれの策を組み込めて千差万別の対応が出来上がります。
話さない防御性には身を守る意識と共に、嫌いな人と関わることでの周囲からの飛び火や副作用への防衛もあり、安泰や保身への欲求がある人もいます。
相手を嫌いな理由と、自分自身の理解を深めることで、自分に見合った対応策が表れます。
話さない対応をする場合、如何に嫌いな人との距離感を取るかが重要なポイントになります。
※嫌いな人との距離感を作る心理は、【嫌いな人なのに?!】あえて近づき話しかける心理に重要な人間味 をどうぞ。
職場での嫌いな人への距離感を保つ例
私が働いていた職場での対応様子をご覧ください。
私と上司以外は全員女性の職場でした。
驚くほど誰しもに嫌いな人がおり、派閥もできている部署ですが、話さない距離感をそれぞれが作って対応します。
仕事上では仕事の話は普通にして、業務的に普通に関わり、挨拶を普通にして、普通に帰っていきます。
嫌いな人の嫌いな部分をちゃんと認識しているため、そこには何があっても触れず、触れるほど怒りや苦しみが出てきた際には上司や私に相談します。
自分にとって不利益になるであろう相手の部分を把握することで、嫌いな人の嫌いな部分を引き出さないように関わり、業務への支障は一切なく仕事として嫌いな人と関わります。
距離感を作るために同僚と協力したり上司を使ったりと、「自分のため」という意識を忘れずに対処・対応をする職場でした。
一人一人に自己理解と自己管理があり、嫌いな人全般を嫌うのではなく、嫌いな部分のみを嫌う認識をしています。
そのため、人をフラットに見て上下には分けません。
変に感情移入させずに仕事し、嫌いな人とも仕事として切り分けて関わり、プライベートな話は一切なし。
スッキリと関わりに線を引きながら、相手の嫌いな部分、自分がされたくない部分を把握して関わり、嫌いな人にフォーカスしない。
そんな職場でした。
話さない、無視以上に、自分のために距離感を保つ意識が大切
自らを知るように嫌いな人の嫌いな部分、自らが不利益を被る点を明確にすると、距離感を保ちやすくなり、疲労もストレスも溜めずに嫌いな人を対応できます。
嫌いであれば嫌いなのであえて話したり話さないようにする必要はなく、相手にフォーカスを強めずに、自らを主体に相手を見て、関わり方を線引きすることが大切です。
話さずに無視する対応は無意識に相手に干渉してしまい、自らを我慢させたり、相手が気になって距離を放とうと逆に意識しかねません。
あらゆる主体を「自分のため」にして、自らの認識をはっきりさせて、自ら距離感を作り保つ意識が疲れもストレスも違和感もなくし、心晴れ晴れと興味を持たずに業務として線引きした関わりとなります。
※無関心になる対処法は、【モロッコでの体験理解】嫌いな人に無関心になる方法は自己内部にあった をどうぞ。
嫌いな人の対応は話さずに距離を保つ
嫌い、邪魔、合わない、自分らしくなれないため、話さずに距離感を保つことが対応策になります。
話さないのが自然な状態になるよう、自ら保ちます。
方法は嫌いな人の嫌いな部分に飲み込まれず、人を上下区分けする認識を撤廃します。
誰に対してもフラットな認識を持ち、他者と自己を理解することで距離感の創作を執り行います。
フラットにすることは、人を上下に分けて、自分に不利益か利益かで見ない意味です。
不利益であれば気づかぬ内に嫌いな人を下、それ以外を上に見ようとするのが防衛意識です。
みんなをフラットにして、個々の認識として「この人は嫌い」と自由に思います。
嫌いであることをなくしたり、嫌いな気持ちを抑圧しないことがフラットでもあります。
例えば、挨拶であれば職場で関わる人には全員に挨拶します。一人にだけ挨拶しないとなれば相手に飲み込まれている意味になりますので、相手にフォーカスを強めないようにします。
※嫌いな人が去っていくスピリチュアルな件は、【4つの方法】嫌いな人が自然と去っていくスピリチュアルな仕組み をどうぞ。
話したくない相手を知り、話したくない自分を知る
距離感を保つためには、嫌いな人との間にある隔たりではなく、自分の中にある「離れたい」という気持ちをコントロールします。
そのために、「この人嫌い、最悪だ、絶対に話したくない」という自分の意見に対して、「なんで嫌いなの?」の真意を把握します。
「嫌いなものは嫌い、では何が嫌いなの?」の答えをしっかり把握すると、距離感を自ら作り、保つことができます。
顔が、化粧が、性格が、仕事への向き合い方が、人間性が、お菓子食べた手で共有PC使うから、挨拶が押し付けがましいから…などを明確にし、「私はこの人の偉そうな態度が合わないから嫌い」などと理由を把握します。
距離感に大切なことは、「嫌いな人の嫌いな部分=自分にとって不利益な部分」を知り、関わりたくない、話したくないという気持ちをコントロールすることです。
※嫌いな人への拒絶反応については、【最上級のサイン】嫌いな人への拒絶反応に潜む意味と対処法(解説by体験談)をどうぞ。
職場での嫌いな人と話さない まとめ
対応策として話さないことは大切です。
しかし、本能的に身をまかせるように話さない場合には、感情や自分のみを主張した状態そのままに、嫌悪を際立たせるための行為になりかねません。
誰しも嫌いな人がいるものですので、嫌いなのは嫌いで決まりです。あとは自己理解を深めるように嫌いの細部に入り、相手の嫌いな点、自分の不利益になる点を知ります。
対応ポイントは、「職場での自分」を明確にすることです。
なんのために職場にいるのか、何をしたいのか、どうありたいのか、職場をどうしていきたいのかの意見をこの機会にはっきりさせてしまいましょう。
仕事とは与えられたことをするだけではないので自らの意志と意見があり、仕事するに適した環境を作ったり、周囲と工夫し合いながらさまざまなことを創作できる場です。もちろん創作しないこともできる場です。
職場の自分を明確にし、嫌いな人とは確実な線を引き、飲み込まれずに自らの認識を律すると、自らを苦しめない対応が生み出されます。
話さないこと以上に自らのためとなる距離感を保ち、嫌いな人は嫌い、仕事は仕事、嫌いな人がいることでの影響なし。そんな具合に対応をされてみてください。
我慢やストレスを溜めず、気楽な関わりとなれば幸いです。
それでは、職場での嫌いな人への対応についてのお話を終了します。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ピン!」と来た方はぜひお試しください。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作成してもらえます
的確にわかりやすく言語化してくださるため、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください