優しい人の中には中身のない人もいれば、温かい人もおり、フリをしている人もいます。
そして冷たい人もいます。
相手に嫌な思いをさせない気使い、賞賛して喜びを与える配慮、礼儀がある。
繋がりを求める近さもありながら、なんだか心の距離を感じやすい。
心意が表に出にくく、周囲からはクールな評価を持たれやすい。
そんな方はふとした瞬間に冷めるなど、太刀筋の鋭さが故の人間模様、そこに潜むクールネスの真意が見られます。
ここでは、優しさと冷たさが一緒くたになっている内情を深掘りし、一見距離感に見えるものは「実は壁ではない?!」という見方をお伝えします。
- 優しいけれども冷たい理由を知りたい
- 冷たい人の優しさについて考えたい
ルール従順と個性を組み合わせた色彩見える優しさはピンクとブルー、そんなイメージかもしれません。
心の理解を深める内容、一つの考え方としてご参考になれば幸いです。
Youtubeもありますので、ぜひご覧ください。
優しいけれども冷たい人の特徴
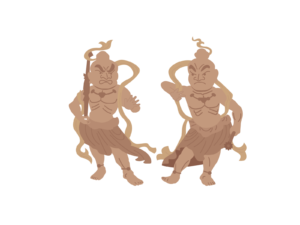
ここでお伝えする主人公は、一見優しそうに見えて実は人を利用する根が冷たい人や、自己利益を得るために仮面を使うテイカーのことではありません。
静かに全体を見据え、突然心を遮断するなど、クールな人でありながら相手を想う心も持っている人、そんな優しい人のこと。
優しいけれども冷たい人の特徴
1,人の見極めが大前提
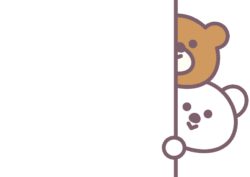
人と関わる際は評価・判断ファースト、まず相手を見極めます。
楽天的に何も考えない、ではなく。気づけば「ジー」と見ている。
繊細な心を持っており、対象に危険性があるかどうかを見つめます。
「むむ、こやつ礼儀を知らないな」と少しでも不穏を認識すれば、一歩下がっていつでも防衛できるスタンスを取ります。
しかし、そのようにしていることは明かさず、気づかれないように潜水下で行うのが特徴的です。
2,感情表現が少ないようで多い
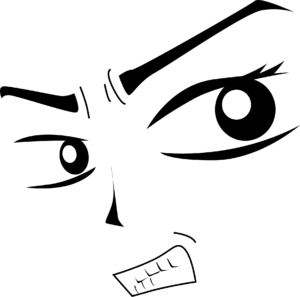
「やった!ニコニコ」「くそ!イライラ」など、ストレートな表出ではありません。
感情が生まれるとゾゾゾと心に熱が入る体感をまずは内側で感じ、その後に表出するかどうか選択する順序があります。
大きな好奇心が湧けば喜びが顔から溢れそう、それは真顔で目と鼻と耳の穴が開く、「な、なんか堪えてるの?」と思える顔をします。
パァっと溢れそうであり、一般的なわかりやすい表現ではないけれども喜怒哀楽を隠しません。
何言ってるかわからない赤ちゃん、「パぺプププ、ぺ?」
けれどもお母さんはわかるように、初見では感情がわかりにくくても、付き合いが長い人はよくわかります。
3,感情豊かだが棒読みに思われやすい

表現があまり得意ではありません。
ただ、感情豊かで、喜びやすい、怒りやすい、傷つきやすい、好奇を抱きやすいなど、感受性の高さや感性豊かな人。
「うわー、やったー、本当に嬉しい、ありがとう」
「なんか棒読み的な…、ほんとに思ってる?」と見られやすく、気持ちを表していると言うよりは、「言葉を発している」という印象になりがち。
が、気持ちを入れようとする意図があります。
興味がない人の場合、気持ちを入れようとする意図がないので本当に棒読みになります。
※利害関係のある間柄、例えば職場の上司などは、気持ちを入れる意図はないけれども演技で大げさに喜んだりする
4,深い関係性、親密なコミュニケーションが苦手
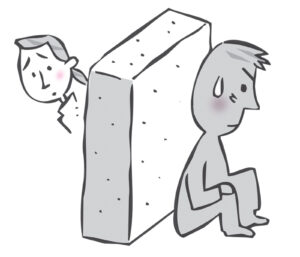
これを課題だと自覚している人ほど優しい人だと考えられます。
家族やカップル、パートナーなど、身近な人にほど親密さの表しが苦手です。
心を表したい意図と、剥き出しにすることへの恐れ(トラウマ、依存懸念など)が葛藤し、自己内部で闘いが起こることも。
内面を理解してくれるまで仲良くなった人との関わりは、とっても大切にする人です。
5,心を許すと冷たくなる

本人にとっては心を許している、そんな気楽な状態ですが、素っ気なく、感情なく、冷たい印象が増えます。
関わりに慣れが生じると“自己”に認識が偏る癖があり、相手側の認識考慮を忘れたり、無意識の思い込みや決め付けが起きえます。
他者を喜ばす意識がなくなっている可能性もあります。
仲がいいからこそ力みのない安心、緊張のなさがありますが、それが冷たさになるジレンマを抱えることになります。
6,“個”の尊重が強い

個人主義ではなく、個々を尊重し合う人間関係を好みます。
干渉や押し付け、「あぁしなさい、こうしなさい」と言われると、高所の渡りロープを切りたい気分になります。
基本的に不干渉、その人のやり方があれば見守り、それを邪魔しないように合わせたり適応します。
一方、自分の個も尊重してもらいたい気持ちがあります。
7,集団も個人行動も好き
 集団の戯れにも一人行動にも抵抗がありません。
集団の戯れにも一人行動にも抵抗がありません。
時に複数で旅行し、時に一人で海外にも行きます。
ただ、目的なく一人行動することは少なく、常に目的を達成する道筋を行きます。
「なんかわからんけど、あそこ行ってみようかな」はなく。
「アイスランドの自然を味わってみたい」
「バンジージャンプを体験してみる」
「温泉三昧の二泊を味わう」
何かを達成する、得たいものを得るための活動など、それは気楽に楽しむといった感情的なものも含めて、道筋を見る人です。
8,任務遂行能力が高い

目的を定める、道筋が決まるとそこへまっしぐら。
ゴールが見えると辿り着くための邁進力が凄まじく、途中に弊害や障害があってもぶち壊して乗り越え、任務を何が何でも完遂させます。
仕事をまかせたら絶対的な信頼を持てる、なんて人であり、シンプルに個人能力がとても高い特徴でもあります。
右腕として力を発揮しやすい人です。
9,知性が高い
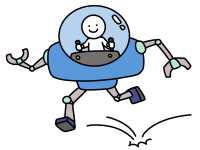
勉強といった学術的な知能かどうかは人それぞれですが、飛び抜けて得意なものがある人。
スポーツの人も、テストの点数が取れる人も、細かい作業が正確な人もいます。
全てに共通して、知性の高さにて自己理解が深く、身体の使い方をよく知っています。
例えば、足の使い方を知っているからサッカーのシュート力が異様に強い、肺の使い方を知っているから持久力に長けている、記憶する方法を知っているから勉強できるなど。
「本当は頭なんてよくないよ、ただテストの点数を取る方法を知ってるんだ」なんて人です。
10,常識的でありながら独自性が強い

優しいけれども冷たい人はとても常識的です。
日本で生育していれば日本人的になり、国民性を表す人柄があります。
忍耐強く、頑張り屋、ルールを大事にして、集団でありながら個人に重きがある。
同調圧力、暗黙の了解を把握し、上司を持ち上げ、部下には少し厳しく。
そしてそれらの常識をクソだとも思っていたりします。
独自性があるために個性、考え方、感じ方を重んじ、自分なりのやり方を大切にします。
ルールに対して、「なんやこれ、意味わからん」と守らない時も多々。
日本人だけど日本人っぽくない、集団も個人も大事だけど、そこにあるエゴや執着(例えば一人でいられないから誰かと一緒にいる、特定の人だけが得するルールなど)に反吐が出ます。
11,他者に迷惑をかけないための心配り

常識を守るのはルールにただ従っているのではなく、心配りです。
他者に迷惑をかけない意識があり、周囲への配慮や礼儀、常識的な振る舞いを大切にします。
集団も個人行動も好きですが、無配慮で害悪な集団の戯れであれば即座にそこから抜けます。
街中で騒いでいる人々を見ると、眉間の皺が絶壁の層のように段々とし、蛇が吐いたゲロを見る目をします。
12,利用できるものは利用するという平等性
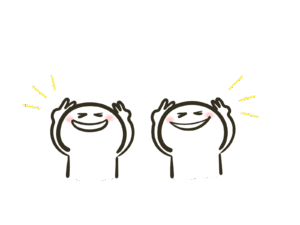
平等や対等を重んじます。
与えられたらお返しする意識があり、もらってばかりだと「申し訳ないな」という気持ちを抱きます。
そのため、奪う人からは奪い返します。
利用してくる人がいれば利用するのが平等であり、「そうくるなら利用してあげる」
例えば、もし日本の制度が国民を利用するスタンスになっているのであれば、利用できるものは何でも利用します。
存分に躊躇なく心置きなく使えるものは使い、その際に妖気的な闇が垣間見えますが、平等性の上では優しさです。
ただ、奪い返す時は何倍にもしてお返しする優しすぎる一面も。
13,自分の意見は控える

自分の意見を言うのは、「相手に害なし」と判断した暁。
そうでなければ意見は言わないため、「どう思う?」と聞かれれば基本的に当たり障りない社交的アンサー、教科書的な発言を使います。
自分の意見が心からのものであり、それに対する反論や批判があると自分の心が傷つくことを知っています。
意見を露わにすることの重さ(リスク)があり、相手の見極めは絶対的にします。
14,無言で時を過ごせる

一切言葉を発さずに自分の時間を過ごせる人。
シーンとしており、「本当に部屋にいる?」と思わせます。
人と一緒にいる際、気を使って話すこともできる。
気を使わなければ一切話さず、気まずさがあっても無言を貫くことができます。
ちなみに、気配を消すこともできます。
15,沈黙が好き
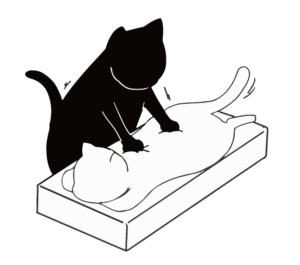
優しいけれども冷たい人は、人に合わせるのも気を使うのも、配慮も礼儀もあります。
なにより対等や平等性を重んじ、フラットな状態や状況を好みます。
それが沈黙。
沈黙を共有できる相手を好みます。
優しさがあるため、ベタベタはしませんが同じ時空にいることを好みます。
同じ部屋にいながらそれぞれが本を読んだり、音楽を聴いたりと好きにするなんてイメージです。
16,人の話を聞く、賛同する
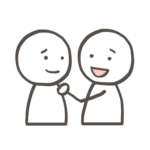
自分のことをあまり話さず、人の話を聞くことが多い人。
相手に合わせるのが上手、賛同するように傾聴するのが上手であるために優しい印象を与えます。
一方、話し始めたらずっと話す人でもあり、自分の興味あることや批判的なことも好きです。
17,忍耐力が忍者レベル

内向性気質があり、一見そう見えませんがとんでもなくエネルギー量が多い人。
身体やエネルギーが強く、それらを『忍耐力』として活かす傾向があります。
耐え忍ぶ力にて内省してエネルギーを昇華し、個人能力に変換し、思考力も高めます。
自己内部でエネルギーを能力にする力があり、内面は自己システムで網羅されており、身体を開くとコンピューターユニットによる電飾七色がそこら中に光ります。
内面の防壁が忍耐と知性によって完璧に構築されており、心を一瞬で閉じることも可能。
興味のない人には間で無関心になる切り替え、「え、あなた誰ですか?」と鋭い刃、相手の急所を一刺しするスナイパースコープ付き。
人の傷つけ方を知っており、何かあれば手を出せないように実力の違いや怖さを一瞬見せてわからせることもできます。
18,リスクマネジメントのリーダー
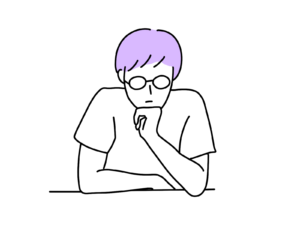
一か所依存を避けて分散させて働く、将来のために居場所を確保、資格をたくさん持つなどリスクマネジメントに長けている特徴です。
不安と恐怖を知性で退けるために、使えるものは使い、できることをできるだけします。
根底に自立している精神も置いており、一人で生きていける準備もあります。
リスク調整のために人脈を新たに広げようとはしない面を持ち、めんどくさがりにもなりますが、閉鎖的ではないためにリスク管理しながら関わる社交性も懐から出します。
19,突然冷める

心が傷つくことへの強い恐れがあると考えられます。
人によっては過去の記憶、トラウマやコンプレックスに起因しており、冷めることで心を護る人もいます。
心の重んじが強く、繊細で感受性が強いために自然と防衛への意識が強くなります。
外面だけでなく中身を見て関わってくる人には仮面や取り繕いではなく親身に関わろうとしますが、何か傷つく懸念があれば咄嗟に心を閉ざそうとする癖のようなものがあります。
その心の在り方を乗り越えようと想える関係があれば、とてつもなく重要な人物です。
以上が、優しいけれども冷たい人の特徴でした。
※期待しない人の優しさについては、他人に期待しない人の冷たい言動11選【真意はいかに?】をご覧ください。
優しいけれども冷たい人の心

優しいけれども冷たい人の心
秘めるもの:誰も踏み入れない神聖な領域

全てのような、宇宙のような、神のみぞ許されたサンクチュアリ。
己以外、誰一人として入れない。
自らがそこに入ることも少ない、しかし実際には常にそこにいる展開領域、平穏で静寂に包まれた絶対性。
優しく冷たい人はここを守っています。
自分のみが踏み入れられる、それでいて門番のように守る。
それだけ大切にしています。
この神聖なる領域を持つ人は、本人の意図関係なく冷たい印象が自然と出ます。
大切なものを知っているからこそ心は優しさを持ち、大切なものを守っているからこそ心は冷たい印象となるものを醸し出します。
本当に冷たいかどうかは全く別のお話。
その心を持っている人には、[優しい+冷たい]が組み合わさった像が映ります。
※本当に優しい人については、【本当に優しい人の正体】レベルが上がっていく“中身のなさ” をご覧ください。
根が冷たいのではない
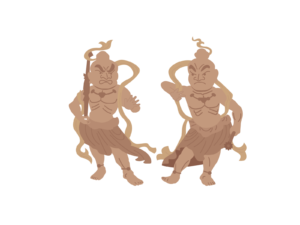
冷たさは防壁の強さ、突然冷める、一瞬で無関心になれる、干渉しない、期待しないなどの言動にて表れます。
心を許して気楽になるほど冷たくなってしまうのも、これに起因していると考えられます。
気楽になるほどに意識は心の在り方に近付くため、潜在的に大切なものとの距離感が近くなります。
大切なものは神聖な領域ですが、物理現実で認識されるのは“個”であり“干渉のない個々の尊重”です。
気楽に心を許せるほど個々に干渉しないことが誠実さとなり、人間関係では冷たさが増えます。
同調しないことが同調であるため、これができるのは自分と同じタイプに限定されます。
ただ、この冷たいと思われる心の在り方があるからこそ優しさがあります。
根が冷たいのではなく、根が優しいからこそ自分を大事にでき、それに合わせた他者を大事にする在り方を見出し、工夫し、磨けます。
根が冷たい人はそもそも他者を考えることが自己利益なくしてできないため、どうしても取り繕いの演技や偽り、平気で嘘をついたり誤魔化したりが顕著になります。
押し付けがましい利益提供やニコニコ、心理的に脳を取り囲む蜜のチラつけや支配など、なんの神聖さもなく、護るものはエゴで歪み汚れた自己愛であるため、違いは明確です。
根は冷たくない、ただ忘れてはならないものがあります。
※根が冷たい人との違いは、【要見分け】優しそうに見えて冷たい人・優しくない人・優しい人 をご覧ください。
優しさの裏側と表側

潜在的か顕在的かは人それぞれですが、神聖な領域が心にある以上、大切にするほど“守る意識”が強まります。
ポイントは、自己愛といった明確な己をストレートに大事にしているのではなく、「自らが入る、在る領域」であること。
領域を守る、穢さないことが自己愛を大事にする動線になっています。
これによって干渉しない、個々を尊重する重んじになり、それが誠実さにもなり、冷たさにもなるという作用。
ここで最も重要だと考えられることがあります。
関わる他者そのものへの尊重もあること。
・冷たい印象は個々の尊重であり、優しさの裏側
・相手そのものの尊重は温かい印象になり、優しさの表側
目の前に調和や協調、深い繋がりを信じる人がいれば、その心の在り方やその人だからこその関わりを敬うことで、相手の尊重と個々の尊重が組み合わさります。
個々人の在り方を干渉せずに尊重できるからこそ、相手側の認識に寄って相手そのものや在り方を尊重できます。
すると冷たさは温かさと交じり、ちょうどいい温度。
ぬるま湯のように、まったり、ゆったり、ゆ~らゆら。
「この気楽、とってもいいですね」というお話です。
※根が優しい人の特徴は、【悪態ついても心は綺麗】根が優しい人の特徴15選+共通点 をご覧ください。
最後に:優しいけれども冷たい人
冷たさは厳しさにもなる欠かせない陰側を担います。
陰陽思想では陰と陽の組み合わせた勾玉に普遍があります。
冷たさだけでは、温かさだけでは成り立たず、どこか崩れが生じるために思考や社会性、ルールで補うことになります。
その補いもまた現実味を作る大切な要素となり、『自分』という紆余曲折、多種多様なカラー、絵具を水に垂らしたグニャグニャを構成していきます。
冷たさも温かさも、冷たさでも温かさでもない空虚も含めて、本物の心、優しさが生まれるのだと思います。
心を許すと冷たくなる場合、ご自身を今一度見つめてみてください。
私たち人間は終わることなくアップグレードでき、常に進歩と向上、退化も含めて成り立つ変化邁進、道行きがあります。
神聖なる領域は誰も踏み入れない。
「誰も踏み入れさせない」ではなく、踏み入れない絶対性。
それを守ることは何かを恐れるのではなく、誓いや覚悟、意志ある心、宇宙との繋がり。
本当の意味での『守る』はとっても深い。
そんな理解が一つのご参考になれば幸いです。
ありがとうございました。

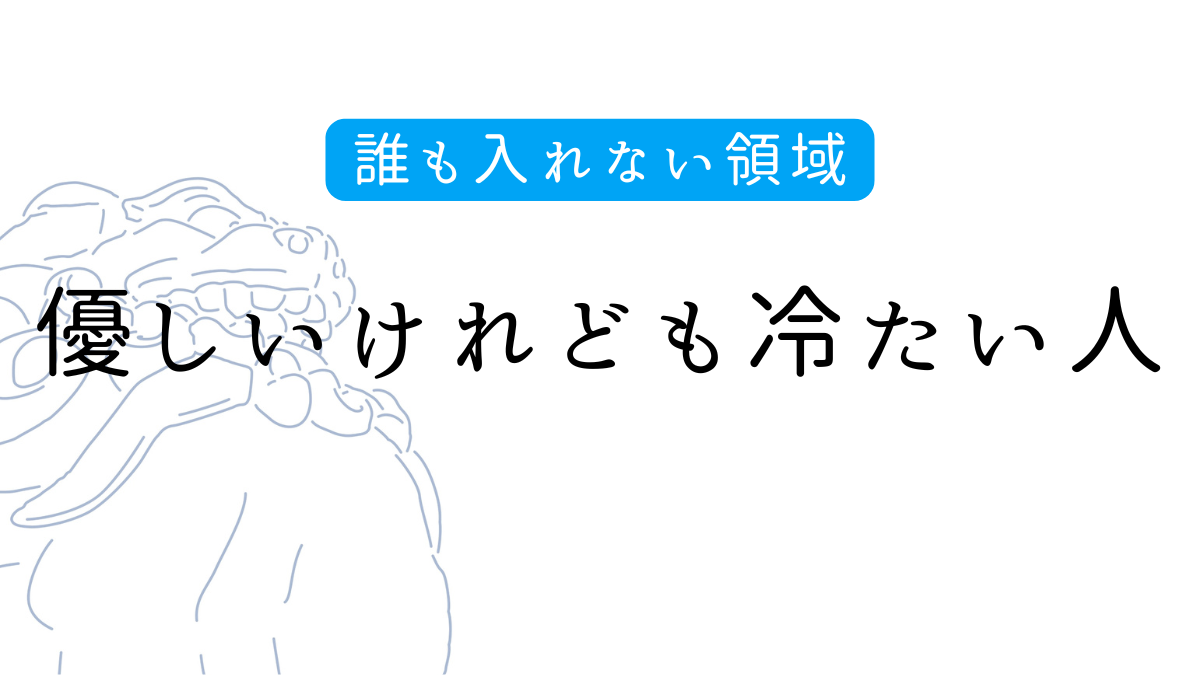




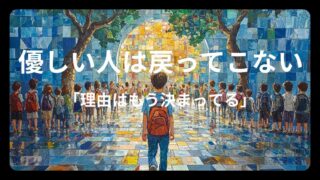




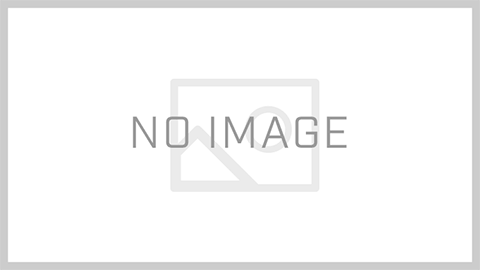
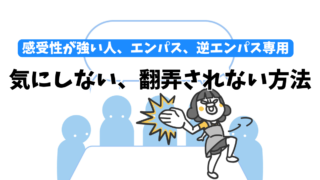




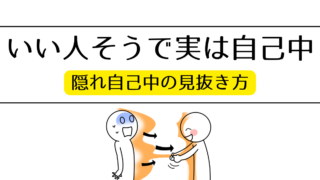
わぁ、北斗さん。このタイミングでこの記事ですか、、、
私にとっては神がかってます。
ありがとうございます。本当に。
ちなみにこの人は、人から誤解されまくりますよね。w
きっと私のことだと思います。
なお、そんな私は、どうしても守りたかったものが壊され、たのか、壊したのか、の出来事があり、「ヘドが出る」と思っていた人格を演じ始めていました。
人の心の理解が進んでおります。いつもありがとうございます。
心の理解促進、本当に何より。
よかったです♪