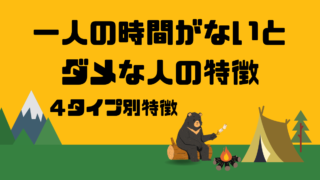【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ぜひおすすめしたい」と感じたのでご紹介です。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作ってもらえます
「なんでこんなにわかるの?」と思えるほど的確で、わかりやすく言語化してくださり、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください
感謝できる人がいれば、できない人もいる。したい人もいれば、したくない人もおり、する人もいれば、しない人もいます。
感謝とはするかしないか?
それとも、できるかできないか?
「あ・り・が・と・う」と音を発することが感謝ではないため、感謝するためには経験や理解が大切になります。
感謝できないことは何かおかしいのではなく、できない理由や原因があります。
ここでは感謝できない人の心理と原因、これらから表れる真意をお伝えします。
- 感謝できない人の心理とは?
- どうして感謝できないの?
- 感謝できない人に大切な理解とは?
感謝できない真相を知っていただき、ご自身をより深く理解する一助となれば幸いです。
心理と原因を知ることで、感謝することの意味や方法が判明しますので、感謝できない真意を見ていきましょう。
感謝できない人の心理
感謝できない人の心理
感謝に必要性があるか否かは本人にしかわかりません。
必要性がない、または必要性を考えない場合には、感謝できない人の心理として自己表現の特徴的なさまがあります。
自己表現がモノクロ。
単調で、色がないと言いますか、とてもシンプルな特徴です。
感謝できない人は自己表現が苦手
モノクロであることには自己表現が苦手な心理が考えられます。
私達人間は脳があって肉体があって心があるので、さまざまな情報を持ち、組み合わせて自分らしさや自己認識をしますが、感謝できない人は混ぜ込めないでどれか一つの単調、それを内側で保持します。
自らの内にあるものを外に出すことが自己表現ですが、外に向けた意識が少なく、創作や創意工夫があまりありません。
思考だったら思考、感覚だったら感覚、感情だったら感情と一つ特化したものに限って自らの世界にこもるイメージで、知性だったら知性、理性だったら理性、感性だったら感性と一つです。
他者側の目線に立った物事の理解や解釈の認識が少ない、または偏っている可能性があります。
感謝できない人は自己認識力に偏りがある
自己認識力とは自らの理解を促す認識のことで、内側の感情や思考、感覚や記憶や意識の内観や内省能力です。
内側があれば外側もあり、自らを客観的に捉える認識や、他者と区分けすることでの認識能力でもあります。
さらに、他者の目線に立って自らを認識することも含まれ、その認識と己のみの認識との合致にて自己認識力の高まりが表れ、内外のバランスにてタイプや傾向も表れます。
感謝できない人は、己のみを対象にした内側の認識力があり、他を含めた認識が乏しい傾向があり、自己認識力に偏りがあります。
内側の認識が強ければ強いほどに、自尊や自負が強すぎたり、自己否定や自己憐憫性が高まったりと極端に心理傾向が表れ、他者の意見を聞かずに頑固・固着したり、謙遜という名の自己防衛や罪悪感意識が強くなります。
共通して、他者の目線に立って物事を考えられないことが起きます。
感謝できない人は内側の自己認識が強く、外側の自己認識が弱いため、殻にこもる(自分の世界に入り込む)。
感謝できない人のパターン
自己認識の内外バランスにて感謝の解釈の違いが表れます。
- 自己認識があり、他者認識がない
- 自己認識がなく、他者認識がある
思考優位か、感覚優位かによって、感謝できないのかしないのかが分かれますので、パターン別に特徴をご覧ください。
①内側の自己認識があり、外側がないパターン
- 思考優位の人
…感謝できない人(感謝とは何かをしっかり理解しないとできない) - 感覚優位の人
…感謝しない人(感謝について考えることもない)
感謝できないとしない人が、思考か感覚優位かの傾向によって変わります。
感謝できない人は思考優位で自分を内側からよく知っており、外側(客観視や他者側目線)からの自分をよく知らないというものです。
②内側の自己認識がなく、外側があるパターン
- 思考優位の人
…感謝を知らない人(規範順守にてありがとうと言葉は発するが中身がない) - 感覚優位の人
…感謝を知らない人(幼少期の教育等にて言うように促されたからただ言う)
内側の認識が強い場合には、感謝とは何かを自ら理解しないと納得いかなくなる人もおり、しっかり自らの意志や認知を持って解釈する経験がないことで、感謝したくてもできないことが起きます。
反対に、外側の認識が強い場合には、「ありがとう」や「感謝」という言葉をよく使用します。しかし、社会順守やルール従順として音を発する状態であるため、感謝の意味を知らずに使用する傾向があります。
みんなと同じであることに安泰の利益があり、感謝していると思い込み実際には感謝できていないさまが表れます。
※謝らない人の詳細は、【一旦人生ストップ】謝らない人の特徴と末路。欲が鎮まるまでの待機条件 をご覧ください。
感謝できない原因
上述の心理はほんの一部です。ここからは原因の紐解きと同時に心理をさらに含め、より詳細をご覧ください。
感謝とは何か?
- 自らの喜びや嬉しさを得た状態表現
- 他者から与えられた恩恵に対してお返しする気持ち
日本語の感謝の意味は、自らの喜びや現状の心地良さを表すものでして、語源からは緊張がほぐれて抵抗のない様を表します。
緊張とは恐怖やこわばりによる抵抗の表れ、抵抗がなくなることは受け入れられる状態を意味し、「自分らしく受け入れるさま、その気持ち」が感謝や謝りと考えられます。
「ありがとう」という言葉は仏教に由来し、「とんでもない、有り得ないことが起きた」という貴重なさま=「有り難い」を表すものとも言われています。
英語やドイツ語やフランス語など、言葉が変わると意味は一変します。
日本語の感謝は着眼が完全に己です。英語などは己ではなく他になります。
他者から恩恵や利益を貰い、喜びを貰ったことなどに対する合図やお返しの気持ちとして、他者に対して伝えます。
- 感動の認知(自らの喜び表現)
- 愛を与えたい気持ち(他者への労いや敬い)
二つの感謝の意味は、自らの状態表現か、他者に伝える気持ちかが分かれます。
感謝する場合にはどちらの意味を込めているかの自己理解が、大前提として必須です。
※感謝の詳細は、言霊のスピリチュアルに神々が宿る|感謝のありがとうは波動の引き寄せ をご覧ください。
感謝できない原因
自らの殻にこもることで他の存在への敬いがなくなり、自分に集中しすぎて回りが見えなくなり、余裕がなくなります。
感謝するためには、自らの喜び認知の自己表現をするのか、他者に対しての労いや敬いとして愛を与えるかが分かれますが、自己認識に余裕がなければ感謝できる状態ではなく、自らの喜びの認知も、他者への愛も自己表現しなくなります。
しかし、自己表現が苦手であるために、表現しないだけで感謝しているかもしれません。
そこには、感謝できない原因がいくつか見られます。
- 自己認識を育む経験がない
- 自己表現せずに自らを抑え込む
- 他が主観
- 他者を含めた認識がない
- 認識力が低い
[認識]、[表現]がキーワードです。
一つずつ見ていきましょう。
1、自己認識を育む経験がない
感謝できない原因の一つ目です。
認識を育むためには経験が必要です。
「これは嬉しいことだ」と自らの感情を知り、情動を感じ、認知を理解する意識がなければ感謝できないのは自然です。
極端な例として、感情を感じない人であれば感謝は困難です。
実際に他者から恩恵や利益を与えれれるような嬉しいことの経験など、肯定にて認められたり褒められたりする経験が乏しければ、自己認識は内側の殻にこもるような育みとなり、感謝から遠ざかります。
2、自己表現せずに自らを抑え込む
肯定されない経験や、他者への興味や関心など他に目を向ける動機がないと、自己表現する意味を見出せなくなる可能性があります。
他者から否定された経験の記憶が強ければ強いほど、他に興味関心がなければないほど、自らの世界のみで生きる常識が本人の中で作られ、感謝の表現をする意味はなく、内側で一人ガッツポーズという具合で片付けます。
恒常化するとガッツポーズの自己満足にも意味を見出せなくなり、感謝を感じることも薄れ、あることが起きます。
受け入れず、拒否が多くなること。自らへの敬いがなくなる意味です。
物事の受け入れがなくなると思考優位で拒否前提の評価・判断区分け意識が強まり、損得勘定、恩徳、貸し借り計算、未来も含めた計算をして感謝に価値という負荷をかけ、拒否して感謝しないで済むように距離を取ります。
※親に感謝できない原因は、【自分のためになる気づき】親に感謝できない原因と改善 をどうぞ。
3、他が主観
他との区分けにて自らを認識することが極端に多くなると、自分がなくなります。
常識やルールの規範に則り、他が決めた世界の中で生きる常識ができ、自らを主観にした認知がなくなります。
他が主観となることで、感謝は「ありがとうと言うルール」となり、ルールのイン・アウトの繰り返しになります。
感謝の意味を考えることも求めることもなく、物事の中身や本質以上に外枠、「他者からどう見られるか」が重要な着眼になり、本当に感謝することが訪れない日々を過ごします。
4、他者を含めた認識がない
認識が自分の内側にのめり込むと同時に、他者が主観となって自らの認識がなくなる両方、いわば極端に己のみ、他のみを見るようになると、認識のバランスを崩して感謝できなくなります。
己か他かの両極端な認識によって、他者を認識する大前提の基盤である“自分”がどこにもいなくなり、何かプレゼントを貰っても他者の労力や時間消費や努力などを理解する概念がなく、逆に自分の欲しいものでなければ文句すら言う人もいます。
敬いや優しさや思いやりと離れていく、感謝できない原因です。
5、認識力が低い
物事を見て、感じて、知って、想って、という認識力が乏しい状態です。
感謝する原材料や、感謝する矛先がわからず、感謝するとかしないとか、できるとかできないとかを考えることもありません。
物事の本質を見る概念が育まれていないため、人に気を使い、気を利かせることもなく、敬いや愛がなく、自らに起きている物事や受けている利益を見ず、物事は「当たり前」になります。
便利な世の中であれば便利は当たり前という認識で、物事を一辺倒にしか見れないために「有り難い」と思わず、自らの喜びもなく、他者への敬いもなくなってしまいます。
※思いやりがない人の心理話は、思いやりがない人の心理と改善│本当に気にしたいのは思いやり偽善 をご覧ください。
感謝できない人に大切なこと
これまでの心理と原因を踏まえると、「感謝できない人は感謝の必要性を知らない」可能性があります。
感謝の必要性=自他への敬い=自分らしさと愛の認知の有無。
感謝するか否かを分けるのは、自分らしさを持って愛の認知があるかどうかです。
- 自分らしさがあれば、自らの喜びの表現として感謝できます
- 愛の認知があれば、他者への敬いの気持ちとして感謝できます
- 両方あれば、物事の意味を一つ一つ理解して有り難いことが常に起きていると感謝できます
自己認識が内側へ向かおうが、感謝できなかろうが、大切なのは自分を見失わないことです。
「ありがとう」と言葉だけで上っ面の感謝という何かをしている場合、本当に感謝できない人になります。
それが感謝だと思い込んでいるので、自ら変える意志や動機がなくなり、気づきを得にくいためです。
感謝の必要性は人それぞれです。自分らしさが欲しいか否か、愛の認知が必要か否か、みんなみんな違うからです。
感謝の必要性があると思った場合には、大切なことは一つだけです。
そんな方へ向けて、最後にその一つをお伝えして終了します。
感謝するには自分を、物事を、一回一回、いちいち受け入れる
もういちいちやります。
自分を受け入れれば、自分らしさが表れて感謝できます。
他者を受け入れれば、敬いの愛が表れて感謝できます。
物事を受け入れれば、「有り難い」と認識して感謝できます。
私達人間は脳を主体にすると怠け癖があり、飽き性で、変化を拒みます。自然とそうなります。
認識が希薄になり、「今日はご飯食べられる」とは思わず、「今日もカレーかよ」と思ったりします。
「炊飯器があって良かった」ではなく、「この炊飯器使えねぇ」となります。
起きている現実を自分ルールで塗り固めずにそのまま認識するだけで、「今日もカレーを食べられるんだ」と感謝が湧き出ます。
「今日も朝早く起きて、仕事して、お金稼いでいるんだ、私は」と自分を受け入れると、どれほど自ら喜びを作っているかわかります。
「今日も奥さんは目の前に居て、私を安心させてくれる」と他者の存在を受け入れると、どれほど自らが利益を得ているかがわかります。
受け入れるためには自分で認識する必要があります。
一回一回、いちいち認識して、見て、聞いて、感じて、触って、理解して、考えて、そして受け入れます。
認識に拒否を作らないと日々の生活は自然な経験の蓄積となり、毎日自己認識を高めて、他者認識を育み、物事の認識力を養います。
配慮ができ、気が利く人にもなる道を開く。そんな恩恵モリモリのお話です。
※感謝の気持ちを持つ方法については、感謝の気持ちを持つために知りたいこと│感情ではなく想いという話 をご覧ください。
感謝できない人の心理と原因 まとめ
感謝できない人は相手を見ていない、行為を見ていない、起きることを見ていない、他者も含めた上でこの世界が成り立っている認識がない可能性があります。
私達は一人一人個々に生きているために、この世には自分しかいないと認識することは何もおかしなことではありません。
自己認識が内側に偏ることには原因があり、幼少期の環境や周囲との関わり、肯定や愛のなさ、自らでしか愛を与えられず、抑制したり自己表現が上手くならない結果があります。
人それぞれに人生があり、生きてきた経過があるため、感謝の必要性はバラバラです。
わざわざ感謝する必要はありませんし、したければするものです。
感謝とは何かを知ると自らを知ることに繋がり、感謝したいと思える動機に繋がり、必要な人は感謝できるようになります。
人と人の関わりを重要視する価値観が見え、生きる環境を与える社会性、あらゆる人と人の繋がりにて構成された恩恵を知り、自分という存在は自然や環境や社会などの他の一部だと気づけます。
認識幅を広げることで、どれほど感謝する材料があり、機会がありと、世の中の見え方が変わり、感謝がまるで当たり前かのようになるかもしれません。
すると、感謝をより認識するために感謝しないことが重要にもなります。
全てが大切で意味がある。人間とはこういう生き物だと思います。
感謝とは自らの喜び認識であり表現、他者への敬いであり愛の気持ち、有り難いと物事を受け入れることの大切さを教えます。
それは自分を中心にして他に目を向ける姿勢です。
欠けたピースだらけの人間だからこそ、自分を忘れたら崩れちゃう、他に頼ったら崩れちゃう。
だからこそ自分を忘れずに内側を明確にし、確実に外を向く。感謝によって紡ぐ他との関わり、物事の大切さがあります。
心理の理解がお役立ちできれば幸いです。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ピン!」と来た方はぜひお試しください。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作成してもらえます
的確にわかりやすく言語化してくださるため、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください