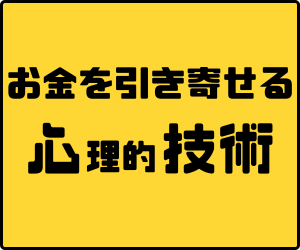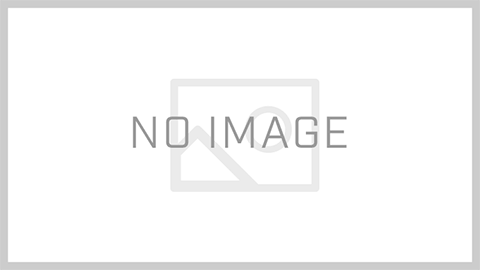「あれ、なにこれ?」
ブヨブヨと体内から心地悪さを感じ、目がキョロキョロし始める。
気づけば呼吸が浅くなっており、なんだが窮屈で落ち着かない。
明らかにこの人によって心地悪くなっているが、何か嫌なことをされた訳でも、悪い人でもないので理由がわからない。
そんな、なんとなく苦手な人。
「私ってなんでこの人が苦手なんだろう?」
ここでは、よくわからないけれども確実に苦手である、そんな不可解な気持ちの真相に迫ります。
- なぜ苦手意識を持っているか知りたい
- 訳もわからず苦手になる自分を深掘りしたい
一体相手との間に何が起こっているのか。
人間関係における苦手意識を明確化するために、一つの考え方としてご参考になれば幸いです。
心理とスピリチュアルを含めた洞察内容、体験談と共にご覧ください。
Contents
なぜか、なんとなく苦手な人

なんとなく苦手な理由:「心を閉ざしたい」
「理由はわからないけど、なんとなく苦手なんだよなぁ」
この気持ち、さまざまなシチュエーションで発生します。
「あのメンバー、みんな明るくて楽しそうだけど、なぜか苦手」
「あの人、悪い人じゃないけど、なぜか苦手」
「なんとなく」と曖昧なニュアンスでありながら、「苦手」とはっきりした認識。
この状態は、ロジカルな理由はわからないけれども、感覚による拒絶感度はバツグンと言えそうです。
思いは不明、感じは明確。
「感じ」は唯一無二の自分でしか体感できない認知ですので、圧倒的信頼感があります。
このことからわかるのは、他の情報や他者からの影響など“他”を含めた思考(頭)ではなく、自分のみが感受できる気持ち(心)が「苦手だよ」と言っていること。
なんとなく苦手な人とは、自分の心が拒否する相手です。
心だからこその拒否理由には、相手と繋がりたくない、同じ時空を共有したくない、共感や共鳴したくない、またはそれらができないことが考えられます。
心を閉ざしたい人であり、心を開きたくないと感じる相手に対して、なんとなく苦手になる、という考え方です。
[苦手or嫌い]の違い
私たち人間には人それぞれの本能や許容、血筋や遺伝など、過去や歴史からの継承による捉え方の基準があります。
さらに心の感受の基準となるものに、[波動、波長、意識階層]があり、スピリチュアルな魂も含めると魂レベルなる次元差異のギャップなんかも加わります。
誰しもが同じロボットではないので、人それぞれに必ず千差万別の波長があります。
波長には波動や意識の違いが関係し、共鳴や共感や共有できるかできないかを分ける、合う合わないが自然と発生します。
合わない場合はお互いの波長が違うので、心は違和感や不調和をサインします。
「はい、この人と心が合いませーん」
心が認知する波長は、「機嫌が良さそうな今日のあの人なら合う」なんてことはありません。
毎日合わない。
合わなければ即座に関わらないで終わりたいですが、同じ職場や仕事関係、家族や親戚など継続的に関わると、合わないことでの拒否感が強まります。
この拒否感、苦手なのか嫌いなのかで、「なんとなく」の紐解きが変わります。
- 苦手な場合 → 心を閉ざしたい
…ネガティブな拒否 - 嫌いな場合 → 心を開きたくない
…ポジティブな拒否
心を閉ざしたいのか開きたくないかは、真意が一変します。
ここでお伝えする主旨は、[苦手=心を閉ざしたいから]
閉ざしたい気持ちの紐解きに、なぜ苦手なのかの答えがあります。
ネガティブ、ポジティブとは、概念的な悪い、良い、ダメ、OKのことではありません。
陰[静・引・受・待・知・凹…]
陽[動・押・発・主・感・凸…]のこと。
なんとなく苦手になるのはなぜ?:認めたくない自分になるため

閉ざしたい気持ちはネガティブ(陰)な状態から生まれ、内部に溜めるのが特徴です。
相手に対して以上に、自らの内部に拒否感を抱きます。
自己内部でドギマギ、ザワザワして落ち着かなくなり、心地悪さや違和感を感じます。
人によっては自己否定に向かい、「私がいけないのかも」と考えます。
ネガティブな気持ちであり、自らを下にして劣等や罪悪感を抱き、自信がなくなり、認めたくない、見たくない、関わらないで欲しいという受動的スタンスになります。
認めたくない自分になることが嫌にもなり、とにもかくにも拒否感が内部に蓄積していきます。
そんな対象にはこんな傾向があります。
- 比較して人を見下しているが、外観はそう見えない人
- 嘘や偽りで塗り固めているが、外観はそう見えない人
- なりたい将来像でありながら、どこかでそうはなりたくないと思える人
- 関わると自信がなくなる対象
- 関わると自分を喪失する対象
- 関わると元気がなくなる対象
全てに共通することがあります。
『なんとなく苦手な人とは、関わると認めたくないネガティブな自分になってしまう相手』
※大人数に対する苦手心理は、【大人数が苦手な人見知り心理】内向性トラップに改善策4点 をご覧ください。
解説:苦手意識の真意は「比較+自己不一致」
「苦手」はネガティブな拒否、「嫌い」はポジティブな拒否。
両者の違いによって、苦手意識を持つ際の状態がわかりやすくなります。
苦手な人といるだけで、なぜか腐ったカステラが自分にだけ降ってくる、「ベチョベチョ、最悪、もう帰りたい」
そのままの自分でいることに耐えられない状態です。
相手は何もしてませんし、知りません。
※エネルギーを奪われることで、元気がなくなってネガティブになる場合は別
苦手になるのは、相手の言動、能力、行動によって、認めたくない自分を見出してしまうためだと考えられます。
紐解くとこうなります。
解説
関わることで相手との比較やネガティブな影響が発生し、認めたくない自分になる
↓
認めたくない拒否感によって恐怖心が生まれる
↓
認められない自分と、認められないのが嫌な自分が生まれ、自己不一致(アイデンティティクライシス)勃発
↓
自己が統率(コントロール)しにくくなり、さらに恐怖心が増え、心を閉じる防衛機能が発動
↓
心を閉じたくなる
嫉妬の人もいると思いますが、ここでお伝えしたいのは、認めたくない自分を見たくない拒否感と心の閉じです。
嫉妬心ではない理由は、なんとなく苦手意識を持つ方は、自らを主張したり相手を変えようとプッシュするタイプではないからです。
喜んで剣を振るのではなく、自分や誰かを守るために仕方なく剣を振るタイプ。
自己防衛優位の意識があると、心を開きたくないのではなく心を閉じたくなり、自己内部に生まれる拒否感を見たくないがために心地悪さを抱きます。
※感情的な人への苦手意識については、【すぐ感情的になる人に疲れる方へ】苦手意識があるからこその策略 をご覧ください。
なんとなく嫌いになるのはなぜ?:強引に変えられるため
一方、「なんとなく嫌い」になる理由は自己防衛ではなく、抑圧されることへの反発欲求、ポジティブな反動、凸系です。
嫌悪や反発を自己内部に留めず、外部に発散します。
「私は、あなたのことが、嫌いだー!」と学校の屋上から叫ぶイメージです。
支配欲や正義感の強さ、自己を正当化したい観念や自意識の強さ、強要されたくないことへの反発が主に考えられます。
中にはネガティブな拒否として嫌いになる人もいますが、その場合は他者のせいにする他責、自らの気持ちを自覚しない無責任などが加わります。
※この場合は嫉妬にて嫌う人が多い
「嫌い」になる際に共通しているのは、自己内部に拒否感を抱く以上に、相手に向けて抱く拒否感。
「関わってくるんじゃない、恐怖心を与えてくるんじゃない、こっちに来るんじゃない」とはっきり。
「この人に心を開きたくない!」
関わる際には自らの心を閉じるか、相手を強引に変えることになります。
相手を強制すると攻撃になりやすいので、多くは心を閉じる選択に。
「閉じたい」なんて心は言っていないのに、関わる以上は閉じなければならない強制が課せられます。
「あの人と関わるとやりたくないことをさせられる、自分を強引に変えられる、ムカつくな」となります。
なんとなく嫌いな人とは、関わることで強引に自分を変えざるを得なくなる相手。
「もう、やめてくれよっ!」と反発心が強くなり、ポジティブな怒りや嫌悪をぶん投げたくなります。
※嫌いな人に拒絶する真意は、【最上級のサイン】嫌いな人への拒絶反応に潜む意味と対処法(解説by体験談)をご覧ください。
なんとなく苦手な人の対処法

体験談:職場の苦手だった部長
対処法がわかりやすくなればと思いますので、先に私が対処した体験談をご覧に入れます。
会社員時代のこと。
当時の私はお金が全てだと思っていたので、とにかく働いて昇給と昇格に集中し、上司に言われたこと+αααをする猛烈な欲の塊でした。
そんな時、職場の部長(中年男性)は年収が1,000万円をゆうに超えていると知り、私は彼のようになればと考え、目で追うようになりました。
しかし直ぐにわかったのは、「あ、この人苦手だぁ」
アンパンマンを30年間くらいエゴ汁に浸して、チャイを一緒に混ぜて顔を洗うみたいな感覚でして、話したり関わる度に、「うふぇー」となっていました。
彼は明確にわかるほどの上っ面仮面を被りながら、毎日ニコニコ、いえ、ニタニタしながら挨拶をします。
挨拶を終えた後、振り返った後の顔が極悪人でして、「一体何人殺めたんだ?」と本気で思えます。
偽笑顔と仮面があからさますぎており、笑顔かと思ったら急に罵倒して怒鳴り出し、普段は異様に優しいという奇怪。
「比較してます、見下してますよ」と顔に書いてありながらニタニタするので、異常性すら感じます。
なんとなく苦手だったのは、シンプルに危険人物であり信用できない、という側面もありますが、主な理由は別に二つありました。
- なりたい将来像でありながら、やり方が汚い(そうやって出世したくない)
- 見下しが自然と露呈しており、部長と関わると私自身も比較する自分になってしまう
「私はあの人のようになりたい」と思いながら、「絶対にああはなりたくないな」と感じる。
隠しているが上から目線で見下しているのが見え見え、関われば関わるほど私のアイデンティティはズレていく。
合わないにもかかわらず、「この人のようになれば」と思う私のエゴが邪魔をして、認めたくない自分と、認められないのが嫌な自分が分かれ、拒否感と心を閉じる防衛が苦手意識を強める。
関わる度に私の内部に拒否感が蓄積され、心を閉じたくなっていました。
自己像がわかると苦手ではなくなった
最終的に苦手意識がなくなったのは、とてもシンプルな方法でした。
「はっきりわかった、私はこの人のようになりたくない!」
それはもう確固たるものでした。
私がこのように認識できたのは、インドに行ったことが全ての要因でした。
当時初海外、10日間の休みを取って突然インドに行った私は、日本に戻ってきてあらゆる物事の見方・捉え方・感じ方が一変しました。
対処できたのは無知がなくなったからです。
どうして苦手なのか、どうして苦手意識が芽生えるのか、相手のことも自分のこともわかっていなかったとわかりました。
苦手が解消する前は、「私はどうしたいのか?あの人のようになりたいのか?なりたくないのか?」がはっきりしておらず、自己像が曖昧でした。
「それじゃあ私はどうしたいか決めよう」
インドから戻って出社し、「ナマステー」と言いながら仕事をするようになった私は、驚くほどはっきりとわかりました。
「絶対に、この人のように、なりたくない、ならない!」
気づけば苦手意識はなくなっていました。
※合わない人や場所の対処法は、波長が合わない人や場所はどうすれば?【対処法は人間の基本原理】をご覧ください。
なんとなく苦手な人の対処法:自己像

対処法は自己像の明確化です。
「自分を明確にする」という壮大なものではないのでご安心ください。
あくまで苦手な人に対する対処として、苦手な人と関わるとブレて曖昧になる自己像をはっきりさせるのが目的です。
することはシンプル、
「この人のようになりたいか?」を自問して明確な答えを出します。
そのためにステップがあります。
- 自分が相手から受けている影響(比較やネガティブになっているなど)を把握する
- その自分がアイデンティティクライシスを起こし、認めたくない自分になっていると把握する
※認めたくないことが嫌な自分が把握できると、苦手意識をなお解消しやすい - 認めたくない自分が把握できたら、「私はあの人のようになりたいか?」と自問自答する
答えが明確に出せれば出せるほど、苦手意識は緩和されていきます。
フワッと手放されるように徐々に相手への意識が薄まり、気づけばなくなっています。
自問自答の答えは、「なりたい」でも「なりたくない」でもどちらでも構いません。
答えには正解も間違いもなく、あくまで相手からの影響を受けている際の自己像を明確化することに意味があります。
そのために、なんとなく苦手な人と自分を一度はっきりと投影させ、認められる自己像を見出すことで、自己内部に発生する拒否感をなくすのがこの方法の仕組み。
自己像を明確化させることで、自分と相手に対する無知(恐怖心)がなくなり、苦手意識がなくなっていきます。
ぜひ、これまでと次回関わる際の体感の違いを味わってみてください。
※スピリチュアルな対処法は、嫌いな人にスピリチュアルな意味深│苦手、関わりたくない、会いたくない人の対処 をご参照ください。
対処する際の注意点
対処するには考え方がとても重要です。
苦手なのは、相手ではなくこちら側の問題と考えます。
極端ですが、「相手は関係ない、問題は私だ」とした方が解消しやすくなります。
一方的に自己不一致になり、拒否感を強め、恐怖心を生み出している。
それによって無知が深まり、相手からの影響を受けやすくなり、自分も相手もわからなくなり、自己像が曖昧になる。
[合わないことでの拒否感+自己不一致+無知=心を閉じたくなる]という仕組みがあるので、対処の着目は相手ではなく完全に自分のみ。
一方的に影響を受けている自分を見つめ、認められない自分を見つめ、相手の前で曖昧になっている自分を見つめ、拒否感を生み出している自分を見つめます。
相手と関わる際の自分を知ることは、自らの在り方に責任を持つ行為となり、相手に対する自己像の明確化だけでなく、自分軸をはっきりさせる効果もあり、一石二鳥です。
※悪態が苦手な人の対処法は、感じが悪い人の特徴とスピリチュアル『気にしない方法は欲求理解』をご覧ください。
まとめ:なぜかなんとなく苦手な人
- なんとなく苦手な理由は、波長が合わないことで心が感じる拒否
- 相手と関わることで認めたくない自分になり、拒否感(恐怖心)が生まれる
- 比較、ネガティブ、自己否定などをする自分になり、自己不一致が起こり、コントロールが困難になり、心を閉じたくなる
- 「苦手」と抱く場合、自己内部に拒否感を作っている
- 「嫌い」と抱く場合、相手に対して拒否感を作っている
- 「心を閉じたい」と心は感じていないのに、関わる以上は閉じなければならない強制が課せられ、嫌いになる
- なんとなく苦手な人の対処ポイントは、相手から影響を受け、自己像が曖昧になっている自覚と、その解消
- 苦手な人と自分を一度はっきりと投影させ、認められる自己像を見出すことで、自己内部に発生する拒否感をなくせる
- 方法は、「私はこの人のようになりたいか?」の答えを明確にする
- 苦手なのは相手によるものではなく、自分によるものだと考えると解消しやすい
- 自己像の明確化によって自責の強化になり、自分軸を強める効果もある
合わない人は合わない、苦手な人は苦手ですので、自分の心はいつ何時でも信じていいものです。
人間関係を気楽にするためのご参考になれば幸いです。
それでは最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
『心理とスピリチュアルの学び場』
誰しもに人生を変える機会と選択があると信じています。 著名な心理セラピストとして知られる、西澤裕倖(にしざわひろゆき)先生プロデュース。
著名な心理セラピストとして知られる、西澤裕倖(にしざわひろゆき)先生プロデュース。PR:株式会社Central&Mission
※これは長期的に本気で変わりたい方専用です。