【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ぜひおすすめしたい」と感じたのでご紹介です。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作ってもらえます
「なんでこんなにわかるの?」と思えるほど的確で、わかりやすく言語化してくださり、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください
中身がない人はモノクロ、単調な特徴があります。
身がないと関わりに空虚なさまがあり、色味や深みがないために人間関係が希薄になり、外面や装飾などの外部情報に関する着目が主体になります。
「中身」
人として、個人として、自分としての内側を表す身とは一体何なのか、気になるところです。
ここでは中身がない人の内側、実情として明確に表れる特徴をお伝えし、中身を入れる改善探索をしていきたいと思います。
- 中身がない人の決定的な特徴とは?
- 何が中身をなくさせるの?
- 中身がない時の改善方法とは?
これらを知っていただき、「中身がない時は中身を入れる以上に大切なことがあるんだ」と知っていただく内容となっております。
中にある身の詳細を知ることで、より深く濃い人間味が追加される一助となれば幸いですので、一つの考え方としてご覧ください。
Contents
中身がない人

中身がない人とは?
中身がないとは、「人間としての中身」を意味します。
人間味、愛情や敬い、思いやりの優しさ、同情に共感、調和に助けなど、人情味としての捉え方もありますが、ここでの中身は別物。
人間くささ、価値であり影響です。
中身がない人とは価値を見出しにくい人です。
周囲の人が価値を見出すための、影響力がない人です。
中身がない人の特徴1選
「周囲が価値を見出すための影響力とは?」
人と人が関わる際、相手に価値を見出すことで、「話したい」「もっとこの人を知りたい」と思います。
同時に、関わっている時に自らの価値を見出すことも起きます。
「あの人の価値は何だと思う?」と中身がある人を考えてみると、何かしら価値があることがわかります。
「一緒に居ると楽しくなれる」
「もっと話したくなる」
「この人をもっと知りたいと思える」
「見てるだけで癒される」
「もう興奮しちゃう」
「怖いけど指摘してくれる」
「気づきを与えてくれる」
「自分らしくいられる」
「嫌なやつだから自分を護ろうと思える」
「利用されているから自分を大切にしようと思える」
‥‥
良い人でも悪い人でも、相手への価値や自らの価値を見出す影響があります。
例えば、悪い人と関わると、「怖いから自分を護らないと」という具合に自らの価値を見出そうとします。
悪い人に中身があることを意味し、何かしら相手か自分かの価値を見出す影響力を持ちます。
価値を見出すことは意味を見出すことでもあり、欲を見出すことでもあります。
この影響力がないと、「この人と関わる意味って何?」となります。
中身がないと関わる意味を相手が見出せなくなります。
ここに中身がない人ならではの特徴として、明確な一つが表れます。
中身がない人は価値を見出す動機(意味)を失わせる。
「この人と関わりたくない」ではなく、「この人と関わってどうなるの?なんか意味あるの?」と思わせる特徴です。
中身がない人の特徴を物語る特徴12選
上述の特徴から派生して、さらなる特徴が見られますので、詳細をご覧ください。
1,他者認識力がない
自らを保持・管理するのに精一杯、他者の立場や目線で認識する余裕がない特徴です。
2,見栄え、体裁、評価の気にかけがメイン
認識のフォーカスは、他者からの見られ方。
周囲の反応や評価を気にかけ、見栄えや体裁を気にした在り方をします。
外観、表面、表層と、鏡に写して見える部分の気にかけが主体となります。
3,自分を知らない
他者から見える自分を大事にするため、自己認識は自らを外側から見る見方に偏りがちです。
内側からの見方や、自分を自分で認識することがなくなり、常に他者の存在ありきで自分を存在させます。
自分を知らない状態ですが、他者の存在によって自らを認識しているので、そのようには自覚しない特徴でもあります。
4,他に執着と依存をする
他者の存在なしでは自らの存在認知ができないために、自然と執着や依存をします。
執着や依存をしているとは思わないようにする特徴があり、自覚しないようにします。
他者を利用しているのに利用していないと思う状態になり、「仕方がない、執着させてあげよう、甘えさせてあげよう」と相手が思っても、「執着してない、甘えてない」と拒否し、関わる意味を相手から喪失させます。
5,矛盾が多い
優しい顔して相手のことを思っている自分を作りますが、いざ頼られたり優しくしなければならない状態になると拒否します。
怒った後に謝りますが、その後に直ぐにまた怒りと、上っ面の表層意識だけであることが露呈し、自己矛盾を公けに表現する特徴です。
信用や信頼から遠のき、「関わると疲れるしつまらない」と関わる意味を喪失させていきます。
6,嘘と誤魔化しを多用する
最も顕著に表れる特徴です。
自覚しないことを重要視して嘘や誤魔化しが多くなり、現実と事実を見ない、感じない、考えない、思わないようにします。
誤魔化しを他者にもしますが、自らに多用することに中身がない人特有のさまがあります。
7,自己価値の押し売り
「これだけ凄いんだ」「これだけ知っているぞ」「こんなのも持っている」
自らを高めるために他者の存在を欲し、自己価値の押し売りが起きます。
8,他者の反応や言動に翻弄され過ぎる
「ガーン」「あんな評価されたから何もできない」「そんな風に見られたら立ち直れない」「あんなことを言うなんて許せないキー」
他者の影響を強く認識し、自己防衛として虚しさや悲しみや怒りを表し、自己コントロールを逸脱する特徴です。
翻弄され、他者の存在が良いも悪いも全てを担うかのごとく、自分を構成する材料になります。
9,感性が乏しい
自分の意見や認識が少ないために感性が乏しい特徴です。
他の意見を主体にしているため、世間の意見や常識などの情報量が多く、他の情報による思考を多用します。
10,「普通は、みんなは」が口癖
常識や一般論、大衆的で統一主義思想が多く、「みんなはこう」「普通はそう」「常識はこうなっている」「これが世間的には正しい」「それは一般的には間違っている」という言葉を使用します。
11,記憶力がある
試験問題の点数が高い特徴です。
教科書や辞書など、既にある規定の他の情報のインプットが上手で、記憶力が高く、決まったことをするのが得意です。
12,創作が苦手
新しく一から作るのが苦手です。
自らの、特有な、独自の、個性の、そういったものが希薄な特徴です。
以上が、中身がない人の特徴から派生した特徴でした。
中身がない人の特徴 一覧
- 価値を見出させる影響力がない
- 他者認識力がない
- 見栄え、体裁、評価の気にかけがメイン
- 自分を知らない
- 他に執着と依存をする
- 矛盾が多い
- 嘘と誤魔化しを多用する
- 自己価値の押し売り
- 他者の反応や言動に翻弄され過ぎる
- 「普通は、みんなは」が口癖
- 記憶力がある
- 創作が苦手
※中身がある影響力者の話は、影響力がある人の特徴に絶対的なことが│信念との合わせ技一本 をご覧ください。
中身がない人の改善
中身がない人になる原因とは?
特徴全てに共通する核があります。
中身がない人を物語るさまは、「逃げる」ことです。
自分を誤魔化す、恐怖からの逃亡癖です。
ここで、中身がない人を表すおとぎ話がありますので、見てみましょう。
シンデレラ。
彼女の近くには意地悪なお姉さま達がいますが、王子様はシンデレラを選びました。
この話、見方を変えるとこうかもしれません。
あるところに中身がある人がいました。
貧しい中身がある人は、外観はみすぼらしいですが、自らを認め嫌なことから逃げずに生活し、一生懸命に働きました。
そこに中身がないお姉さま達がおり、綺麗な服を着て、お化粧をバッチリして、外観を取り繕い、他者からの見かけを気にし、嫌なことは認めずに逃げ続けていました。
王子様は一緒に関わった際に、自らの喜び、そして関わった中身がある人の価値を見出す影響力を、中身がある人との時間で味わいます。
一方、「なんだこれは?」「この人と話して何か意味があるのか?」「この時間は一体何なんだ?」と思ってしまい、良いも悪いも価値を見出せないお姉さま達との時間。
中身がある人を選びました。
実は番外編が存在し、中身の改善がわかりやすくなる話もあります。
番外編:毒リンゴばばあは中身ぎゅうぎゅう
別のおとぎ話のキャラクターが参入、中身がある人に毒リンゴを渡したばばあがいました。
このばばあの存在によって中身がある人は死に、恐れおののいた王子は、「自らを大切にしなければ」という欲求を増やし、無意識に自分の価値を見出す影響を受けていました。
あまりに影響力が強過ぎたため、毒リンゴばばあを仲間に迎え入れ、自らを危険の身から案じて言いなりに。
王子のいた国は毒リンゴばばあに牛耳られましたとさ。
中身がある人とは、良いも悪いも関係なく、価値の見出しを促す影響力者。関わる意味を強く見出す人です。
- 「喜んで関わりたい」と思わせる中身がある人もいれば
- 「絶対に関わりたくない」と思わせる中身がある人もいる
中身がない人はどちらでもありません。
関わりたいとも関わりたくないとも思わせない影響のなさがあり、恐怖からの逃げ、自分から逃げているさまが原因にあります。
※中身がある人の核は、中身がある女性に共通する「ある一つ」│ギュウギュウに詰まる身とは?をご覧ください。
中身がない人の改善ポイント
恐怖から逃げるとは、認めたくない、知りたくない、味わいたくない、嫌だ、拒否したいと思える自分から逃げることです。
恐怖という苦痛、危険、拒否に対しては、誰もが嫌がりたいものですので、逃げるのは自然な反応かもしれません。
逃げたことを自覚しない=逃げたことからさらに逃げる場合、「嫌なことを味わわない恐怖のなさ」に対する欲求を見出し、自ら進んで逃げる人もいます。
逃げの表れとして顕著になるのが、「嘘、誤魔化し、自覚しない、認めない」です。
例えば、友達と喧嘩した際、誰しも謝るのは怖く、何を言われるか怖れ、誤魔化したくなります。
逃げない人は中身がある人です。
逃げる人は自分を正当化し、外観を取り繕い、他者の反応を気に掛けるようになり、それを自覚しないように誤魔化します。
自分がなくなり、人間味がなくなり、人間くささがなくなります。
負の連鎖へ向かいますが、このことから大事な理解もわかります。
誰しも逃げ続ければ中身がなくなるけれども、誰しも逃げなければ中身を入れられることです。
改善のポイントは逃げない、自分から逃げないことです。
中身がない改善方法①:感性を養う
一つ目は感性です。
自分がなくなるとは感性がない意味でもあります。
感性とは自らの認識による、自分という存在の知覚能力であり、自分を構成する自らの認知材料と言えると思います。
自分を構成する基盤となり、完全に己を主体にした五感、感情、欲求などの感受認識です。
感性を養う方法はとてもシンプルでして、自分の認識にある、感覚や感情や想いのあらゆる感受、感じをじっくり体感。
ご飯を食べたら、風が吹いたら、肌に当たったら、人を想ったら、怒ったら、泣いたら‥‥。
何を思うかではなく、感じるかが重要になります。
この認識を増やしていくと感性が養われ、自分の内側を彩る材料が増えていきます。
また、過去、感性が豊かだった子供の時などを思い出すのも方法です。
※感性の詳細は、感性が豊かな人から学ぶ感性とは?│特徴には知性の有無とぶっとびパンピー をどうぞ。
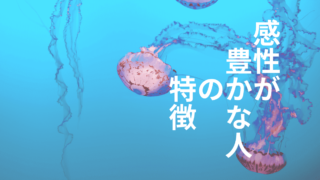
中身がない改善方法②:逃げない
いきなり逃げなくなるのは困難なので、初めは逃げている自覚が大切です。
嘘をつかない、誤魔化さない、事実をすり替えない、なかったことにしない。
嘘や誤魔化しをする自分を自覚し、逃げている自分をまずはチラ見、その後はジー。
虚しくなった時、それが誤魔化しかジー。
怒りが出た時、誤魔化しかどうかジー。
悲しくて泣く時、誤魔化しかどうかジー。
他者を否定・非難したい時、誤魔化しかどうかジー。
逃げる経験が多ければ多いほど、恒常化して自分の中での常識になるので、少しずつでも逃げている自覚を増やします。
しかしそれでは苦しいだけですので、重要なのが感性の養いです。
逃げている自分をジーっとしている時に、「一体何を感じますか?」
これを認識し、自覚を増やしていくことが改善に繋がります。
※中身がないと人生がつまらなくなる話は、人生がつまらない理由は明確に一つ、普通だから。それを変えていく話 をどうぞ。
中身がない改善方法③:執着を認める
中身がない改善方法は、中身がある人になることではありません。
物事には段階があるので、中身がない状態を認めるのが先決になり、その後は自覚できる実感(逃げない認識)を増やしていくことで中身を詰め込みます。
中身を増やすには感性を基盤にした上での知性を要します。
会話を作れるようになり、自らも価値を創出できるようにしていきます。
そのための改善は、中身がない状態を認めることです。
中身がない人は他に執着と依存をします。
私達は誰しも弱い存在で、一人で生きられないからこそ他者にすがり、利用し、利用され、上下関係を作り、ルールで縛り、利益を見出し合い、関わりに工夫を作っていきます。
他者の存在にて自分を見出す執着があれば、その自分を認められると次へ向かいます。
認めないと自分が掴めない影のようになるので、「執着が悪い、ダメ」と決め付けず、認めることで他者からすれば中身が見えるようになります。
中身がない人の特徴と改善 まとめ
「自分がないのにないと認めない」
これは関わる人に、価値を見出す動機を与えず、喪失させる可能性があります。
誰しも恐怖は嫌なものですので、逃げてしまいたいものだと思います。
ここで戦うかどうかは人それぞれですが、「逃げない」が重要になるのが、私達の人間味を作り、人間くささを作ります。
人間としての中身を探求すると、中身も外身も自分であることがわかります。
自分ではない何かがあると、中身も外身もない他の装飾になり得ます。
自分ではない何か、それは自らを認めなくさせる材料です。
中身がなくてもなんでも自分ですので、認められれば即座に中身として、自分という「身」が入ります。
外観を装飾させるのは何も悪いことではなく、大事だと思います。
ですが、装飾に執着し、恐怖から逃げる誤魔化しに使用する時、中も外もないからっぽになってしまいます。
どんな自分でも認めることから人間味が加わり、自分にしかない個性や強みが認識されていき、自らの価値や影響が表れます。
逃げないことは強さにも意志にもなり、中身として人の深さや色味として、関わりに意味をもたらす価値のある人になります。
ぜひより価値を見出すためのご参考となれば幸いです。
それでは、中身がない人の特徴と改善のお話を終了します。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ピン!」と来た方はぜひお試しください。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作成してもらえます
的確にわかりやすく言語化してくださるため、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください











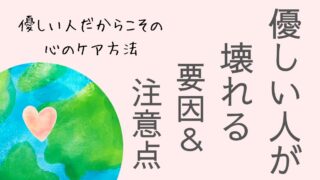
アドラーの共同体感覚についてどういう風に捉えてますか?
共同体感覚…生きている基盤を含めた自分、まさに自分を認識した常識から感じる感覚という具合ですかね。
言い方を変えると、ワンネス、社会認知、俯瞰性、人間の基本原理そのものを綺麗に表現する言葉かと思います。
他者の心理理解は全く詳しくないので、このような賢人の表現を教えてもらえると、とても勉強になります。
また何かこのような問いがあれば、ぜひ。