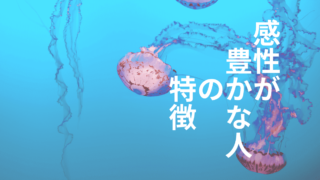【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ぜひおすすめしたい」と感じたのでご紹介です。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作ってもらえます
「なんでこんなにわかるの?」と思えるほど的確で、わかりやすく言語化してくださり、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください
褒められる、認められる、肯定される、称賛に賛美。
褒められると嬉しいものです。しかし嬉しくないことがあります。
喜びを感じない、気持ち悪い、苦しい。
褒められているのに自分はおかしいのかな?
人間の心を失ってしまったのか?
褒めてくるこの人に原因があるのか?
私自身、褒められても全く嬉しくありませんでしたが、本当に褒めてくれる人に出会った時、この認識は一変しました。
「これまでは褒められていなかったんだ」と気づいた瞬間でした。
褒められて嬉しくない場合、自分がおかしいわけではありません。褒めてくる人がおかしいわけでもありません。
両者の合致のなさ、一方的な褒めの使い方や思い込みがあるかもしれません。
- どうして褒められても嬉しくないのか?
- 褒められても嬉しくない心理とは?
- 褒める意味とは?
ここでは、どうして褒められても嬉しくないのかの詳細をお伝えします。
褒めているけれど実際には褒めていない可能性があり、“褒める”とは絶滅危惧行為だったりします。
褒める意味を知っていただき、ご自身を知る一助と共に、褒め行為の生存を図る内容となることを願います。
Contents
褒められても嬉しくない

褒められても嬉しくない理由
優れていたり、良いと判断できる行為・言動に対して、「よっ、あっぱれ、よくやった、関心」などと称えることで褒めます。
これに嬉しくないと、「はっ、うるせぇよ、ぺっ」と。
褒められて気持ち悪い、苦しい、違和感を感じる場合、褒める行為を使用して攻撃されている可能性があります。
褒められたことに対する悪態は自己防衛の意味があり、嫌悪を感じる場合には大切です。
褒められて嬉しくないことには、“褒める”使い方の逸脱による攻撃作用からの自己防衛があり、攻撃でなくとも単純に嬉しくも何ともない結果があります。
攻撃されていなければ悪態をつく必要はありませんが、嬉しくも何ともない褒めとは一体何なんでしょう?
両者の合致がないと嬉しくない
褒める意味を知らない使い手、褒められる恩恵を求める受け手がお互いに別々の認識をしていると、褒められても嬉しくならない結果が起きます。
褒める時には褒める側と褒められる側の合致が必要です。
褒めることはとても難しく、「褒めたらこうなるだろう」「褒められたらこうなるはずだ」と思い込みや決め付けなど、褒める行為をルール化していると、両者が合致しずらくなります。
褒める行為は発信側スタート。受信側が事前に褒められるルールを相手に押し付けることは困難ですので、褒めて相手を嬉しくさせられるかは発信側が全てを担います。
褒める人が両者の不合致を作らないように褒めることを要するため、相手をしっかり認識して、褒める意味を理解していることが求められます。
さもなくば不合致が起きて、相手は嬉しくなくなります。
褒められて嬉しいかどうかは、褒める側に全てがかかっていると考えられます。
褒めるとは技(魔法)
褒めるとは教育や他者からの植え付けにてインプットするため、自分の理解がなく、他者から言われたことだけを情報として持ち、正当化してルール化します。
「褒めれば相手は喜ぶもんだ」「褒められれば嬉しいもんだ」となります。
自己肯定感が低いと褒められても嬉しくない自分に疑問や不安。プライドや見栄が強いと自分の望む点を褒められないと嬉しくないと制限。
褒められる側が“褒められた結果”を自分のために見出そうとします。
ルールが前提にあることで褒める行為の使い方が多様化し、利益追求、価値見出しとして、常に自分の喜びや利益を中点とした褒めの舐めまわしが起きます。
しかし、リアルはちょっと違うかも。そんな内容がここの主旨です。
リアルはどんな様子か見ていきましょう。
褒める側が全てを担い、褒められる側は受けるのみ
褒めるとは技(魔法)。褒める側が全ての効果や作用を握り、褒められる側はそれを受けるのみです。
- 褒められて嬉しいのは、褒める技を上手く使えているレベル高め
- 褒められて嬉しくないのは、褒める技のレベル低め
- 褒められて気持ち悪い、苦しいなどの心地悪さを感じる場合には、そもそも褒められていない
褒める行為をルール化している褒められる人、同様にルール化している褒めてくる人が揃うと、褒める行為の不合致が起きます。
褒めた結果を自分の利益(納得や満足)にしようとする認識があり、お互いに褒める行為の意味を知らない可能性が潜みます。
訳わからない話になる前に、褒める行為の意味をご覧ください。
褒める効果
:相手を称賛して喜ばせる
:モチベーションを与える行動動機増長
※効果が多く、相手が嬉しいと思えば思うほど、褒めるレベルが高い
ゲーム風がわかりやすいかと思いますので、少しお付き合いください。
褒めるレベルを上げないと、相手を喜ばせられない
褒めるに偉いもなにもありません。
殿様が、「そのほう、褒めてしんぜよ」
「いや、別にいいっす」「褒めるなら嬉しくさせてね」とこんなものです。
褒めてくれるから有り難いなんてことはありません。褒めて嬉しくされるから有り難いとなります。
褒める効果があるから、感謝を抱けるというものです。
褒めるからにはレベルを上げないと効果発動がありません。むしろ褒めることで相手の時間を使い、会話にもならず、「えっ、これって何の時間?」と。
「いや、あのー、今私は褒めたんですが…?」
「だから何やねんっ、レベル上げてー」と。
随分褒める側に手厳しい話ですが、褒めたいから褒めるので、褒めなければならないなんてことはありません。
褒めるのは義務ではないため、褒められるか否かが問われる行為
例として親子関係での褒めがあります。
幼少期は自己肯定感の高まりが自信や自尊に、同時にスキンシップが愛の理解と育みに大きく関わることが教育や心理、過去の実験等から知られています。
「子供を褒めなければ」以上に、「褒めてあげたい」という気持ちがあり、自然と親から褒める行為がなされ、熟練されればされるほどに褒める意味が正常化して効果増し、子供のためになります。
会社のチームなどでも誰か褒める人がいればモチベーション左右となり、より活力的に成果や結果をもたらす力となります。
リーダーなど全体を統括し、認識力と洞察力を持つ人が行うことで、業績に大きく関わるため、褒められる(相手を喜ばせられる)か否かを問われる褒める側が重要な行為です。
※褒めるために大切な洞察魔法は、【力の根源案内】洞察力がある人の見ている世界とは?特徴と鍛え方 をご覧ください。
褒められて嬉しくないのは当然かも
褒められて嬉しくないのは当然?
褒められて嬉しいかどうかは、褒めるレベル次第であることから、褒める人がどれほど貴重な存在かがわかります。
褒めることは教育にて教え込まれました。
「人間は褒めると伸びるんだよ」
「人を褒められることはスゴイんだ」
しかし、実際に褒めるとはどういうことか、本人が経験しなければ育まれません。初めは誰しも褒めるレベル0スタートです。
褒められたことがなければ人を褒めることは困難
レベル0からのスタート。
親からよく褒められて育った人はスタートダッシュします。
褒められる人から褒めてもらう経験にて褒める意味を体感し、自ら育みます。
本当の意味で褒められなければ人を褒めることは困難です。
学校では、褒めるレベルがどうとかふざけたことを教えませんし、私は実際に褒める人に出会うまではこのような理解に気づく由もありませんでした。
「類は友を呼ぶ」というように、私達人間は同じような類、波動、認識にて引き寄せられ、取捨選択されて関わる人が決められていると考えられます(潜在的、直感的必然)。
褒められる環境が少ない人は褒める魔法を知らない人同士の集まりになり、褒められて嬉しくないのは当然かもしれません。
褒めるを自分のために使用する場合、褒めるレベルは限りなく低いので、相手を嬉しくさせられません。
実際には褒められていないので嬉しいはずがない
褒めているつもりの人はとても多いと思います。私自身も褒める意味を知るまではそうでした。
「そんなことができるなんてスゴイよね」
「こんなこと私にはできないよ」
褒められます。
「ふーん、で?」とこんな反応になってしまうのは当然かと、私は思ってしまいます。
なんせ褒められていない。
褒められていれば嬉しくなります。自分を認めてもらい、肯定してもらい、称賛してもらったら嬉しいものです。
嬉しくなければそれが答え。褒められていません。
褒める行為を使用して自らの価値や意義を見出そうとする人もおり、いくつかのパターンがありますので一覧でご覧ください。
- 相手を優越させることで自らを劣等化し、自己否定、自己憐憫という求めるものを手に入れる褒め
- ルールに則って褒めることで自己評価を高め、他者に披露して承認欲求を満たす
- 親、役職など自らの立場に見合った義務や、自己納得するために、「私は、ほ・め・た」という確証を得る
- 「これまでできなかった褒める行為ができた」と他者の存在を利用する褒め
- 褒めて相手に利益を与えたと、損得、恩徳計算にて自らを追われない立場にする策
- 「へぇ、やるじゃん」と上から目線で他者が劣等者であることを明示し、自らの価値を強引に高め思い込む我欲、マウント
- 褒め続けることで隙を作り、弱味やつけ入る隙を狙う支配・コントロール欲
- ゴマをスリスリして他者肯定に勤しみ、自らが否定される恐怖回避と同時に、心理的に他者から恩恵を得ようとする接待
人それぞれにさまざまな策や利用を練り練りしている褒めがあり、我欲と言われるエゴからの欲を満たそうと褒める対象を利用します。
嬉しいはずはありません。
褒めるという外枠の着ぐるみモンスターですので、最悪見えない攻撃をされて、気持ち悪い、苦しいと思うことになりかねません。
※人を利用する人の詳細は、人を利用する人の末路に闇と光│利用される人との相互関係にカルマ有 をご覧ください。
褒められることを認めたくない人の心理
嬉しくないことには理由がありますが、自ら理由を作る人もいます。
嬉しくないとは別で、嬉しさや喜びを認めたくない心理があります。
- 自己肯定感の低さ
- 自己否定癖と恐怖対処不可状態
- 見栄が強い
- 完璧主義
- 他も自らも支配する
- ‥‥
「称賛は己が認めることのみ受け入れる」という心理があると、褒められる行為を認めないことが起きます。
せっかく褒められて嬉しくなるチャンスも、拒否認識にて掻き消してしまいます。
自らが喜び嬉しくなることを認めず、嬉しさをもらったことでアドバンテージを取られるかの如く思い込み、褒められる効果を掻き消し、納得のいく箇所を定め、自らの思うようになる状態のみを求めてそれ以外は認めず。
このような心理があると、引き寄せられる人や関わる人を無意識に制限してしまい、本当の意味で褒められることが少なくなります。
褒められると起きる内情ダンス
褒める人は絶滅危惧種、レアキャラです。
私が褒める人に出会ったことで明確に体感したことは、褒められることを認めない心理があっても、褒める技の効果が強ければある状態が表れます。
内情ダンス、踊ります。
自分の中で隠したり抑制したり、誤魔化しているものがフツフツと湧き上がる情動です。
褒められると自分の内側で戦いが起きます。認められないとか嬉しくないとかは吹っ飛び、素直になるか否かの選択が起き、ある感情が生まれます。
「恥ずかしい」
褒められる人の褒めはシンプルに嬉しくなります。認められない心理があると戦いが起き、抑制する結果として恥じらいが表れます。
頑張って素直にならず、自らを抑制した状態。恥ずかしい感情を抱くと褒める人が脳裏に残り、気になります。
褒める人は好かれます。
褒める意味を知る人々
褒められることを認められなかった私は、ある日褒めるレベルの高い魔法使いに出会いました。
USAアリゾナ州からアラスカへ向かう旅の途中でした。
出会ったのはダウン症の女の子。
お母さんと二人で一緒にいました。
「スゴイね」
この一言でした。
号泣。
全てを崩壊され、素直さを抑制する心理はドバーンとダム崩壊、ドッパーン!
「褒めるって、気持ちなんだ」と体感した瞬間でした。
あそこまでレベルが高いと、抑制なんてちっともできませんでした。その後、ダウン症や知的障害者の方々と出会う機会が多かったために、褒めるレベルが高い人の脅威の効果を知ったしだいです。
褒めるとは、相手のために褒める気持ちの伝授
褒める人から教えてもらった褒める方法は、完全に相手のために褒めることです。
ダウン症や知的障害者の方々は自己愛のおすそ分けという具合で、純粋に溢れた大きな気持ちを授けてくれる体感があり、それ以上の褒め効果を体感したことはありません。
気持ちの大小は人それぞれですので、一般的には洞察から相手の褒めポイントを掴み、相手のためを思って使用する思考的な方法になると思います。
ロジカルな細微認識があり、目の前の人を理解し、その人の立場で物事を考える他者認識の育みがあり、モチベーション向上と喜びを与える目的を持って効果発動。
このように“褒める”と言っても違いがあり、褒める行為や意味を知り、育みや経験にて思考と気持ちを組み込めるレベルがあると理解しています。
- 気持ちのみで褒める
- 思考を組み込めて気持ちを入れて褒める
どちらにしろ喜びを与える効果がありますが、気持ちだけで褒められると相手を想う愛が伝わり、本当に魔法のように感じる力があります。
※褒められたい心理については、【危険で大切】褒められたい心理│疲れた時に見直す承認欲求の使い方 をご覧ください。

褒められても嬉しくない まとめ
褒められても嬉しくない理解からわかるのは、褒めるとはとても難しいことであり、本当に褒められる人は少ないことです。
実際に褒めてもらう経験が少ないと、褒める知識が乏しく、褒める意味を理解できないために育みが困難です。
もし褒められて嬉しい気持ちになる場合、相手をご確認ください。褒めるレベル高めです。
褒める人は相手を敬い想う気持ちがあり、愛があります。
褒める行為は実際に褒められ、知識をもらい、経験を重ねることで構築される人間味であり人間力だと思います。
褒める人が少なければ、褒める行為は外枠のルールとなり、何が褒めなのかに対して疑問を抱かなくなる違和感の流しが起きます。
「褒められても嬉しくない」と感じることは、とても重要な気づきです。
褒めることで他との共存社会での調和を作り、個々に対しての喜びやモチベーションを与えることは行動を促す活力となり、チームワークの源にもなります。
嬉しくないと感じる人は、褒める意味を知れる人だと思います。
褒めの体感を見極めながら褒めの意味を知っていただき、褒める側の人になる一助となれば幸いです。
絶滅危惧行為の褒め。ぜひ身近な所から褒めを使用した喜び作りを広げていきましょう。
それでは、褒められても嬉しくない理由と心理のお話を終了します。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ピン!」と来た方はぜひお試しください。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作成してもらえます
的確にわかりやすく言語化してくださるため、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください