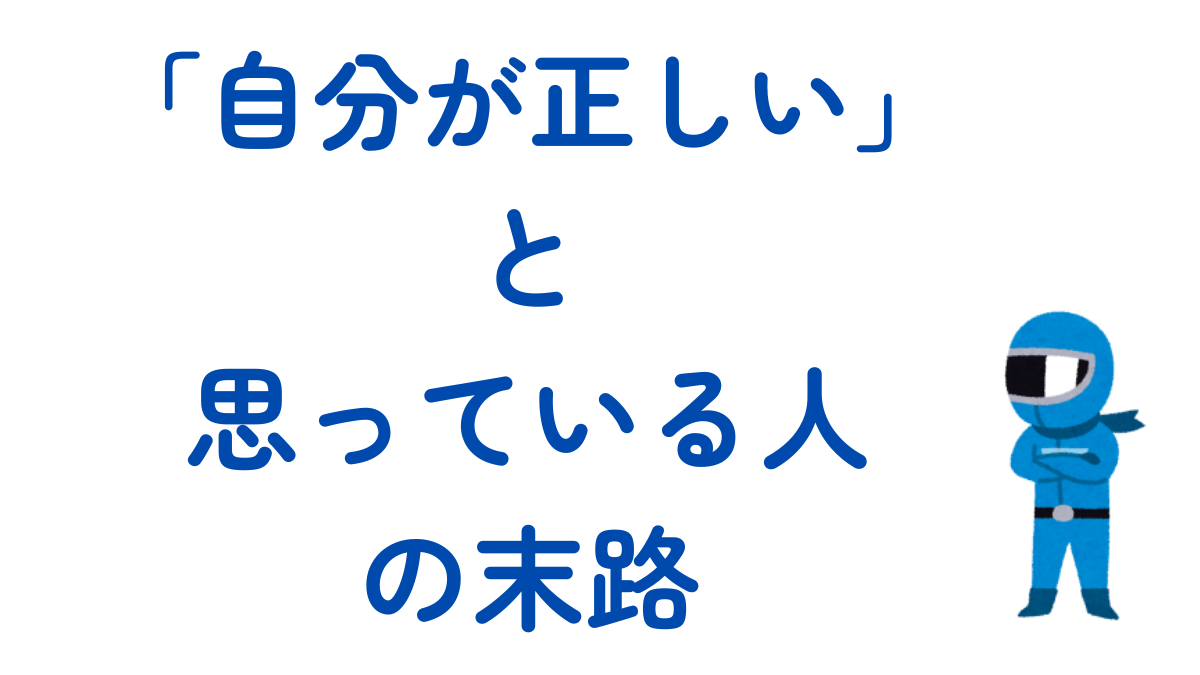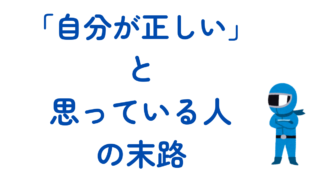【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ぜひおすすめしたい」と感じたのでご紹介です。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作ってもらえます
「なんでこんなにわかるの?」と思えるほど的確で、わかりやすく言語化してくださり、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください
信じられる確証がなければないほど思い込みたい、自分の正しさ。
心理には、心を護り、自らの価値を見出したい目的があります。
このような人と関わると、めんどくさいので少し疲れてしまうかもしれません。
ここでは、自分が正しいと思っている人の末路と、関わる際の対処法をお伝えします。
- 自分が正しいと思っている人の末路を知りたい
- 正当化と思い込みが激しい人の対処法を考えたい
対処法は自分が正しいと思っている人を知ることがポイントになりますので、内情を紐解く内容となっております。
表舞台だけでなく裏側を知ることで、気楽に関わる一助となれば幸いです。
自分が正しいと思っている人の末路

自分が正しいと思っている人の末路7選
この性格によって自らデザインする末路を順番にご覧ください。
1,自分を信じられなくなる末路
自らを自らで信じられないために、自分以外の他(人や常識や社会性など)によって信じられる材料を得ようとする行為が、正当化や思い込みや我の貫き(主義主張)です。
自分が正しいと思うのは自由ですが、貫き続けることは自分そのものと向き合わず、振り返らない現実逃避かもしれません。
向き合うべきことから逃げ続ける方法でもある正当化ですので、自分をどこまでも信じられなくなっていく末路を自ら作ります。
2,周囲の目や反応や評価を気にする末路
周囲が気になってしようがなくなり、周りの反応や評価が主体になる末路。
「自分がなくなる末路」と言えそうです。
周囲からも自分が正しいと思ってもらいたいので、気にする評価は「良いじゃん、うん正しいよ、それが勝ち、優れている」と認めてもらうこと。
しかし、周囲を気にしている自覚は自己評価を下げてしまうので、「周囲なんかどうでもいい」と極端に気にしていないように振舞います。
ストレスは常にたまり続け、動物の癒しが必須になり、年々一人では自己保持ができなくなっていきます。
3,急に何もかもに飽きる末路
自分が正しいと思うことは行動や努力の動機になる利点があります。
「英語を話すには独学のこのやり方が一番なんだ!ペラペラペラ」と努力し続ける。
一方、ある程度の段階に辿り着いた時、行動や努力の動機が瞬く間に消え去り、「私って何のために英語話したかったんだっけ?ま、どうでもいいや、ボソ」と燃え尽きます。
やる気を失い、何もかもに飽きる末路です。
4,否定をやめられない末路

自分が正しいと思いたい欲が強ければ強いほどに、他を比較対象にした否定が増えます。
獲物を見つければ食い付くように否定する、そんな努力を続けた結果、否定が趣味になり、嫌われることが当たり前になります。
それも正当化すると魔女になるという噂。
否定をやめたくてもやめられなくなる末路、「これが私なんだ!」と怒りだします。
5,周囲から人が離れていく末路
自分が正しいと思い続ける際の我の貫きにてエゴは日に日に増していきます。
プライドを強め、見栄を張り、自惚れて顎から下を見なくなり、見下しやモラハラ、そしてマウントが激化します。
まるで腫れ物、周囲に人がいなくなり、誰からも好かれず、関わりを拒まれ、嫌悪感を抱かれる末路です。
6,メンタルの弱さを誤魔化し続けなければならない末路
正しいと思っている人は思い込みの自己世界で生きる特徴があります。
何もかもを思い込み、それが思い込みではないと思い込むために正当化を目論見、一般的な意見、社会的な意見、論理的証拠、科学的根拠などの否定されにくい(または共感を得やすい)情報を重要な材料とします。
「他」をバックアップにして安泰を得る状態は、メンタルの弱さを隠すため。
「私は否定されている」と少しでも思えることがあれば、徹底的に相手を否定して自らを正当化する、そんな自己防衛意識が過剰に太ります。
本質に目を向けず、決め込み、他を否定し、自らを上だと思い込むことで事実を誤魔化す在り方であるため、現実を隠し続ける義務が課せられます。
現実を認めることが難しくなり、嘘と誤魔化しの多用をやめられず、現実から逃げ続けなければならない末路です。
※見栄が強くて謝らない人の末路は、【一旦人生ストップ】謝らない人の末路は待機条件 をご覧ください。
7,自分の欠点を改めない末路

「ここまで来たらもう戻れません」という状態。
反省なく、後悔はあったのに誤魔化してなかったことにしました。
過去を見つめず、自らを見つめ直す機会を放棄してきた因果は、自らで自らを改められない末路。
欠点だとわかっても変えられないため、誤魔化しや自分への嘘をやめることはできず、あとはそれをいつまで続けるか、そんな自分との戦いが続いていきます。
以上、自分が正しいと思っている人の末路でした。
末路ポイント:自らを肯定したい、傷つきたくない欲
「それでは自分で自分を認め、自分で自分を護りましょう」となりますが、それができないために自分が正しいと思うことで欲を満たし、解消します。
正しいと思い込むことで自らの在り方を変えなくても納得できます。
残すところは相手を変えるか、相手がおかしいと批判するに限定されます。
- 自らを肯定したい欲
…相手を変えて自らの正当化を貫いて欲を満たす - 傷つきたくない欲
…相手を批判して自らに非がないと認めて欲を解消する
これら我欲によって他に求める承認欲求を満たし、他によって不安と恐怖の解消を果たせるのが、自分が正しいと思う行為です。
我欲はオラウータンのように檻の中で暴れるので、この暴れるオラウータンと戦い続ける義務化が末路のポイントになります。
※正当化の別スタイル『マウント』の末路は、「何がしたいの?」マウントを取る人の末路は悲しき人生ストーリー をどうぞ。
自分が正しいと思っている人の対処法

対処ポイント
正しいと思いたいのは私達人間にとって自然なさまでして、おそらく誰しもにあると思います。
自分が正しいと思っているのは当然だとして、関わる上での問題点になりえるのがこちらの二つです。
- 自らを肯定したい欲
…相手を変えて自らの正当化を貫いて欲を満たす - 傷つきたくない欲
…相手を批判して自らに非がないと認めて欲を解消する
我欲を貫くために妥協しない、一生懸命頑張って努力するのが自分が正しいと思っている人です。
自らは折れず、相手を折らせて押し切るまでやめる気はありません。
押し切ることが我欲の満たしと解消の利益であるため、これ以上に利益を与えなければ相手は変わりません。
給料1万円では何を言っても自分のやり方でしかやろうとしませんが、「10万円あげるからこっちが言うやり方でやって」と言えばうなずくイメージです。
この利益をお金ではなく、[承認欲求を満たす・不安と恐怖の解消]にしてあげるのが、対処法のポイントとなります。
ポイントを主軸にした対処法を見ていきましょう。ご参考になりそうなものがあればお役立てください。
※自分が正しいと思うために否定する心理は、否定ばかりする人の心理と対処法│否定癖は「エゴ」を知るチャンス をご覧ください。
自分が正しいと思っている人の対処法①:「どうして関わるの?」の把握
言わずもがなかもしれませんが、自らの利益のために正しさを押し通す人は、自らのために他者を利用する人です。
関わる意味は一体何なのでしょうか?
仕事上などやむを得ないなどでなければ、苦行やボランティアや自己犠牲という状態になり得ますので、今一度関わる意味を対処前に把握しておきましょう。
対処法②:心理を知って距離感を保つ
仕事など関わる意味がある場合には距離感を保つことで対処します。
否定され主張され、勢いや罵声で押し切られると飲み込まれ、相手主観になって距離感を保つことはできなくなります。
距離感創作には相手の心理把握が重要になるので、これまでの内容で思い当たるものがあればその目線で相手を捉えます。
相手を俯瞰して捉えられるので、意見を押し通してきたり否定してきた際には、「これが世に言う承認欲求だ」「不安と恐怖がある状態なんだ」という見方ができます。
相手の把握は自分を優位にさせるためではなく、相手の我欲行為に飲み込まれないで自分主観をキープするためです。
※決めつける人の対処法は、決めつける人の心理と対処法【クレーマー的内情の把握】をご参照ください。
対処法③:押し付けない、否定しない
距離感を保ち、少し余裕ができた時にする対処法です。
自分が正しいと思っている人を変えようとすることは、相手を否定して価値を下げ、評価しない行為となり、相手は傷ついてしまいます。
思い込みの世界にいるため、相手を否定するつもりがなくても自らの意見を通せなかったり、少し意見と違うことを言っただけで、「反論されているムムム」「自分を護らないとムキー」と強く否定してくる可能性があります。
客観的に相手を捉える目線にて実情を少しずつ把握していった時には、相手の心理に重きを置いて、「否定されている・反論されている」と思い込ませない言動にて関わります。
言葉使い以上に敬い尊重する気持ちで、相手の自尊を穢さない関わり方が大切です。
無理矢理肯定してあげる、めんどくさいので一時凌ぎのために見栄えだけ良くしてあしらうなどは、無意識に相手を否定して恐怖を与えてしまいますので、相手を理解して関わり方に敬いや受け入れを増やすことが大切です。
対処法④:軽い肯定で受け流す
「この人には危険性がない、信頼できる」と思われると関わりは本当に楽になります。
自分が正しいと思っている人と関わる際、穏やかに接し、押し付けも決め付けもせず、受け流すように肯定するとノーストレスで気楽なものになります。
このために、軽い肯定で受け流す関わり方をします。
支離滅裂でメチャクチャなことを言っていても、「うんうん、そうなんだ」と聞いてあげます。
※真面目に聞く必要はないですが、テキトーにあしらってはいけません
具体的には、その人のしてきた行動や努力、成果や結果をその人として見てあげる、否定しない。
「それはすごいね!」とあからさまに肯定するのではなく、「あー、そのやり方は大切だろうね」と受け流すように肯定するのが私の経験上おすすめです。
相手の性格や価値観、メンタルや過去、生活環境や幼い頃の環境、家族との関わりなど多岐に渡る相手の理解があるほど、この対処はしやすくなります。
※真逆の対処法は、嫌いな人をこらしめる方法パート②【対象:自己中、ナルシシスト】をどうぞ。
自分が正しいと思っている人の末路と対処法 まとめ
メンタルの弱さとは、弱さを見つめず、変化させずに我を貫くことに本質があります。
思い込み、決め付け、主張するように正しいと貫き、心身を護るための自己防衛を意識して、絶対に曲げられないかのごとく剣を振りかざします。
しかし、錆びだらけの剣はパキンと軽くいっちゃうことを本人も知っているからこそ、正当化と思い込みを激しくしていきます。
正しいと思いたい人にはそうなった過去があり、そうしたい価値観と生き方があります。
全ては後付けの記憶と経験によって構成される私達人間は、誰しもが未完成で未発達で未熟者です。
正しいと思うには間違っている理解が必要になり、どちらも知ることで見えるのはなんでもいいという答え。
誰しも自分が正しいと思っています。そのために、正しいと思っている人がちょっとおかしいと思ってしまいます。
その人にはその人の正しさがあり、他に押し付ける意味があります。
そんな人とは関わらない。
これが最もシンプルな対処法ですが、関わる意味がある際には相手を知り、自らを知り、関わりにある人間の深さを楽しみましょう。
適当に気楽に、そんなお話がご参考になるものであれば幸いです。
ありがとうございました。
【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ピン!」と来た方はぜひお試しください。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作成してもらえます
的確にわかりやすく言語化してくださるため、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください