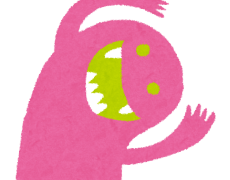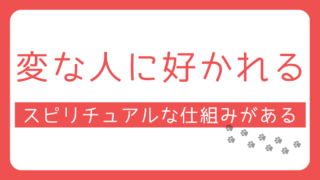【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ぜひおすすめしたい」と感じたのでご紹介です。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作ってもらえます
「なんでこんなにわかるの?」と思えるほど的確で、わかりやすく言語化してくださり、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください
何かと助けてもらえる人を見ると一つわかることは、助けられる時の着眼が利益ではなく、その時間や空間ということです。
これは助けることの意味を知っているためです。
助けてもらえる人の特徴を見ると、助けてもらえる理由が明確に表れます。
それは、助けてもらえない人との天と地の差を作り、「本当に同じ世界に生きているの?」と思いたくなるような違う認識が両者にあります。
ここでは、助けてもらえる人の特徴からわかる助けてもらえる秘密、そして助けてもらえない特徴と理由をお伝えします。
ご自身を理解する参考になれば幸いですので、お助け行為に見える人間性を見ていきましょう。
Contents
助けてもらえる人の特徴

助けてもらえる人の特徴一覧
- 一つ一つの行為に本気で取り組む
- 嘘をつかない
- 素直
- 独りでどこでも行く
- 他に執着しない
- 切り替えがはっきりしている
- 意志と信念が明確
- 環境適応能力が高い
- 頑張り屋さんに見える
- どこか抜けている可愛さがある
- 人を変えようとは絶対にしない
- 心に余裕のある豊かな人を引き寄せる
- 助ける行為の意味を知っている
助けてもらえる人の特徴13選
それでは特徴を順番にご覧ください。
1、一つ一つの行為に本気で取り組む
どんな行為でも手を抜いたり、テキトーにあしらいません。
テレビを観れば本気でふむふむ言ったりゲラゲラ大笑い、ご飯は何を食べれば「最高、うえっ」などと明確に認識し、行為に集中します。
本気で自分の行為に取り組んでいる特徴です。
自分自身に対して真剣であることを意味し、我慢や忍耐とは別に、あらゆる行為に一生懸命である姿を周囲は見ます。
2、嘘をつかない
助けられる人は自分に対して真剣で本気でため、嘘をついて自分を誤魔化したり、現実に対して見て見ぬ振りをしません。
起きる現実を認めることにも本気で真剣、嫌なことにも立ち向かおうとする懸命さがあります。
自分の気持ちにも現実にも嘘をつかない誠実さが周囲に伝わります。
3、素直
嘘をつかず、事実を認める素直な人間性です。
嬉しければ本気で喜び、嫌であれば本気で嫌がります。
「嫌がると相手に申し訳ない」という気持ちがあれば、出さないようにします。
しかし、嘘をつかないので明らかなぎこちなさが顔や仕草にありありと出て、「絶対嫌なんだ」と確実にばれますが、そこに微笑ましくなる素直で正直な様が露呈し良い印象を与えます。
演技していれば、「演技中です」と顔に書いてするようなもので、何をしても素直さを周囲に与えます。
4、独りでどこでも行く
助けられる人は集団に属しません。
仲間など集団でいることはありますが、単独で行動できないというのが皆無。
海外でもどこでも独りで行っちゃいます。
独りなので困っている時に周囲が助けやすい状態にいます。
5、他に執着しない
助けられる人は初めに自分で何とかしようとします。
他に頼ることはあっても執着してすがりません。
素直なので、困れば困っていると伝えたり助けを求めます。
しかし、執着しないので一方的に助けられるのではなく、助けられる中でも自分に何ができるか考えて行動します。
6、切り替えがはっきり
甘えられる時は大いに甘えます。
甘えた後は切り替えがスパッ。
甘えられた結果から人を利用するようになったり、甘え続ける依存など、心の弱さがありません。
助けられる時は助けてもらい、普段は普段の生活、人を助けられる時は助ける。
何か一方に偏り他にもたれかかって生かされることがなく、常に他者との共存の中でその場その場を柔軟に寛容的に切り替えます。
7、意志と信念が明確
自分を明確に認識しているため、自分の力だけで生きる、他者の力だけで生かしてもらうなどの一方通行がありません。
どんな状況でも環境でも、その時その時に必要な関わりや出来事を認識して、自分にとって自然な状態に従い流れるように適応します。
明確な意志と信念があり、「自分を大切にすること」は何が何でも貫きます。
8、環境適応への努力と能力が高い
押し付けや干渉を他にしない特徴でもあります。
場所や関わる人々によって価値観や認識の仕方を変えます。
海外へ行けばその土地の風土や文化を尊重し、我を押し付けません。
どこに行っても素直に環境適応努力、東京にいれば東京の暮らしを、アマゾンに行けば泥川で魚を捕まえ、インドネシアに行けばいかだを作って暮らし、アフリカに行けば川で洗濯します。
9、頑張り屋さんに見える
環境に適応しようとする態度、素直さ、一つ一つに真剣に取り組む様、執着せず、自分を持って甘える時は甘える。
そんな姿は周囲に、「この人は誠実で頑張っている」という印象を与えます。
頑張りは苦労や我慢ではなく、一つ一つの起きることに意味を見出し真正面から関わる一生懸命さに表れ、賞賛を称えたり協力したいと思える人によって助けてもらえます。
10、どこか抜けている可愛さがある
助けられる人は若干のポンコツ感があります。
どれだけ自立して自分を持ってシャキッとしていても、「おろ?」と気が抜ける完璧ではない様があります。
ご飯を食べているとボロボロこぼしたり、しゃがんで一生懸命作業している時に半ケツ出ていたり、大事な時に寝坊したり、お化け屋敷は絶対に入れなかったり。
欠点と思えることも隠さずに正直にさらけ出すので、愛らしさやチャームポイントとして可愛い印象を与えます。
ギャップとしての好印象も与え、人に好かれる理由にもなり、「助けたい」と思わせる個性です。
11、人を変えようとは絶対にしない
助けてもらえる人の大きな特徴は、人を変えようとしないことです。
他者一人一人の存在を尊重し敬っているためで、執着しない理由です。
干渉して他の認識を踏みにじり、否定して批判して変えさせることはなく、アフリカに行けば川で洗濯することを嫌々するのではなく喜んでします。
人だけでなく土地の考えや理解、動物や虫や植物、自然や地球に対する敬いがあり、そのものを尊重して邪魔や抵抗を作りません。
12、心に余裕のある豊かな人を引き寄せる
敬いの人間性は行動など外的に見える部分から良き印象を周囲に与えますが、同時に内面から醸し出されるオーラや波動として伝播するため、心に余裕のある人を引き寄せます。
スピリチュアルな認識として、高波動の同調作用によって“助ける意志”を持つ心の大きな人を呼ぶ仕組みがあります。
困っている人を助けようとする人は、経済的に余裕があるだけでなく、精神面での心の余裕として他者に喜んでもらおうと敬う人間性があります。
豊かな人を引き寄せるのは、助けてもらえる人が豊かな心を持っているためでして、心の余裕は見えない所で引かれ合う糸を紡ぎます。
13、助ける行為の意味を知っている
無意識の人が多いと思いますが、助ける行為の意味を理解しています。
助けられる際の焦点は自分に起きる結果ではなく助けてくれる相手、または助ける行為や時間や空間そのものにあり、人と人の育み、調和、営みとして、助ける本質的理解があります。
以上が、助けてもらえる人の特徴でした。
※守ってもらえる人の特徴は、【守られ人の心得】ご先祖様に守られている人の特徴11選+方法 をご覧ください。
助けてもらえる理由

助けてもらえる人は強い人
助けてもらえる人の特徴から、“この人を助けてあげたい”と思わせる理由がわかります。
そもそも、人を助ける人は助けることで自分ではなく相手の喜びや利益を見出そうとします。
そこで助けるという行為を使って、自分の価値を見出したり肯定材料としたり、恩を売ったり徳を積んだりという自らの利益や損得勘定をする人もいます。
それは人を助けるのではなく、人を助けるという行為を利用して価値を得るということなので、人を自分のために利用することです。
助けてもらえる人は利用されることはなく、純粋に助けたいと相手の喜びを求める人から手を差し伸べられます。
一方的に助けられるだけでなく利用されない人間性があり、助けられる人は強い人です。
助けてもらえる人は強い人間性を持つために助けられる
※利用ではなく助けようとする人を引き寄せる同調となり、出会う人の人間性や人格が違う
どんな大衆の面前で困っていても、そこで助けてくれる人は一部です。その一部の寄せ付けが多い人が何かと助けてもらえる人でして、そこには“強さ”という理由があります。
強いとは、自分の確立度による利用されない様です。
それは、相手に執着されない意志の強さでもあり、他に執着することもありません。
言い方を変えると、恐怖という自分の嫌がるものを拒否して逃げ続けるのではなく、恐怖に打ち負けない心の強さ、精神性の高さです。
助けてもらえる人は人に好かれる
助けてもらえる理由には、助けたいと思ってもらえる好印象があります。
一生懸命な様など多くの助けたいと周囲に思わせる姿があるので、もはや「助けてあげる」ではなく、「助けさせてくれよ」という人もいます。
喜んで助けたいという印象には、好かれる人格があります。
その一つに上述の“強さ”があり、他にも素直さから来る柔軟さがあり、押し付けずそのままを尊重する敬いがあります。
同時に、他に執着しないハッキリした様が、助けてもすがられないという安心感を与え、心おきなく助けられる動機を与え、全力で助けさせるサポートになります。
助けたいと思わせる印象を周囲に醸し出すことで、周囲から助けられる結果があり、人に好かれる人間性を持ちます。
※もらい物が多い人の特徴は、なぜだか物をもらう人の秘密【スピリチュアルな仕組み&人徳】 をご覧ください。
助けてもらえる秘密
既にお気づきかもしれませんが、助けられる人は自らが、「助けたい」と思わせる動機を周囲に与えています。
助ける側から始まっているのではなく、助けられる側から“助ける”という行為に至るまでの道のりを示しているという。
言い方を変えると、「助けてあげたい」「OK,それじゃあ助けてください」という、逆の順番が作られています。
そんな見えないやり取りがあり、「この人に協力したい」と思ってもらえることに秘密があります。
助けられる人は、「なんとかこの人のためになりたい」「この人に協力したい」「喜んでもらいたい」と思ってもらえる人です。
そこにはそのように思える心豊かな人と出会えるかどうかの“引き寄せ”があり、自分自身がそのような素敵な人達に値する人である前提として、上述の“特徴”があります。
そして、「助けたい」と思ってもらえる秘密として、大きな理解がこちらです。
「この人と関わると嬉しくなる」という気持ちを与えること。
助けてもらえるのは、助ける人の心に喜びを与えているから
助けられる人自らが発端となる行為が、“助ける”です。
助けることは助ける相手に利益を与え、助ける本人は自分のしたことや、相手が喜ぶことに利益を感じます。
その“相手が喜ぶこと”をモリモリ増やすのが助けてもらえる人です。
「この人を助けて良かった」と思ってもらえる在り方を無意識に助けてもらえる人はしています。
それが、一緒に居る時間を楽しんでもらい、関わって良かったと思える記憶を与え、助けたことを後悔させないことです。
それらを行為にするとこうなります。
- 笑顔
- 敬い
- 一緒の時間を共有する
- 助ける行為で人と人のプラスを育む関わりを作る
- 躊躇なく素直に100%で助けてもらう
- 本気で感謝する
とてもシンプルに、笑う、楽しむ、共有する、躊躇しない、甘える、感謝する。そして全部本気というものです。
そこには、同じ時間と空間を共有することで良き関係が作られ、共に良き時間を作った記憶になり、心温かい敬いと喜びの空間になります。
この認識を持っていることで何かと助けてもらえ、自然と助けてくれる人を引き寄せ、「助けて良かった、また助けたい」と思える結果を作り、循環を作るように人と人の関係を作ります。
すいませんは言わない、ありがとうと言う
助けることで人と人の人間味ある関わりの機会になり、助けてもらえる人はその機会を相手のために具現化します。
それが、共有、話すこと、楽しむこと、笑うこと、敬うことです。自分のことだけでなく相手の喜びを“助けられること”で作ろうとします。
助けられる人は助けてくれる人の行為だけでなく、「助けたい」という気持ちを汲み取り配慮します。
それを無意識にしているのが助けられる人です。
甘える時は本気で甘えて執着しません。それは100%相手に助ける行為をしてもらうためとなり、自分も相手も喜ぶ共有が作られます。
自らが発端で助ける行為をしてもらっているため、助けられる人は「すいません」と申し訳なさそうにすることはありません。
本気で感謝して、「ありがとう、感謝しています」と伝えてお別れをする、そんな人です。
※助ける側の話については、困っている人を助ける人の気持ち│人助けする理由と心理とスピリチュアル をご覧ください。
助けてもらえない人の特徴

助けてもらえない人の特徴
助けてもらえない人は助けてもらえる人の反対をしていることがほとんどです。
特徴はこちらをご覧ください。
- 自分で解決しようとしない逃避癖がある
- 他者に執着して依存する
- 甘えるだけ甘えて終わり
- 助けてくれる人を敬わず尊重しない
- 自分の利益のみ考え、助けられる行為以外が見えていない
- 嘘をつき、現実を誤魔化す
- 恐怖に対峙せずうやむやにする癖がある
- 人や起きる現実に対して拒否や批判や否定をする
- 素直ではない
- 柔軟性や寛容性がない
- 物事の俯瞰性がなく認識幅が狭い
- 感謝、ありがとうの意味を知らない
- 押し付けや干渉して自分ではなく人を変えようとする
- 独りで行動しない、またはしても不安や恐怖で心細くなる
- 意志が弱く、他者の反応や評価を気にする
助けてもらえる人と助けてもらえない人の違い
助けてもらえる人と助けてもらえない人は真逆の人間性があり、何もかもが対極しているように思えますが、実際には大きな違いは一つしかありません。
“他に執着するか否か”です。
助けてもらえない人は執着するため、甘えて依存して離れなくなります。
助けられることを利用する人間性です。
自分一人では生きられないという恐怖から逃げ続ける人間性でして、恐怖との関わり方を見ないようにしていることに起因します。
プライドや自惚れにもなり、事実をそのまま認識せず、都合の良いようにしか物事を解釈しないようになります。
物事の認識が狭くなり、「ありがとう」の意味を理解していないのに使用するという状態になり、何もかもの知識や理解が軽薄で核のないものになります。
自分自身に核がないことを表し、他者を考える余裕がなくなります。
助けられる人と助ける人の人間模様
助けられる人がいて、助ける人がいる。
頭も心もある自分という完全な存在同士の関わりがあります。
戦いにもエゴにもなり、育みにも愛にもなり、全ては関わる人次第で作ります。
助けてくれる人が助ける行為を知らなければ、助けるは“利用する”に変わります。
同様に、助けられる人が助ける行為を知らなければ、助けられるも“利用する”に変わります。
子供は親に助けてもらえるのが当たり前だと思っても、助ける行為を知らない親が居れば助けるのではなく利用します。そして利用価値が見出せなければその行為すらしません。
そして、助けられることに己の利益しか見ていなければ、助けてくれる人を利用しようとします。
助けられない人が助けられるようになるために必要なことは、助ける行為を知ることが大切です。
助ける行為は人と人の共有と調和にて関わりを作ることです。
それは、良きことをもたらすための共同作業であり、向上や成長を育む関わりです。
人間同士の調和を作る関わり、それが助けるという行為であり、尊重や感謝を作り、良き流れを作る始まりとなります。
助けることで相手の利益をもたらすだけではなく、人同士の育みと流れに愛を乗せて関わりを作る、そんな“助ける”ことの意味を知ることが大切な気づきになります。
何だかいっつも助けられる人は、助けられて生きてきたことや、人と人の関わりの良き面を知っています。
※徳が高いから助けてもらえる詳細は、【徳を積んだ人の特徴14選】徳が高い人と低い人の違いは『自分の大きさ』をご覧ください。
助けてもらえる人と助けてもらえない人 まとめ

助ける行為を知っているかどうか、利用にするかどうか。そんな理解一つで物事の見方は大きく変わり、子供はそんな見方を知っています。
助けてもらえる人の典型は子供です。特に幼少期までの子供は助けてもらえるプロのような存在かと思います。
あの人達は、自らが愛を与えることで助けてもらえることを潜在的に知っているように生きています。
しかし、助けるの意味を理解する気もなく、人と人の関わりは利用し合うものだと認識している場合、利用価値があれば助け、価値がなければ助けません。
自分のため、困らないため、悲しまないため、自分が辛い思いをしないため。
子供は助ける行為を無意識に理解していますが、大人になれば意識的に理解できます。すると、より人の関係性がわかりやすく見え、助ける行為によって社会を作るように人と人の良き流れとして向上や成長を調和と共にもたらすことができます。
それは私達人間の力だと思います。
共に同じ方向を見て突き進む助ける行為が大きくなることで、コミュニティにもユニットにも会社にもなり、町になり国になり、皆が同じ方向を進むことが一つの大きな力になります。
それは流れであり成長であり、後世が継承を喜んでしたいと思える社会を作る意識。
全て私達次第です。何かを変えようとする押し付けや干渉はせず、助ける人と助けられる人を知ることで、人としての大切な何かが見えてくるかもしれません。
それが生きている意味であり、人とは何かの真理であり、助ける力です。
助けられる人と助けられない人の特徴から何だか哲学的なことが知れる、そんなお話が何かに役立つことを祈ります。
それでは、助けられる人の特徴についてのお話を終了します。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
【カタカムナ診断で自分を知る】
当ブログの運営をしている北斗です。「ピン!」と来た方はぜひお試しください。
 カタカムナ使命診断
カタカムナ使命診断PR:和のしらべ(PARK経由)
※一人一人にある『氏名』を個別に診断し、独自の結果を作成してもらえます
的確にわかりやすく言語化してくださるため、自分には何が大切かわかります。
さらに言霊・音・文字に含まれるエネルギーを強く意識でき、波動が明らかに上がったため、「これはぜひみなさんにも♪」と思った次第です。
結果が送られてくるのでLINE要です。
※カタカムナ自己理解、興味のある方はぜひご活用ください