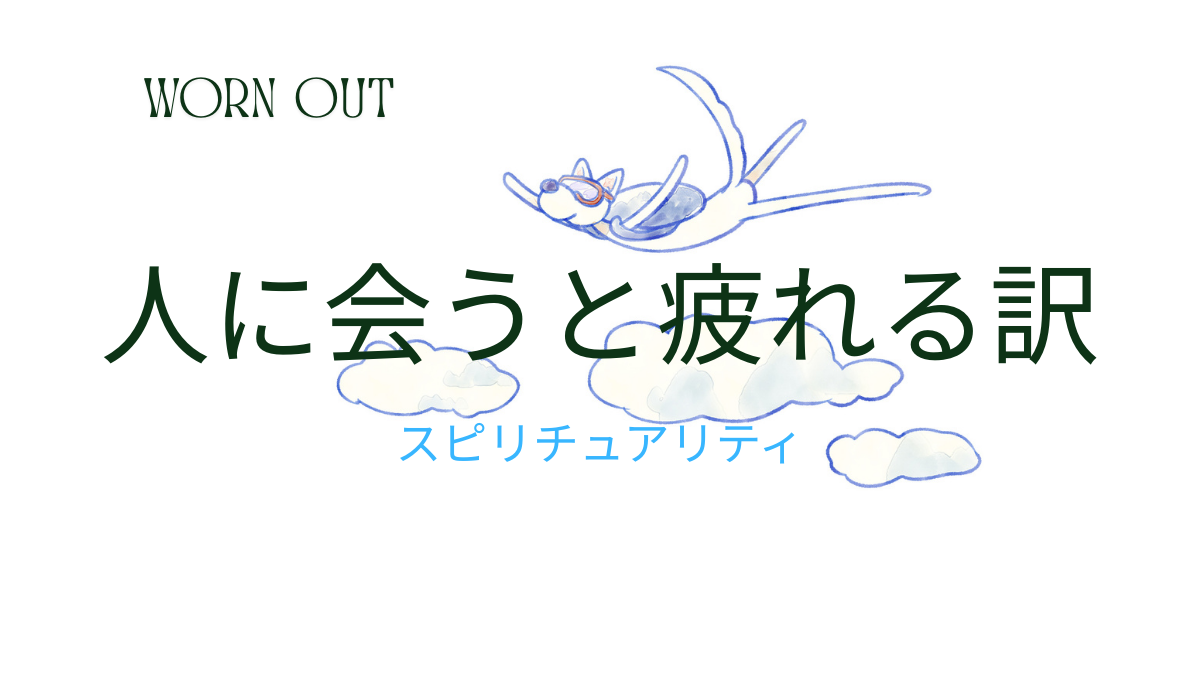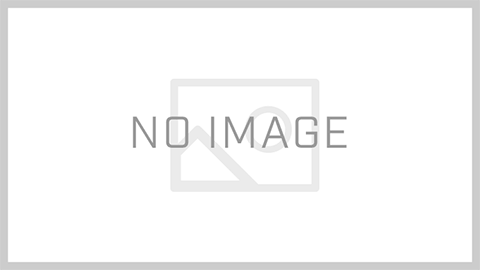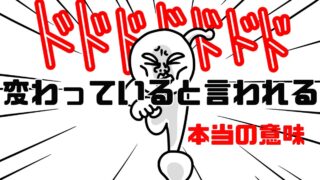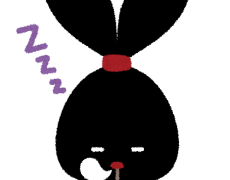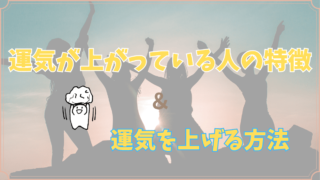ドサッ。
玄関を開けて間もなく、靴も脱がずに床にへなへなぁ。
「づぅがぁあぁれぇえだぁぁ…ポテ」
人との関りは千差万別。
楽しく元気になる人もおり、一緒にいる時はホワワァン。
一方、イライラして鼻の穴が二倍になり、力が入りすぎて目からミルクがピューと出てくる。
そして、寝込むほど疲れることもある。
生気が抜けて意識に力が入らない、生身があるか腕をつねって確認したくなる。
嫌な人なら疲れるのはわかるけど、別に嫌な人ではないのに疲れる、そんなこともあると思います。
どうしてなのか?
ここでは、疲れる事実と、改善する際の重要点を私の経験則から紐解き、言語化していきます。
- 人に会うと疲れる理由を知りたい
- 疲れないように自らを磨きたい
疲れる理由はシンプル、そして原因もシンプル。
難しいのは実行ですので、事前準備として仕組みの理解をまずは念頭に置く、そんな一助になれば幸いです。
それでは自己の深掘りに入りましょう。
Contents
人に会うと疲れる理由

敏感、繊細以上に、「我慢」
「疲れる要因ナンバーワンはこれだ!」的な回答
・繊細
・感覚過敏
・ギフテッド
・エンパス、HSP
・嫌われたくない症候群
・考えすぎ、気を使いすぎ
・相手が自分勝手なセルフチューチュー
・エナジーバンパイア、もはや人間じゃない
・上っ面だけいい人で、実は悪くて怖い人
これらは疲れやすい要因になり、自分か相手かのどちらかに着目した場合です。
ここでお伝えしたいのは、「誰かと一緒にいる」という前提ありき、関わりにおける要因。
人に会うと疲れる要因としてあげたいのは、『相互交流がない』ことです。

スピリチュアルに言うと、エネルギー循環がお互いにできていない、できない相手、できない自分の状態。
繊細以上に、相互交流のなさが疲れる要因になるお話。
深掘りしていきます。
人に会うと疲れる理由
要因の紐解き、まずは理由から。
我慢が多くなる相手ほど、一緒にいると疲れます。

例えば、猫と一緒にいる時。
「ゴロニャーニャー(お腹撫でて~)」
「仕方ないなぁ、スリスリー」
「ニューゴロロ、ピャーゴロロ(はぁ、気持ちええの~。もっとやって)」
「全く甘えん坊だ、スリスリー、よし、仕事しなきゃだから終わりね」
「ニャーニャー(やだー、もっとやって~)」
…一時間後
「もう、いいでしょ?ねぇ、いい加減にいいでしょ?ねぇ」
「パッ、スタスタスタ」。どこかに行く勝手気ままな猫。
初めは自分にも利益があった、可愛かったし。
でも次第に要望が生まれ、甘え出し、こちとら仕事ができなくなり、何も言わずに去って行きやがった、と。
『相互』がない場合、片方が喜ぶために、もう片方はその分を与えるための“働き”が起きます。
猫であれば、「はいもう終わりね」とできるけれども、人間にはそうもいかない。
評価に響く、面倒が起きる、長期的に見たら今我慢した方がいいなど、今後を見据えた計画がある人もいます。
どちらにしろ相手に我慢している状態は、相手のために自分のエネルギーを消費・浪費する働き、いわゆる仕事になります。
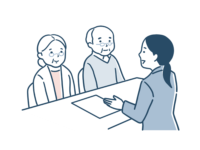
契約を交わしたい、いつでもハンコを持っておいてくれ。
「肩たたき5分やったらちゃんと100円ちょうだい、はやく」
「もうちょいやって、じゃないし、いいじゃん家族なんだからお金なんて、でもない」
そんなことをされたら我慢になる、相手のために自己犠牲したい訳でも、奉仕の気持ちがある訳でもない、そもそもそんな動機で始めていないから突然の切り替えはできない。
契約書のない仕事はブラック人間関係となり、相手が悪い人でもいい人でも疲れます。
人に会うと疲れる場合、タダ働きマインドでの我慢が多い可能性があります。
※一緒にいて疲れる対象については、【上っ面だけいい人の見えざる搾取】一緒にいて疲れる人にされていること3種 をご覧ください。
我慢が疲れるのは頑張るから

我慢にて疲れ、さらに人間関係を頑張ってなんとかしようとする場合。
[我慢+頑張り+努力]のトリプルアクセル、とんでもなく疲れます。
これを疲れなくするには、確実に成果を挙げなければなりません。
努力しても順位は変わらない、これを継続したら疲れるのは当然です。
この『頑張り』で考えたい本質があります。
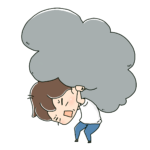
我慢できる人にとって頑張る行為は楽。
私たち人間はやるべきことが決まっている、道行きが見えると、どれだけ大変でも気持ちは楽です。
全力を注ぎ、努力している感じ、突き進んでいる感じを得られ、生きている情動も味わえます。
何もない砂漠地で、「はい、自由に生きてください」と言われて、「え、何をどう頑張ればいいの?」ともがくより。
やり方のわかっている作業にノルマを課され、「はい、明日の19:00までに完成させてください」と言われる方がいい、「え、無理だよ、でも頑張るぞ」なんてイメージです。
工程と成果が見えやすい作業などであれば、頑張ることに意味も目的も見出せますが、
人間関係には答えがありません。
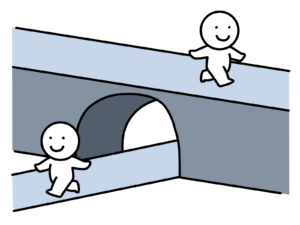
砂漠地と同じ、自由があり、「お互いに決め合って初めて答えっぽいものが生まれる、でも移り行く」なんてものです。
答えのないものを頑張っても、進んでも突き破っても一歩引いても、何が起きるかわからない。
「プチ子さんのお弁当って可愛いですよね」と言っただけ、ただ言っただけなのに。
毎日彩緑のお弁当を作って見せてくるようになり、なんだか褒めて欲しい人間になっている。
方や、「何よ、あげないよ、プイ」と欲しがったと思う人もいたりと色々です。
答えのないものを頑張ると、何に頑張っているのかわからず、成果も出ないので疲れ果てます。
人間関係における我慢と頑張りの組み合わは、人といることをとにかく疲れさせ、人間嫌いにもなりえます。
※頑張りの中身は、頑張っても報われないスピリチュアル「報われているけど気づきにくい」をご覧ください。
ポイント:自分を抑える癖
我慢と頑張りが相互のなさに繋がります。
[我慢・頑張り=自己にこもる意識状態]

我に慢心する、我慢。
我を張る、頑張り。
共に外側の他に向けた意識ではなく、内に取り込み、自己認識を強めて他者認識を弱める内向の社会的在り方。
自分の世界に偏り、こもる意識や精神を強めたさま。

自意識が強い内省タイプ。
内向性、自律傾向、内観、内省力があり、責任感が強い、周りを気にしすぎる、気づきすぎる傾向があります。
これに該当する場合、この世で最も何が起きるかわからない“公共場”で、答えのない“人間関係”をすると、他人との関わりを相互ではなく自分の内側のみで把握しようとすることが起きます。
受動です。

受動的になると自分をまず抑えます。
自律がある人ほどまず抑えます。
「まず抑える、受ける」を継続すると癖になります。
良い悪いは抜きにして自己抑圧が起きます。
抑える、自己内部にこもる・受動状態によって、『相互・循環』できるかどうかは自分次第ではなく相手次第になります。
相手がこちらの状態を理解できる人、思いやりや尊重のある人であれば相互になれますが、そうでなければ一方通行になるため疲れやすくなります。
ちなみに…
抑えない人は疲れません、が、周囲を疲れさせます。
抑える人には抑えない人が凹凸合致しやすく、吸い付くように近付いて来ることが起きやすいです。
※いつの間にかエネルギーを削られているケースは、【心を護る人と消す人】人といると疲れやすい人が気を付けたいこと『無意識テイカー』をご覧ください。
人に会うと疲れる原因
理由の次に紐解きたいのは、根本の原因です。
ネガティブにお伝えすると、サンドバック状態。
この原因となるのがこちらです。

人に会うと疲れる原因は、伝える力の欠落。
※自己開示・自己表現がない
抑える癖があっても、その後に発することでバランスは保たれます。
例えば、人の話をよく聞き、自分の話もする人と一緒にいる。
向こうから話をしてくれる、さらに聞いてくれるのでこちらも話せる関わり方をしてくれます。
相互交流を作ってくれる人は受動と発信のバランスを持ち、こちらは疲れにくくなり、むしろ楽しい時空になると思います。
抑えることは気質や性質、性格でもありとても大切な自分らしさの一つです。
しかし、抑えるだけで発さなくなった時、自己開示や自己表現がなくなり、伝える力が衰退します。
このような方が当てはまると考えます。

・相手に合わせる
・一人が気楽
・人に自己表現しないが一人の時はする
・人に自己開示しないが動物や子供にはする
・気を使いすぎる、周りが気になる
・なんでもまず「うん」と言う
・断れない、「No」と言えない
・エネルギーが弱い
・余裕がない
ポジティブな言い方をすると、優しすぎる。
ネガティブな言い方をすると、怖がりすぎる。
自己抑圧が癖になると受動が定着します。
「どうして受動が定着したのか?」を考えると、そこに楽があったからというのが私たち人間のさがです。
伝えるより伝えない方が楽なんです。
伝える力の欠落は、伝える力の未発揮。
自己表現ができていない表れであり、自己開示しないメンタル。
以上から、
疲れるのは、自己開示せずに人間関係を図る受動スタンスの癖にて、伝える力が衰退したため。
という見方です。
※合わない人に疲れる場合は、【大切なことを思い出す】波長が合わない人に疲れる時の秘訣 をご覧ください。
人に会うと疲れるスピリチュアルな理解
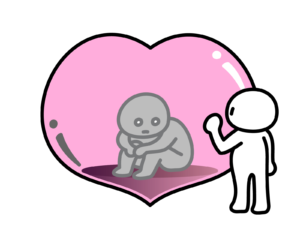
スピリチュアルな解釈:心を抑える
顕在的でも潜在的でも、伝える以上に伝えないことを少しでも、「楽だなぁ」と思ったら自発的なカルマを生んでいます。
カルマのポイントは、自発的に行為のエネルギーと責任を生み出していること。
心を抑え、本音を抑え、真意を抑える。
カルマによって心を抑えることが当たり前になり、受動的になり、我慢や頑張りを優先しやすくなり、人間関係で疲れやすくなります。
※この抑える行為によってエネルギーは流れず、内部で停滞して蓄積する
心の声があっても押さえて出さないことが「当たり前」になり、嫌なことを自らに強いて我慢と頑張りを優先してもそれを味わい続けられるようになります。
心を抑える行為を何度も何度もすると、自分の心がわからなくなる可能性があります。

心を執拗に防衛しようと過保護になり、損害回避、適応障害、精神疾患に繋がる可能性があります。
当たり前になるとわかりにくくなりますが、心を抑えることは大きな損害を内部に生む行為、ストレスも作ります。
ストレスはエネルギーを抑える重荷となり、邪魔となります。
邪な悪魔が憑きます。
邪な悪魔は、これからも伝えない方法を選び、現状維持を図ろうと頑張ります。
スピリチュアル(精神性)とは自責を意味します。
自らの思考と行動を認めて自覚する意識や精神ですので、物事を改善する際はスピリチュアリティがとても重要。
自己抑圧を恒常化させ、自己開示せず、自己表現しないことを選びやすくするカルマを作った。
そして何より、心を抑えることが当たり前になる。
これが人との関りに疲れるスピリチュアルな理解です。
※友達に疲れる時のスピリチュアルは、【いらない友人関係?】友達に疲れるようになった時に大切な自己理解 をご覧ください。
疲れないために:「伝える」
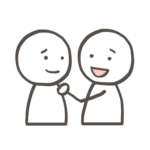
これまで伝えたいと思っても抑えていた、それを伝えることで滞留エネルギーは流れていきます。
と、これが本質ですが、何を抑えていたか一つ一つ覚えているのは難しいので、
見つめたいのは疲れる在り方となっている、心を抑えること、伝えないを選ぶことの改善です。
・『心を抑える在り方』
・『伝えないを選ぶこと』
これら二つを一挙に改善する方法となるのが、抑えずに伝えることです。
「言った方がいい、こう思った、わかってもらった方がいい、伝えたい」
「発そう、伝えよう、表そう」など心が欲したものを相手に伝えることでカルマは流れます。

欲するものがなければ、それは関わる相手に興味を持っていない可能性がある、または自分を抑える癖が過剰であり、欲求や感情まで抑えてしまっています。
精神病状がある場合は回復が必要ですが、そうでない場合、心の声を聞くと欲があります。
自己愛は常に自分を喜ばそうと、多くを欲しています。
その欲のままに従い、「こうなって欲しい」を狙うのではなく、自分の意思や状態、疲れてしまうこと、疲れないためのアイデアを相手に伝えるのが方法です。
※繊細な人へ向けた内容は、【繊細な人の対人戦略】人と話すと苦痛で疲れるようになった時のポイント をご覧ください。
具体的に:自己開示、謙虚に伝える

「あんたって一方的じゃん、こっちも一方的になんなきゃ飲み込まれるから疲れるんだよね、クチャクチャ」
ではなく。
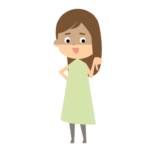
「私ってHSPだから疲れやすいの、察して欲しい」
でもなく。
要望や他責の投げつけではなく、自分のことを相手に伝える自己開示がエネルギーを流し、カルマを解消し、疲れる要因をなくします。
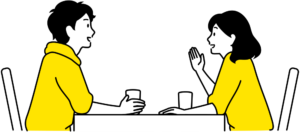
相手が賛同してくれるかどうか関係なく、自分の心の意思や気持ちを伝える、些細なことから始まる伝えるキャンペーン。
例えば、「私はこのカフェに行きたい」
「次は私の話を聞いてもらっていい?」
などなど。
他にも、自分が疲れやすいメンタル、在り方であること。
自分を抑えがちで、伝えるのが苦手だけど伝えたい意思があること。
改善できるできないにかかわらず自らどうにかしたい意思があると伝えると、それは相手と関わる意思がある表現にもなるため、聞き入れてもらいやすいと思います。
それで関わらなくなるのであればそれまでの相手。
または、自らが相互交流を本当に求めていない相手だと、自己理解にも繋がります。
心に発したい気持ちがあるかどうかを見て、あるなら伝える。
伝える行為が大切です。
利益どうの関係なく、伝える行為、この行為が自己を変革します。
蓄積しているエネルギーを流し、内部を浄化し、物事を改善させ、新しい自己を創造していきます。
疲れにくい自分を一歩一歩構成することができます。
「こうなって欲しいから伝える、伝える結果がちゃんと返ってきて欲しい、自分にとっていいようになって欲しい」
など要望や期待、利益着眼を目的にするとエゴが強くなって逆効果になってしまうのでお気を付けください。
あくまで自己開示や自己表現することを目的に『伝える行為』をして、『心を抑える』『伝えない道』を選ぶ自分を変えることが改善の主体となります。
※気の使いすぎは、相手も疲れる優しさの呪縛【気を使いすぎて疲れる人に大切な理解】をご覧ください。
最後に:疲れることは人間関係を見つめる機会
「疲れる」時。
相手を見つめ、さらに自分を見つめるチャンスになります。
「自己開示のない人間関係、私は何を求めているのか?」
私自身、人に合わせるのが癖であったため、相手に利益を与えることにフォーカスしてしまい、いつのまにか人間関係は労働になっていた時があります。
疲れてばかりで、関わりを心から楽しむことは生育と共に減っていました。
相手に利益を与える労働の実体は、自分を抑える癖と心の声を聞かない当たり前(カルマ)でした。
自己開示もなく、自己表現もない。
人見知りでもあるので性格の問題かと思っていた時もありましたが、実際には楽を選んだが故の恒常化であり、リスクを減らして関係性を作るという策略。
失礼でした。
私の場合、相互交流のなさは相手への敬いのなさ。
心の声を無視し続けてきた暁として、心に怯え、「心をなんとか護らなければ」と空想にふけて不安を自発的に作る自己世界のこもり。
相手を真に見ていませんでした。
伝える行為は相手を見ている証拠です。
相手にもそれを知らせる表現になります。
人の気持ちはわかりませんので、伝えて初めて繋がります。
「伝えないとわからない」もそうですが、それ以上に理解しているのはこんなものです。
「伝えると、お互いに関わりを作り合える」
伝えるものが心の声ならば、より深い関係性を作り合えることと思います。
答えのない人間関係、自分がルールを作るでも相手が作るでもなく、その人その人との関わりでお互いに作り合うもの。
人間関係のルールは宇宙の星々と同じだけある。
多様性の極みを遊び楽しむためにも、多彩な人間イロハを実りあるものにしていきましょう。
そのためのご参考になれば幸いです。
ありがとうございました。